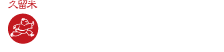かくして昇和亭は「一杯のラーメンが一軒の店舗を生み出した」というストーリーが評判をよび、お陰さまで“昔ラーメン”は 大ヒット商品となって、昇和亭の看板ラーメンになりました。
やがてお客様からは 「Tラーメンの原点と言うべき“昔ラーメン”が、新店でしか食べれないのはおかしい、何で他店(特に本店)で出さないのか」 という声が訊かれるようになりました。
実は、僕たちはその声を待っていました。お客様のその要望がピークに達した頃、全店一斉に昔ラーメンを発売する予定で、 その準備を進めていたのです。 オープン以来、昇和亭の厨房は社内的に“昔ラーメン調理実習研修所”として全社員の新技術習得の場となっていました。
やがてすべての社員がその技術を習得し、昔ラーメン全店展開のための厨房用具・機器の手配も完了したころ、 僕はある人からスルドイ指摘をされました。
その人は僕の母。すでに現役から退き、夫亡きあとの残された人生をエンジョイ中の、悠々自適の温泉バーサンです。 バーサン曰く「ひとっちゃ(僕のこと)、昔ラーメンにノットット(乗っかってるもの)、あら違うばい。 あらシナチクじゃなかばい。」
僕・・・・ 「そらメンマたい。」
バーサン・・「メンマちゃ何ね?」
僕・・・・ 「タケノコたい。シナチクちゃ何ね?」
バーサン・・「タケノコたい。」
僕・・・・ 「オンナシ(同じ)やろーもん。」
バーサン・・「んにゃ、ちごとっ(いや、違ってる)。」
・・・
と、まあこんなやりとりでありましたが、その途中で僕はハタと気づきました。 そういえば母の言う“シナチク”とは“支那竹”のことで、昔の久留米のラーメンにはコレが乗っていました。 らーめんが“支那そば”と呼ばれていた戦後間もない頃は、久留米の屋台のオヤジさんにとってメンマなどの中国食材など手に入れる術もなく、“やむなしメンマに似て非なるもの”、いわるる“シナチク”を代用としていました。 それは決して“支那の竹”ではなく、“八女”の竹でした。久留米の隣町・八女特産の“干し竹の子”を水で戻し、千切りにしたあと塩と若干の醤油で味付けをして、油で炒めたものです。
さらに、それは食紅で真っ赤に染められて“シナチク”という名で“支那そば”にトッピングされていたのです。 しかしその八女の“干し竹の子”も、昭和三〇年代後半から次第に姿を消し始めました。 そこで、これまた“シナチク”の代用として、久留米の屋台のオヤジさんたちが次に白羽の矢を立てた食材が、 皆様ご存じ“紅しょうが”であります。 「とんこつラーメンには“紅しょうが”」という現在のラーメン界の常識、このルーツが何と、八女の“干し竹の子” だったのです。
僕はショックでした。 完成したと思っていた“昔ラーメン”には、トッピングの部分で大きな落とし穴があったのです。自慢の大リーグボールが、花形満にかるくホームランされてしまった星飛雄馬のような衝撃を受けた僕は、 目前の昔ラーメン全店展開の計画を中止し、“干し竹の子”探しの一人旅に出ました。(実は隣の八女あたり)。
そして長い食材探しの行脚(?)の果てにたどり着いた村が、福岡県内最後の秘境と言われた「矢部村」でありました。 ~だが、そこにはトンデモナイ事態が待ち受けていた!
‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ
第三十三話 昔ラーメン誕生秘話 その3
2013年4月12日 金曜日第三十二話 昔ラーメン誕生秘話 その2
2013年4月12日 金曜日 Tラーメンの支店としては初めて別名を与えられた「昇和亭」。その名の由来は、創業者である父の名“昇(のぼる)”に 僕の会社の企業理念である“調和”の“和”をからめ、その読みは、やはり創業の時代である“しょうわ”としました。 それは、父も“時代”も一番元気の良かった二〇代後半年~三〇年代のころの“昭和”であり、大正や明治などの 現在からかけ離れてしまった骨董の時代ではなく、多くの人の記憶に残っている“見覚えのある懐かしい時代”です。
そんな昇和亭には、やはりそのコンセプトに合った旗印が必要です。
そこで今回支店としては異例の、この店オリジナルのCI(Corporate Identityの略・独自にデザインされたシンボルマーク・ ロゴを必要なグラフィックアプリケーションに決められた秩序のもとで体系的に展開させること)を開発することにしました。今までの僕たちの店舗(商品も)開発がそうであったように、今回も外部の代理店やコンサルタント会社へ依頼するという発想はありませんので、当然CIそのもののデザインはもちろんのこと、店舗の内外装からテーブル・椅子などの 調度品・サイン(看板)類・店内POP・什器・カスターセット(テーブルの上の箸立てや調味料入れ)・壁紙・制服と バンダナ、はては名札に至るまで、ひとつのコンセプトのもと、自分たちの手でデザインしなければなりません。
また僕の場合、外食チェーンでよく見かける“支店はすべて判で押したような同じカタチ”というのがとても 気持ち悪く感じるタイプなので、自分の新店開発に対しては「常に新店は、既存店よりカタチもシステムも進化した ものでなけれなならない」という信念じみたものがあります。 ということは、既存店での様々な問題点を絞り出し、それを解析し、対策を立て、その解決案を新店の基本設計から 厨房レイアウト・機器の開発にまで反映させなければなりません。さらに“物”だけではなく作業オペレーションや 接客サービスという“人”の進化のために、膨大な作業マニュアルの再整備も必要です。 これらすべての作業を、昔ラーメンという新商品の開発・社員への調理教育と同時にやらなければなりませんでした。
いま思えば、そんな気の遠くなる仕事を当時の社員だけでよくぞやったものです。“キテレツ君”の異名をもつS店長など、新人面接をやりながら店舗図面を描き、ついには新人教育の合間に、 建築現場の監督をやりながらも新型スープレンジやオリジナルのグラスディスペンサーまで開発してしまいました。
CI開発を担当した僕は、カリカリ昔ラードの調理実習の合間に暇をみつけては、前途の什器やバンダナなどの 各種デザインをやり、また各地のアンティークショップを廻って調度品の収集(これは以外と楽しい)。 どうしても欲しかった昭和三〇年代の映画のポスターなどは、近郊のアンティークショップではなかなか手に入らず、ついには東北の田舎町まで探しに出かけた思い出があります(山間のひなびた温泉宿に一人で泊まり、風呂上がりには、 近所のこれまたひなびた居酒屋で高倉健になった気分でイッパイ・・・。出張という名目でこんなイキな旅気分を 満喫したとういうことは、ウチの社員には今でも秘密です)。
もちろんこの新展開発の陰には、S店長だけでなく、何人もの社員たちの努力があったのは言うまでもありませんが、 ヤハリ仕事というものは、楽しくせんとイカンです。“創る”という仕事は特にそうです。暗い気持ちで設計した店や イヤな気分で開発したラーメンなどにプラスのエネルギーが宿るはずもなく、そんな暗いオーラを発するラーメンと 店にお客さんが集まるワケありませんよね。
ということで、この昇和亭、建坪四〇坪・六二席、千坪の総敷地の中央に位置するかたちで、平成九年一二月に 久留米の南の動脈・上津バイパスについに出現しました。 お陰様で、オープンと同時にこの新しいコンセプトの店は、有り難くも多くのお客様から支持をいただき、 各マスコミからの取材も殺到しました。
・・・だが、しかし!
第三十一話 昔ラーメン誕生秘話 その1
2013年4月12日 金曜日 僕の店に“昔ラーメン”という名のラーメンがあります。僕が営むTラーメンは、昭和28年久留米の片隅の小さな屋台からスタートしました。 創業者はこのコラムの記念すべき第一作にも登場しました町の名物男“ラーメン界の星一徹”こと僕の父であります。
“昔ラーメン”は、その頃の“狂ったように元気がよかった”父の在りし日の姿を思い出しながら、二代目の僕が当時の父のラーメンを現代に復活させたというものです。5年前の発売以来、なぜかこのラーメンの人気には既存のラーメンをしのぐ 勢いがあり、いまやTラーメンの看板商品となった観があります。
しかしながら!この父の魂でも宿っているかのような大ヒット商品となったラーメン。その開発の陰には様々な苦悩があり、 また、このラーメン誕生と共に色んな物語が生まれた・・・(ここでNHKのプロジェクトXのテーマ曲スタート)。
九州のラーメンは今から半世紀ほど前、久留米の町から一斉に産声をあげました。由来は久留米は九州(または豚骨)ラーメン 発祥の地とされております(このコラムの読者諸氏には耳にタコですね、感謝)。現在の豚骨ラーメンの原形は、当時の久留米においてすでに確立していたようですが、今回その時代の父のラーメンを再現するにあたり、僕の前にはいくつかの障害が待ち受けていました。麺の開発に関しては、当時も今も形状(太さ・加水率・ストレート麺)には 大きな変化はありません。といいますか、小麦粉の質や麺の製法が当時よりも格段と向上していて、麺そのものの品質においては、現在の方がはるかに高いもの(まして現在のウチの麺は自家製で昔は外からの仕入れ)になっています。 資料館展示用のラーメンではないので、味を落としてまでの再現は不本意です。したがって、麺に関しては 「昔ながらの形状を守りつつも、その品質(味・食感)は更に向上させる」という方向で決まりました。
次はスープ。創業当時から父のスープには何ともいえない“独特の香ばしさ”があり、そのスープには通称“カリカリ”という 名のクルトンのようなものが浮いていました。実はこのスープの香ばしさは、スープに溶け込んだ“手作りラード”から 醸じだされるもので、“カリカリ”はそのラードを作る際にできる副産物、いわゆる豚脂の揚げ玉です。 ラーメン業界には早い時期から加工された市販のラードが出回りはじめ、現在ほとんどのラーメン屋さんはこれを使って いますが、父はずいぶん長い間、自分のラーメンに入れるラードは自分で手作りしていました。 といっても当時は全家族が労働力という家内制手工業です。僕が小学生の頃は、肉屋から仕入れた豚の背脂の塊を、 せっせと基盤の目に切るというラード作りをいつも手伝わされていました(悲しきタダ働き)。
そんなガンコ職人の父も、味のライト化志向という時代の波には逆らえなかったようで、いつの間にかこの手作りラードは Tラーメンから消えてしまいましたが、“昔ラーメン”のスープの決め手は、この“カリカリ”の浮いた手作りラードの 再現に掛かっていました。
ところが、この手作りラード(昔ラード)の調理技術を持っているのは、僕と、父の最後の弟子と言われた本店のI店長だけです。この技術を全店の全正社員(当時5店舗・正社員数約30数人)に伝授しなければ なりません。正社員たちの技術習得までの時間には個人差があり、拾得の一番遅い社員に合わせると、せっかく完成した商品も発売がいつになるか見当もつきません。かといって未習得の社員を残したまま、発売の見切り発車を することは、不良品を販売することと同様、絶対に許されません。
そこで僕は考えました。「昔ラーメンそのものを コンセプトにした新ブランドのラーメン店を作ってしまおう。昔ラーメンは、その店限定の看板商品にすればいい」と。
かくして、一つのラーメンが、ついに一軒の店舗を生みだすことになったのです。やがて屋号が決まりました。 名はTラーメン「昇和亭(しょうわてい)」
第三十話 飛んだ話
2013年4月12日 金曜日 ついこの間まで千年説だ21世紀だと、騒いでおりましたが、はや2002年。スタンリー・キューブリックの名作SF映画「2001年宇宙の旅」の時代をついに越えてしまいました。30年ほど前のこの映画に描かれていた未来は、果たして訪れているのでしょうか?そんな質問を、この映画を知っている2人の友人にしてみました。
ハイテク畑のある友人は、あの映画の“宇宙開発技術の進歩”の部分を捉えて「重力を発生させる回転式巨大宇宙ステーションは現在まだ完成してないし、一般市民の宇宙旅行もまだ現実化してないが、近い将来それらは確実に実現するだろう。しかし、この映画に登場する巨大なコンピューターに関しては、いまの方が技術的にはるかに進歩し、小型化している。従ってバランスで見れば、現在は、ほぼあの映画の世界と同レベルの技術進化を遂げている。
しかし、あとの“意志を持ったコンピューターの謀反”とか、宇宙を漂う“モノリス(黒い石版)”などは非現実的で問題外だ」こんな話を、やや大槻教授ににている彼は学者が研究論文でも発表するかのごとく無感情で話してました。
次に、心や精神に重きを置いて映画鑑賞をする友人に訊いてみました。
彼曰く「あの映画は進歩した技術文明を楽しむ映画ではない。まさに“意志を持ったコンピューターの謀反”と、宇宙を漂う“モノリス”の存在こそがこの映画を意味あるものにしている。この映画のテーマは、人間の存在意義を人間自らが無視し、機械文明に溺れながら天(宇宙)の意志とは違う方向へ進んでしまったことに対する“神の啓示”だ。悲しいことに、この問題はいま現実化してしまった。
たとえば、外で友だちと遊べず、部屋のパソコンに籠もった少年たちは、シュミレーションゲームの“面白さ”と、現実の戦争の“悲惨”さの区別がつかなくなろうとしている。さらにはインターネットを利用した性犯罪の増加・・・等々。これらの現象は、もはや“神の啓示”だ。30年前にあの映画が与えてくれた警告を私たちは無視している!何ということだ!嗚呼!」といって、興奮したり嘆いたりの感情豊かなこの友人をなだめながら、僕は思いました。
「いや~それにしても、同じ1本の映画でも人それぞれ色んな捉え方・観(み)方があるもんだな~」と。
はい、ここで“宇宙”からイキナリ話は飛んで、内容は縮んで庶民化してしまいますが、・・・“1杯のラーメン”。これもやはり食べる人によって色んな感じ方があるんでしょうなぁ。なんか飛びすぎて苦しいまとめでした。
第二十九話 愛の貧乏脱出大作戦・最終章
2013年4月12日 金曜日夜の合川店、その暗い駐車場の片隅にうずくまる黒い二つの影。いい歳したおっさんがウンコ座りで向かい合い、何やら話し込んでいます。S店長が帰ろうとする中山さんを必死で説得しているのです。
テレビクルーはそんな二人を遠巻きに捉えながら、状況に変化があれば電話で僕に知らせるようになっています。最悪の場合僕が駆けつけ、中山さんに対して最終的な結論を下すようになっていますが、僕はS店長を信じていました。
しかし、二時間待っても三時間待っても、何の連絡もありません。この修行に強い疑問を持つ中山さんのガンコな耳には、S店長の言葉はなかなか聞こえないのでしょう(そのガンコさで修行もやり通せばよいものを・・・)。
夜もしだいに更け、やがて深夜も1時を過ぎた頃、突然僕の携帯が鳴りました。電話の主はS店長・・・・、そして一言。
「大丈夫です。中山さん修行続行です」
僕は感動しました。それは、考え直してくれた中山さんに対してではなく、幾つも年上の、それも極限状態のガンコオヤジを説得した若いS店長に僕は感動したのです。かつて僕に反発し、僕の元を離れた経験を持つS店長は、中山さんに向かいながらも、本当は昔の自分の姿と向かい合っていたに違いありません。「何で俺たちの思いが解らないのか!」薄っぺらい言葉ではなく、相手のために本気になって心から訴えるS店長の魂が、極限状態のガンコオヤジの心を開かせました。
翌日、修行三日目の朝。中山さんは決められた時間よりも早く出勤してきました(ここからはテレビでご覧のとおり)。彼は、昨日とは打って変わって、すべてが吹っ切れた顔をしていました。
「二日間駐車場の整理やって、どうでした?」僕の問いに彼は答えました。「正直言って、昨日はもう修行を辞めて帰ろうと思いました。でも今、やっとわかりました。この二日間の修行は、お客さんへの“感謝の気持ち”これがテーマだと」僕は彼をじっと見ながら、目で伝えました。“あなたが今一番感謝すべき相手は、S店長だよ”「今から多久まで行こう」
その場で僕は、中山さんの店で集中的な調理実習を行うことを決め、早速、食材・調理器具を車に積み込んで、佐賀県多久市に向かいました。残された修行期間はあと四日です。
それから三日三晩、彼はもう何の疑問も持たず、徹夜の実習をひたすら頑張りました。すべてを受け入れた人間というものは、こんなにも劇的に成長するものなのでしょうか。元々ラーメン屋として基本的な技術があるにしても、僕が独自に考えた“てぼ(麺の茹でカゴ)から放り上げた麺を、空中で素早く麺揚げ(柄付きの金網)で受け、湯切りする”という麺揚げのワザも、何とほぼ三日でマスター(テレビではこの麺揚げ実習シーンが最も話題になった)。
同時進行中の“呼び戻し豚骨スープ”の基本調理も、何とかカタチにはなってきました。
そして修行最終日“試食会”の日がやって来ました。審査員は僕たちTラーメンの店長をはじめ、社内歴戦の“豚骨ラーメンのツワモノ”たちです。彼らの厳しい舌を満足させなければ、この修行は不合格となります。・・・
ところが!中山さんはやりました。この日、親父のために駆け付けて来てくれた長男と二人で、見事に素晴らしいラーメンを作り出しました。審査員たちは満足し、まずは合格のようです。感激している中山さんに、僕は最後に言いました。「俺達は今日、久留米に帰る。明日からは中山さんは一人になる。それから中山さんの本当の修行が始まるんやけど、呼び戻しスープは、そんなに簡単なもんじゃなか。ばってん、これも縁、中山さんとはずっと付き合う覚悟がある。その意味で、俺の新しい外弟子の一人として“合格”」と。
かくして中山さんの愛の貧乏脱出大作戦の修行は終わりました。修行後の新装開店の日の売上は、目標の三倍を記録しました。
収録のスタジオでは、みのもんた氏やゲストたちが、VTRの中の「達人に感謝、お客さんに感謝、そして息子に感謝」という、そんな中山さんの姿に感動して涙ぐむという場面もあり、スタジオの一般参加者に対するアンケートでは、なんと全員が“合格”のパネルを表示するという(前代未聞?)、感動のラストでこの番組は終了しました。
放送後三ヶ月を過ぎた現在も、多久の大将ラーメンは、修行前の十倍近い驚異的な売上を維持しています。S店長や、その他の店長も、時折自分の公休を潰して(僕の知らないうちに)多久までスープ指導に通っているようです。有難いことです。
この番組をとおして、僕は思いました。本当の“達人”は、テレビにほとんど出ることのない、この店長たちなのだと。
第二十八話 愛の貧乏脱出大作戦(3)
2013年4月12日 金曜日 中山さんは初日の修行内容が納得できずに、遅くまでヤケ酒でも飲んだのでしょうか、一時間も遅れてやって来ました。旅館からの、すでに陽が高く昇った二キロの道をダッシュで駆けて来たらしく、彼は服を着たままシャワーを浴びたような姿でした。
彼は方で息を弾ませ、喘ぐような声で詫びていましたが、僕はそれを許さず、今日も引き続き合川店での駐車場整理を命じました。中山さんとしては、「とりあえずこの場をなんとかつくろえば、今日から予定されている念願のラーメンの調理実習ができる」と思っていたようですが、彼のその甘い考えは僕に見抜かれ、打ち砕かれてしまいました。
更に僕は、この本店から二キロ先の合川店まで徒歩で行くように命じました。あとの彼はもう、自暴自棄。合川店までの道をふてくされたように歩く彼の姿は、歩道に立ち昇る陽炎越しに、望遠レンズがしっかり捉えています。
テレビクルーがやや離れた位置から尾行していることに気づかないまま、携帯電話で誰かと話し始めました。彼の怒りは頂点に達しているらしく、高感度の小型ワイヤレスマイクが自分の胸元に仕込んであることさえ忘れているようです。音声さんのヘッドフォンに聞こえてくる声は・・・「ぞーたんのごと(冗談じゃない)なーんが修行やろかい!朝からオーライオーライば、クソばかーんごつ(ばかみたいに)一日中しよったばい。今日もばい!」
やがてなんとか駐車場整理を始めてみたものの、恨みつらみの毒をまき散らしながらの仕事です。本人が仕事の意味を理解できないまま続けれる仕事などありませんし、ましてお客さんへ感謝が伝わるわけがありません。昨日にまして照るつける太陽が、ようやく西へ傾きかけた頃、本店にいるぼくへディレクターから緊急の電話が入りました。
その前に、この放送をご覧になった皆様はご存知とは思いますが、テレビでは、~店から出てきたお客さんが、駐車場整理でくたくたになった中山さんの姿を見て、「頑張ってください」と声をかける。その言葉で目が覚めた中山さんは、この仕事の大切さを知る。~という流れになってました。これで間違いはないのですが、放送時間の関係でしかたなくカットされた部分を皆様にお伝えしましょう。
そのディレクターからの電話とは、「中山さんは修行を断念するそうです」というものでした。予感はしていましたが、ついに最悪の状況になってしまいました。ディレクターはいいました「達人が直接本人を説得できますか?」・・・僕はあえてそれはしませんでした。なるほど僕が今から本人に会って、疲れきった心を癒しながら、この仕事の本当の意味を論してあげれば、彼はスグにでも立ち直るでしょう。
しかし、出題の答案をスグに教えるということは、「とことん考える」という、人間が生きていく上でとても大切な能力を失わせるような行為だと思ったからです。
そこで僕はS店長を行かせました。このS店長というのが、かつて僕に反発し、一時期僕の店を離れてみたものの、やがて自分なりに答えを見つけたのか、いつの間にか一皮も二皮もムケて戻ってきた男です。
かくして、S店長、僕、テレビクルー、そして中山さんにとって、暑くて長い長~い夜が始まりました。
第二十七話 愛の貧乏脱出大作戦(2)
2013年4月12日 金曜日 七月二十日・修行初日。貧乏脱出をめざし意気揚々と現れた中山さんは、とっても元気でした。絵に描いたようなハリキリおじさんです。
そんな彼に、僕はいきなり“駐車場整理”を命じました。場所はTラーメン合川店駐車場。バイパス沿いのこの店は、一日の客数が千人を超え、そのほとんどは自家用車による来店という、極めて忙しい郊外型の店です。 その日は朝からの猛暑で、日の出と共に急上昇する気温は、午前十一時にはもう三六度に達していました。そんな。靴底を溶かすほどに灼けた炎天下のアスファルトの上で、彼の修行が始まったのです。
ところで今回の“修行”に、僕はあらかじめテーマを決めていました。ラーメンに限らず他のあらゆる職人の世界も同じと思いますが、僕たちの“呼び戻しスープ”の技術も、わずか1週間足らずの修行期間で取得することなど、経験者でもまず不可能です。“呼び戻しスープ”の洲業はこの番組の収録が完全に終了して、ゆっくり、何年も時間をかけて教えることにしました。弟子が入門を希望する、そのきっかけは“テレビ”でも“職業安定所”でも、同じこと。「縁は縁」です。僕は中山さんを本物の外弟子にする決心をしました。
ひとりの人間の、生活や人生を左右するような役を引き受ける以上、当然の決心でしょう。そして、この(番組上の)修行では、彼に技術よりも、僕自身の“思い”を伝えることにしました。それは「来てくれるお客さんにありがとう」「職場の先輩・同僚・部下にありがとう」「自分の家族にありがとう」そんな思いを伝えたい・・・。そう、この修行のテーマは「感謝」です。
ところが、そんな師匠の思いなど知る由もなく、目下駐車場整理中の弟子。「オーライ、オーライ、ストォーップ!」午前十一時にスタートし、陽が傾きかけても次から次へと押し寄せる車に向かって、この繰り返し。体力には自信があるはずの彼も、最所の気合いは次第に薄れていきました。さらに、昼間の太陽熱を思い切り吸い込んだアスファルトの駐車場は、陽が沈んでも気温は一向にさがらず、オマケにこの日は風のない熱帯夜でした。 人間、疲労が極限に達すると、その人の顔からは一切の装飾的な表情は消え、その時の心そのまんまの顔になるようです。一見無意味とも思えるこの苦しい単純作業の繰り返しの果てに、全身水を浴びたような汗とホコリで無惨な姿になった彼の顔からは、笑顔は完全に消え、その目は“疲労”から“疑問”、そして“恨み”の色へと変化していきました。
初日の修行は駐車場整理のみ。深夜二時に終了。やっと帰りついた旅館の階段を這うように上がり、部屋の布団に座り込み、思い詰めたように一点をにらむ彼に、密着のテレビクルーが質問しました(当然僕はこの場にはいません)。「今日の修行から何か得るものはありましたか?」中山さんは吐き捨てるように言いました。
「まったくありません。こげんこと(駐車場整理)して、自分は修行で来とっけんが、意味がなか!」
そして翌日、修行二日目の朝。約束の時間に彼は来ませんでした。
第二十六話 愛の貧乏脱出大作戦(1)
2013年4月12日 金曜日 「捨てる神あらば拾う神あり」と言いますが、魁龍の華々しいオープンを見届けて、ここに残ってしまいそうな念を振り払うようにラー博を立ち去ろうとする、まさにその瞬間、東京のテレビ局から僕にある番組の出演依頼の連絡がありました。
その番組とは「愛の貧乏脱出大作戦」。そう、“売れない店の主人を、その道の達人が貧乏のどん底から救い出す”というアノ番組です。何と僕に、その“達人”役で出てくれというものです。今度は“目からウロコ”ではなく“目が点”でした。「なんでオレが達人や?股間はまだまだ“立人”かも知れんバッテン・・・」
そんなこと言っておちゃらけてみても、受話器の向こうでは、TVディレクターが必死に何か説明しているようです。僕はただ呆然と考えていました。店の数字はどうか知りませんが、いままで一生懸命に商売を頑張ってこられたであろう同業の方の大切な人生が、イキナリ現れた初対面の“達人”から左右されるのです。そんな責任重大な恐ろしい仕事が僕に出来るだろうか?それに耐えれる器が僕にあるのだろうか?
僕が出演を躊躇(ちゅうちょ)していると、ディレクターは「5日後には撮影を開始します。もう時間がありません。いま決めて下さい」僕は一瞬の内に考えました。いろいろあった魁龍のラー博出店の件も、何とか自分なりに整理ができ、ふっと心に隙間ができた途端、降って湧いたようなこの話。もしかしたら神様が、「お前には休む暇なんか与えない」とばかりに試されているのでは?これは天が与えた試練かも?そう思ったら何となく勇気が湧いてきて、遂に引き受けてしまいました。
その後は濃縮された撮影スケジュールが待ち受けていました。局との打ち合わせが2日後の7月13日。撮影開始が18日から約1週間。ロケ地は、佐賀県多久市の依頼人の店と久留米の僕の店との往復ロケ。1日の撮影時間は早朝から深夜まで無制限。当然撮影期間は僕の通常業務は一切できない状態です。
撮影班は何かと、カメラ・照明・音声全て2台体制で、依頼人担当と達人担当の2班に分かれています。VTRのテープは、カメラが一週間2人に向かって回り続けるため100本以上も準備されています。こんなに大がかりなテレビの取材体制は初めてです。僕もこれに対応するべく、社内で店長クラスを中心にチームを作り、受け入れ体制を固めました。
そして撮影前々日、依頼人のプロフィールが書かれた資料が僕のもとへ届けられました。依頼人の名は中山昇氏。
現在、佐賀県多久市でラーメン店を営まれており、離婚後奥さんに息子2人を連れ去られ、孤独な独り暮らしの中でヒマなラーメン店(一日の客数約20人)の経営と道路工事のアルバイトで生計を立てている、絵に描いたような苦労人です・・・・。撮影開始と共に、この人の人生の奥に、僕は入り込むことになるのです。もう後にはひけません。
~かつて司会のみのもんた氏が、「依頼人が修行を断念すれば、その依頼人の店の改装工事も中止し、それはそれで事実として放送します。当番組の方針としてヤラセはしません。」と言われていたのを僕は憶えていますが、いま、撮影を振り返るとまさにそのとおりでした~・・・・そしてついに撮影の日はやって来ました。
第二十五話 新横浜ラーメン博物館に久留米の風
2013年4月12日 金曜日 前回のコラムにも登場したご存知「新横浜ラーメン博物館」、先日ここに“久留米ラーメン”と銘打った「魁龍(かいりゅう)」という店がオープンしました。久留米の皆さんでこの店名を知る人は少ないでしょう。
実際この店の本店は、久留米ではなく北九州の小倉にあります。それではなぜ“久留米ラーメン”なのか? 実は、この店の先代店主が元々久留米の人で、「幸陽軒」(久留米の文化街付近に昭和二七年から四十年まで存在していた幻のラーメン店)の出身なのだそうです。この「魁龍」の特徴は、超コッテリ豚骨というか、ここまで濃度の高い豚骨スープは久留米にも見あたりません。
しかし、久留米のラーメン独特のあのニオイはきちんと漂っております。
新横浜ラーメン博物館の魁龍も、のれんをくぐると、その店内には懐かしい“久留米のニオイ”が充満しており、館内の全国のラーメン店ひしめく中で、その存在をしっかりと“発散”させておりました。天下のラー博出店、しかし羨ましいなァ。ホントは、僕もラー博出店が長年の夢でした。今では新横浜随一の観光スポットといわれるこの施設がオープンしたのが七年前のこと。当時博多代表として館内店舗に選ばれた一風堂の河原さんからのお誘いで、僕は初めてラー博を訪れたのですが、そのときの感動は今でも忘れません。館内のラーメン店に並ぶ幾筋もの長蛇の列も圧巻でしたが、何と言っても“ラーメン”の“博物館”というテーマそのものの斬新さに驚嘆しました。
地階は、壁一面にディスプレイされた全国ラーメン店の丼やらラーメンに関する様々な展示物、そして地下に下りると全国の有名ラーメン店たちを取り囲む、見事に再現された昭和三十三年の夕焼けの町並み・・・。このラーメンをエンターティナーにした天才的演出を目の当たりにして、僕はまさに“目からウロコ状態”でした。
でも、同時に思ったのが「九州の豚骨ラーメンの代表で博多と熊本が選ばれとるばってん、なしてそのルーツである久留米のラーメン屋がここにないとやろうか?」ということ。そして、当時から“ラーメンによる久留米の町おこし”構想を密かに抱いていた僕は、「久留米のラーメン屋は何ばしよっとかいな?豚骨ラーメン発祥の町のくせに、博多ラーメンや熊本ラーメンの陰で目立たない久留米のラーメンの名が、ここに出店できれば全国に広まることは間違いなか・・・。もうよか、いつかウチがここに出てやろう・・・いや、出たい。いや、出していただきたい・・・出れたらイイナァ。」と、イキナリ片思いの恋に取り憑かれた三十六歳の怪しいオヤジのように、ラー博の人波に揉まれながら独りつぶやいていたのを憶えています。
その後もラー博は、次々と新しいラーメンブームを創り出し、今や屈指の“ラーメン情報の発信基地”として全国にその名を轟かせていますが、未だその施設内には久留米のラーメン店の姿はありませんでした。
しかし突然此度の「魁龍」のラー博出店話。この噂を僕が耳にしたのが今年の一月でした。魁龍といえば、そのオーナーの森山君とは去年、一風堂の河原さんの紹介で知り合い、一杯飲みながら互いに意気投合し、付き合いが始まったばかりでした。力一杯ショックでした。七年におよぶ片思いの恋に落ちていた怪しいオヤジは、イキナリの間男(失礼、でも実際ヨカ男です)の出現で、その恋に幕を下ろされ、奈落に落ちてしまいました。
そんな、失恋の痛手に眠れない夜が続くある日、ラー博の岩岡館長が突然、久留米の僕の店に現れました。館長は「K(僕)に今回の出店決定に至るまでの経緯(なんと最終選考まで僕のTラーメンがその候補に残っていた)の説明をしたい。そして、町おこしを頑張ってるKをねぎらいたい」という思いで、わざわざ久留米まで来てくれたのです。有り難いことです。そんな館長の人柄に触れて、僕は吹っ切れました。どうも僕は道を誤りかけていたようです。「僕にとって、ラー博出店の目的が本当に久留米の町おこしであれば、それは僕のTラーメンでなくてもいいはず」このことに気づかせてもらうまでの僕は「我欲」と「使命」の違いを理解出来なかったようです。またもや“目からウロコ”でした。
いま僕は“久留米ラーメン”の看板を背負って関東に単騎出陣する魁龍を心から応援したいと思っています。 今月(七月)十一日、魁龍は華々しくラー博デビューを果たしました。このコラムを書いている今現在、僕のTラーメンの店長たちは・・・実はラー博にいます。 彼らは今、オープニングパニックでごった返す魁龍を、懸命に手伝っています。
第二十四話 ラーメンブームの仕掛け人
2013年4月12日 金曜日 しかしまあ、ひとくちにラーメンといっても色んな話があるもんです。ラーメンネタ一本で二八回も書いとります。このコラムを書き始めたのは二年と三ヶ月前になりますが、ちょうどラーメンブームもピークといわれた頃で、十年以上続いたこのブームも、もう終焉を迎えるだろうといわれてました。ところがどっこい、今このコラムを書いている現在もなおラーメンブームに陰りは見えず、そのフィーバーぶりはなお健在です。
ある専門家は「ラーメンは、もはやブームを越えて完全に国民食となった」といってましたが、はたしてどうでしょう。僕は学者ではないので、社会現象の学術的な要因解析はできませんが、ラーメン屋の僕個人として思うことがあります。
“ブーム”と一口に言いましても、その陰には必ず“仕掛け人”と呼ばれる企画のプロ集団がいます。かたや、新たなブームの「きざし」をいち早くキャッチしてその情報を広く伝える“マスコミ”という仕事人たちがいます。この両者がうまく連動して、はじめてブームという名のいわば“にわか景気”が起こるという仕組みになっています。 当然ラーメンブームの始まりも、この仕組みがうまく働いた典型的な事例でしょう。
しかし、そのブームも十数年続いております。もはやラーメンはその“ブームの仕組み”から完全に自立し、新たな国民食として一人歩きしているのでしょうか?もう仕掛け人たちは不要なのでしょうか?
ところで、日本のラーメンは、同じ麺類のそばやうどんに比べるとはるかに歴史の浅い、いわば“若い”食べ物です。その反面、伝統に縛られることのない自由さがあります。音楽にたとえると、そばやうどんが“クラシック”なら、ラーメンは“フリージャズ”といったところでしょうか、表現自由なナンデモアリの食べ物です。“ブームの仕掛け人”にとって、そんなラーメンという、まだまだ未知の可能性を秘めた若手のエンターティナーはとても魅力的です。気の利いた仕掛け人なら、そのエンターティナーから湧き出る自由なアイデアを小出しにしながら、そのブームを長く続かせることも容易かもしれません。
皆さんには「ご当地ラーメン」という言葉はもうおなじみでしょう。昭和六十年ごろ東北の喜多方と佐野から静かに始まったご当地ラーメンブームは、平成八年の北海道・旭川ラーメンで火がつき、その後、飛騨高山ラーメン、尾道ラーメンへと飛び火して、平成十年の和歌山ラーメンで大ブレイクし、翌年の徳島ラーメンへと伝播しました。
その間の平成六年にはラーメンのテーマパークというべき「新横浜ラーメン博物館」がオープンしています。平成八年の旭川ラーメン以降のご当地ラーメンブームは、実はその「新横浜ラーメン博物館」の天才仕掛け人たち(実は僕の友人)が仕掛けたブームといわれています。
その天才たちは、全国ご当地ラーメン発掘のネタも出尽くした今、新たなる発想でブームを仕掛けようとしています。そのキーワードは「ご当地ラーメン」から「ご当人ラーメン」へ。
ラーメンが名物の土地よりも、ラーメン屋の名物オヤジにスポットを当てようという動きです(最近の某カップラーメンのCMからもその傾向を感じます)。彼ら仕掛け人がいる限り、ラーメン“ブーム”はまだまだ続くでしょう。そして、ラーメンがそばやうどんのように「音楽でたとえるなら“クラシック”」といわれるには四百年の時間が必要のようです。