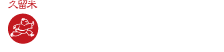「昔と変わらずおいしい。そうお客さんに思わせるには、見えない〈味の進化〉が必要だ」これは、東京の老舗ラーメン店〈春木屋〉の店主の考え方で、業界では〈春木屋理論〉とよばれています。これは大変的を射た理論で、僕も昔から同じ考えでした。
皆さんも経験があるかもしれませんが、たとえば、かつて通ったある食堂の大好きなメニューを、十数年振りに食べてみたら、「何か物足りない。さては大将、味を変えたな」と感じる。そして「この店は味が落ちた」という烙印を押してしまう・・・。実は、大抵の場合、そこの大将が味を変えたのではなく、あなたの味覚が変化(または進化)したのです。「十数年振りに食べても変わらずおいしい」と思った場合、それは恐らくそのお店の味が、あなたの味覚と同様に進化していたのではないでしょうか。
手前味噌ですが、ウチのラーメンの豚骨の使用量は、かつて初代が屋台を営んでいたときの2倍近いものになっています。加えて元ダレやトッピング、主にチャーシューはより上質の肉に進化させています。また、ウチには〈昔ラーメン〉という商品がありますが、もしそれを元ダレやトッピング、さらに豚骨の使用量まで50年前と全く同じものにすれば、ほとんどのお客さんは「物足りない」そして「味が落ちた」と思うでしょう。
そんなことを考えていたある日、即席麺大手メーカーの担当者からこんな話を聞きました。「当社の役員たちが、入社当時の商品の味を懐かしがって、その味そのままの復刻版の商品を発売したところ、全く売れなくて、すぐに製造中止になったんです」と。 人の味覚は進化します。その味覚の進化に付いて行けない店や食品メーカーは衰退するのかもしれません。
ハナシは変わりますが、これをお読みの奥様、ン十年振りの同窓会なぞに行かれることもおありでしょう。その折にでも、ン十年前の男子の奥様を見る目と、現在の奥様のご容姿が、共にどう進化しているのかをご確認されてみるのも一興ですね。
‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ
第百十三話 ラーメン進化論
2013年4月16日 火曜日第百十二話 やっぱり雪が好き
2013年4月16日 火曜日 僕は戌(いぬ)年生まれです。だから雪が大好きです。雪が降れば庭かけまわりたくなります。うちはマンションなのでバルコニーをかけまわります。しかし地球温暖化の問題が叫ばれている昨今、確実にこの久留米でも雪の降る日は少なくなりました。去年の冬など一度も雪らしい雪を見ていません。僕が子供の頃(約40年前)の久留米の冬といえば、平野部でも寒い朝など軒下にはツララが下がり、道端の水溜まりに氷が張っていて、子供たちはその氷を長靴で割ったり、霜柱を踏んでサクサクとした感触を楽しんだり、ラジバンダリ(?)しながら学校へ行ったものです。今ではほとんど見ることのできない懐かしい冬の朝の風景です。
しかしこの冬は比較的雪が多いようです。11月下旬には最初の雪が降りました(福岡地方では記録的な早さ)。雪好きオヤジにとっては願ってもない今年の冬です。そしてついに昨日の天気予報が「明日の筑後地方は大雪となり、平野部でも積雪するでしょう」と言ってくれたのです。しかも明日は休日。「久々の雪景色ばハライッパイ見らるっばい♪」と、僕は喜々として床につきました。そして今朝、町の雪化粧を楽しみに早起きしてみると、なんと雪はおろかピーカンの青空。「くそっ予報のおっさんにだまされた!ヒマワリもヒマワリたい!宇宙から何ば見よったとか!」と、ワケのわからない逆恨みをしながら背振山を見てみると、こりゃまた真っ白な雪化粧。そうです、北西の大陸からやって来たスジ状の雪雲さんは、福岡市に雪を降らせながらも、標高1,055メートルの背振の尾根を超える根性がなく、そこで持っていた雪をみな背振の山にぶちまけて、久留米には知らん顔しとったとです(たぶん)。
ばってんBUT!ふふふ・・・、ワタクシはそんなことではめげません。実は来る2月21日、東北・喜多方のラーメンフェスタに、うちの大砲ラーメンが出店するのです(出店3回目)。そう喜多方といえば、ラーメンの町としても有名ですが、雪好きにとっては何と言っても、会津磐梯山の懐に抱かれた雪、雪、雪のあこがれのまちでもあります。フェスタのラーメンブースには食材の冷蔵庫はありません。ブース裏の積もった雪に穴を掘り、そこに保管すればいいのです。磐梯山まで少し足を伸ばせば、道路の両脇が3~4メートルという高さの垂直の雪の壁になっています。そんなところなのです。全く九州では想像もつかない雪国であります。
せっかく喜多方で「ラーメン町おこし」のお手伝いをさせていただくのに、雪ばかり楽しみにしているようで、何だか不謹慎ですね。
・・・それでもやっぱり、雪が大好きな戌年オヤジでした。
❄❅❄❅❄❅❄❅❄❅❄
PS これを書き終わって窓の外を見ると、吹雪でした。予報のおじさんと衛星ヒマワリさん、文句言ってゴメンナサイ。スジ状の雪雲さんも「根性なし」ではありません。ゴメンナサイ。さて、今から雪の露天風呂に行ってきま~す♪
第百十一話 もうひとつの熱風録(最終章)
2013年4月16日 火曜日 今でも母はよく言います。「アン人に白シャツ買うてやっても、一晩で赤シャツにしてしまいよったとばい」要はケンカ好きの父は、いつも殴り倒した相手の返り血を浴びて帰って来たということです。当時は敗戦の傷跡も癒えぬ復興期で、人々の心もまだ荒れていたのでしょう、腕っ節が強くなければ、小さな屋台などチンピラにひとたまりもなくひっくり返されてしまうような時代でした。父のケンカ強さも、ある意味必要だったのです。一方、父は屋台仲間の用心棒的存在でもありました。ところが母にしてみれば、そんな暴れん坊など、母が育ったのどかな村には1人もいませんでした。米俵を2俵も3俵も担げる大力のマッチョな叔父はいましたが、性格はとても温厚な人でした。そんなのんびりした環境で育った母ですから、父の傍若無人な暴れぶりが、それはそれは恐ろしかったそうです。ある雪の夜、酔狂を回して家中大暴れする父から逃げるために、母は小さな僕を抱いて外へ飛び出し、行くあてもなく、木の下でふるえながら雪の降る夜を明かしたという記憶が、いまでも僕に残っています。
しかし人間は環境に順応する動物です。毎日を父に脅えながら暮らしていた母も次第に慣れ、肚も据わってきました。その頃は毎日夕方になると父が先に家を出て屋台を開き、母は子供(筆者)の世話をした後、送れて出勤(?)していたのですが、そんなある日、母はある情報を耳にしました。屋台に父1人しかいない時間帯に、毎日顔を出す飲み屋の若いお姉ちゃんがいるというのです。そのお姉ちゃんは父にぞっこんで、父もまんざら悪い気もしていないという・・・。それを聞いた母は当然穏やかではありません。数日後、母は意を決して早い時間に屋台に出向きました。暖簾をくぐってみると、やはり情報通り、そのお姉ちゃんがいました。父は母と目を合わせるなり顔面蒼白。その父の表情と、後ろに立っている母に気づいていないお姉ちゃんは、目をハート型にして父を見つめています。母は、たまたまそこに居合わせた知人に、抱いていた僕をヒョイと渡すと、いきなりお姉ちゃんの後ろ髪を掴み、外へ引きずり出しました。そして引きずったまま明治通りを渡り(当時は車はまばら)、西鉄バスセンターのベンチにお姉ちゃんを座らせ、その横にどっかと座った母は、お姉ちゃんをビシバシ小突きながら、思いっきり説教したそうです。その間、父はただ唖然。当然、その後そのお姉ちゃんは、2度と父の前には現れませんでした。この頃になると、母の度胸と肚の据わり方は、父のそれをすでに超えていたのかもしれません。
さらに、その後大砲ラーメン最大の危機を救ったのも母でした。ある日、近所で火事が起きたとき、なぜか母は、父の枕を抱いて外へ飛び出し、父から失笑を買ったことがありましたが、実は、いざというときの為にと、母は父の枕の中に、父名義の預金通帳を忍び込ませていました。残高何と100万円(現在の価値では1,000万以上)。その後屋台の行政立ち退きが決まったときに、その預金のお陰で、立ち退き後も難なく小さな店舗を出すことができたのです。母のこの内助の功がなければ、現在の大砲ラーメンは存在していません。子供も旦那の有り金も、全てを持ち出して出て行く嫁の話をよく耳にする昨今、こんな話はもうただの昔語りになってしまったのでしょうか。去年喜寿の祝いを終え、現在78になる母ですが、きょうも〈ラーメン醤油〉作りに余念がありません。
第百十話 もうひとつの熱風録(2)
2013年4月16日 火曜日勉強よりも防空壕掘りに明け暮れた母の尋常高等小学校時代は、終戦と共に終わりを告げました。その後両親を亡くし、やがて20代になった母は、諫早の農村を出て、雲仙の麓・島原の某大手旅館に勤めました。実はその旅館が、父との運命の出会いの場所となったのです。何となくロマンを感じますが、実のところテキ屋をやっていた父が流れながれてフラリとそこの旅館に現れ、仲居をやっていた母を見初めたというワケです。 路上に広げたマガイ物を流ちょうな講釈で売りさばき、そそくさと別の町に移動するというヤクザなテキ屋家業の父でしたが、ルックスはまるで映画スター並み(息子の自分が言うのも何ですが)でした。そのマガイ物屋の映画スターは言いました。「あんた、こもしてえーらしかの」(君は小さくてカワイイね)「久留米に来んや?」 身長140センチ足らずの母は、久留米弁が解らないまでも、父の男気を漂わせる雰囲気とルックスに参ったのでしょう、二つ返事で久留米について行くことを決めたそうです。父との約束の日、母は島原から汽車で来ました。いまもJR久留米駅の北側に筑後川に架かる鉄橋がありますが、そこから初めて筑後川を見た母は、本気でそれを〈海〉と思ったそうです。母の村には〈大川〉という川が流れていますが、それは名ばかりで、水深30センチ・川幅2メートル程の小川です。母の中ではその小川が一番大きな川でした。それが九州一の大河・筑後川を見ても、それは〈海〉と思うしかなかったのでしょう。狭い山村育ちの母はその後も、久留米で見るもの聞くもの、驚きの連続でした。 それにしても、国鉄久留米駅で母を待つ父の姿は、くわえタバコで壁にややもたれる感じで、それはそれはカッコよかったそうです。 かくして2人は所帯を持つこととなり、これを機に父はテキ屋家業から足を洗い、兄と一緒にラーメン屋台を営むことになりました。その屋台の名は〈清陽軒〉、所は明治通り第一勧銀前(現在のみずほ銀行。当時そこの交差点は、パリのエッフェル塔前のようにロータリー式の交差点になっていて、その〈ロータリー〉という呼び名は現在も残っている)。昭和20年代後半のことでした。やがて父兄弟は、それぞれ所帯も持ったし、お互いに一国一城の主になろうということで、父は清陽軒から独立し、西鉄駅前の佐賀銀行前で新たにラーメン屋台を開業しました。その屋号は〈大砲ラーメン〉。そう、その一軒の屋台こそが、いまの僕の家業の原点です。昭和33年生まれの僕が物心ついたときには、屋台の前の歩道が僕の遊び場になっており、いつもチョークで歩道に絵を描いて遊んでいました。それはいいとして、母は映画スター並みのヨカ男と結婚はしたものの、いざ一緒に暮らしてみると、その映画スターは大変な暴れん坊だったのです・・・
第百〇九話 もうひとつの熱風録(1)
2013年4月16日 火曜日 以前、このコラムの〈初代熱風録〉シリーズ全7話。有り難いことに大変好評をいただき、たまたまこれを読んだ映画関係者から「このシリーズをストーリー仕立てにして映画化したい」との打診が僕に届くほどでした。その〈映画化〉のはなしは別として、我が家業の過去のエピソード集は、ある意味大砲ラーメンの社史としてのみならず、久留米のラーメン史の一端としても、これは貴重な資料になるのではと思いました。
そこで〈初代熱風録〉では充分に書けなかった主人公・香月昇の妻、つまり僕の母の話を〈もうひとつの熱風録〉と題して書き綴ってみたいと思います。
母の名は嘉子、昭和6年生まれです。その母が尋常高等小学校2年(現在の中学3年)の夏、世界史に残る大事件に遭遇しています。それは大東亜戦争(太平洋戦争)末期の昭和20年8月9日の昼前のこと。母の通う農村(長崎県諫早)の小学校はこの日、夏休みの出校日でした。朝礼も終わって掃除の時間、突然村中に空襲警報が鳴り響きました。この空襲のない農村でも、とりあえず生徒たちは防空ずきんを被り、机の下に身を潜めます。やがて空襲警報が解除され、掃除再開。母は、バケツを持って小高い丘の上の校舎から丘の下の井戸まで水汲みに。そのとき母の頭上で爆撃機の音が聞こえてきました。見上げると、自分の真上に銀色に輝く一機のB‐29(当時は小学生でも、その米軍最大の爆撃機のカタチも音も知っていたそうです)がありました。母は「空襲警報は解除されたのに、何で?」と思いつつ見ていると、B‐29は長崎市の方へ向かって行き、やがて飯盛山の向こうに差しかかったあたりで、二つの落下傘(パラシュート)を投下したそうです。母は、水を入れたバケツを持って丘を上り、校庭へ出たそのとき、昼と言うのに目が眩むほどの閃光に包まれました。母は驚きながらも、そのまま校庭を横切り、校舎に入りました。その瞬間、今度はドーンという凄まじい轟音。そうです。それは原子爆弾です。米軍は8月6日、人類史上最悪の兵器・原爆を、初めて広島に投下。さらにその3日後には長崎へ投下したのです。広島12万人・長崎74,000人という20万人近い命が一瞬にして奪われました。そのほとんどが一般市民。これで日本の敗戦は決定的なものとなりました。僕の母は、その悪魔のごとき歴史的瞬間を目撃した生き証人のひとりなのです。母の村は、長崎市から幾つかの山を隔てた僻地であったために、原爆の直接被害は避けられましたが、そこが被爆地の風下に位置していたために、原爆投下直後から真っ白な灰が村中を覆い、収穫を迎えた芋畑も一面真っ白になりました。太陽も、その灰のために真っ赤な火の玉のようになり、野良仕事に出ていた村人を震え上がらせたそうです。その灰は翌日まで降り続いたといいます。それが後にいわれる〈死の灰〉です。14歳のときにその灰を浴びた母は、49歳で乳癌を患いましたが、幸運にも完治し、喜寿を超えたいまでも健在です。
今回は、直接ラーメンとは関係のない話でしたが、この母の体験は、母の人生を語る上では、どうしても外せないエピソードとして書かせていただきました。
第百〇八話 グルメな久留米
2013年4月16日 火曜日 〈グルメ〉と〈久留米〉をモジるというのは、どこかのラーメン屋さんのキャッチにもあったような気がしますが、実際、久留米はグルメな町なのです。歴史のある国には必ず、その国独自の食文化が存在しているように、〈まち〉にも、その歴史と共に町独自の食文化があります。ご存知久留米を発祥とするとんこつラーメンは言わずもがな、我らの町の代表的食文化であります(筆者職業上手前味噌?)。そして、肉や内臓を中心とした焼き鳥も、この久留米独自の食文化のひとつです。また、そのカテゴリーに入れるとすれば、夜の〈屋台〉も然りですね。最近では、これらを総じて〈B級グルメ〉と呼ばれています。まさに久留米は、B級グルメの聖地なのであります。
しかし!我が久留米には、それらB級グルメのみを以てグルメな町と言わしめている訳ではありません。例えば、僕が初めてピザを食べたのが32年前、18歳のときでした。そのお店は、池町川のほとりにあった小さなイタリア料理店〈サーラ・カリーナ〉です。始めてのピザの味と、イタリアの片田舎の家をイメージさせる店の雰囲気、その感動は今も覚えています。本場イタリア帰りのシェフの店という、39年前の九州では初めての本格的なイタリアンの店でした。天神町に移転した現在でも、サーラ・カリーナは、歴史と共にその味に磨きをかけながらイタリアの食文化を発信し続けています。
そして、そのサーラ・カリーナの正面に通りを挟んで位置する串揚げ専門店の〈五味一路(ごみひろ)〉。ここも独特の店の雰囲気と上級の串揚げの味を守り続ける老舗です。 話はちょっと逸れて、これは友人から聞いた話ですが、西鉄電車の車中、中年女性たちの会話、「久留米のおいしか物っちゃ何ね?」「そりゃアンタ、タイホーとタイホーたい」「え?」「大砲のラーメンと大鳳のとんかつたい」という会話が聞こえたとか(筆者職業上極メテ手前味噌?)。そう、そのとんかつの大鳳さんも、これまた大砲ラーメンと同じく創業昭和28年という、とんかつ専門店の老舗です。肉汁ほとばしる分厚い肉にサクッとした衣の絶妙なバランスはまさにとんかつの王道。その味は二代目の大橋一夫さんによって、頑なに守られています。
それからインド料理。これもイタリア料理同様、日本人の味覚によく合う料理文化ですね。当然カレー屋さんのことではでありません。久留米にも何軒かのインド料理の店がありますが、僕のイチオシは〈タンドゥーリ〉という、本物のインド人のオーナーシェフの店です。なぜか僕は、ここで焼酎を飲みながらタンドリーチキンを食べるのが大好きなのです。
その他にも、久留米には沢山のグルメな店があるのですが、紙面の都合上、またの機会とします。
そういえば、来たる11月の1日・2日は、日本中のB級グルメを集めた〈B1グランプリ〉が久留米で開催されます。久留米が一層グルメになる日です。今年の〈食欲の秋〉は、僕のメタボにさらに拍車がかかりそう・・・。
第百〇七話 カラダは正直
2013年4月16日 火曜日 今回のタイトル・・・「ふっふっふ、奥さん、イヤイヤ言うわりにはカラダは正直じゃぁねえか・・・」なんてイヤらしいハナシではありません。
実は先日、僕は検査入院をしました。入院中、何度も血圧や心電図をとります。特に血圧は30分置きに看護婦さんが交代で測りに来ます。最初は若くきれいな看護婦さんでした。その時の血圧は何と上が140の高血圧。無意識の動揺です。30分後、今度はやや年配で容姿は微妙な看護婦さんでした。血圧は120の正常値でした。僕は思いました。「カラダは正直だ」
もっと的確に心の状態が数値に出るのが心電図でした。タコの吸盤みたいなものを乳首の周りや脇腹などにペタペタくっつけると、モニターに波形が流れるアレです。これはオモローイ機械です。この機械は、少し体を動かすだけでモニターが反応して波形がいろんな形に変化します。僕は病室のベッドでひとり、腕を曲げたり、両足を上げてシンクロのマネをしたりして波形の乱れを楽しんでいました。そんなとき病室の入口に向かって大きく足を拡げると、僕の股間の向こうに看護婦さんがこっちを見ていました。とーっても波形が乱れました。〈ハズカシサ〉もちゃんと心臓の電流として数値に出るのです。・・・カラダは正直だ。
笑いながら看護婦さんは話しかけてきました。「香月さんは大砲ラーメンの社長さんだったんですね」波形がやや乱れました。看護婦さんは続けて言いました。「うちの息子もラーメン屋にしようかな。だってラーメン屋って儲かるんでしょう?うちの息子の将来の夢は〈金持ち〉らしいから」それを聞いた僕の心電図は激しく乱れました。「ちょっとまって看護婦さん。俺はね、カネモチになるためにラーメン屋を始めたワケじゃなかと!」僕は次第に興奮してきました。「大体、そげな露骨な金銭欲でラーメン屋初めても絶対うまくいかん!ソレは夢じゃなくタダの欲望ばい」その瞬間、心電図のモニターから大きなアラーム音が鳴り、計測不能になってしましました。・・・カラダは正直だ。
そういえば、学生時代にこんなことがありました。男ばかりの友人4人でドライブしていたときのこと、1人の友人がやにわにワイ談(エッチな話)を始めました。それは次第に盛り上がり、聞き手語り手が雑多に入れ替わって大いにテンションが高まってきました。しかし、その中で運転手のA君だけがしらけた顔をしています。彼はワイ談嫌いなのかホモなのか、その手の話には全く興味がないようで、ついにA君は皆に言いました。「いいかげんにしろ、そんなつまらんハナシ」・・・一同しらけた空気の中で、突然B君が、なにかを見つけて言いました。「おいA!ソレは何や?」
A君の股間には大きなテントが張ってありました。・・・カラダは正直だ。
と、いうことで、最後はやはり下ネタになってしまいました。今回のコラムはお子様の手の届かないところに置いて下さい。
第百〇六話 ラーメン王逝く
2013年4月16日 火曜日 去る7月13日、ラーメン王こと武内伸さんが逝去されました。享年47歳。肝硬変による早すぎる永眠でした。武内さんは平成四年のTVチャンピオンラーメン王選手権で優勝し、これを機に、それまで勤めていた建設会社から、新横浜ラーメン博物館広報担当へ転職。やがて独立し、ラーメン総合研究所を設立。その間ラーメンに関する著書を多数執筆(中にはマンガ本原作もあり、我が大砲ラーメンの物語もあります)、さらにテレビや雑誌のレギュラーも多く抱えており、ラーメンを『ブーム』から『文化』の水準にまで引き上げた功労者のひとりであります。武内さんのラーメンに関する知識と情熱は、ラーメンフリークのみならず、多くのラーメン店主からも一目置かれている、まさに本物の『ラーメン人間』でした。僕がその訃報に接したのは、武内さんと最も親密なラーメン店主・支那そばやの佐野実さんからの電話でした。「タケちゃん死んじゃったよ・・・」あの『ラーメンの鬼』といわれる佐野さんは声を詰まらせていました。その後も続けて何人もの関東のラーメン店主たちから僕のところへ訃報の連絡が入りました。『雷文』の女将・宇都宮さんは受話器の向こうで号泣していました。
武内さんはラーメン研究家という『食べる側』の人でありながら、ラーメン店主という『作る側』の人々から本当に愛された人でした。今でも僕は、武内さんとラーメン談義をやったり、飲み歩いたりしたことが昨日のことのように感じます。酔っぱらってイキナリ夜の歩道に柔道の『受け身』をやり、腕時計を壊した武内さん。テレビ取材で柳川に行ったとき、汲み取り便所に財布を落とし、汚れたお札を川で洗って干していた武内さん。別の取材では財布を完全に失い、佐野さんに「パパ?パパ?」と言いながら、お小遣いをねだっていた武内さん・・・。とても人間味溢れる人でした。そんな武内さんには多くの名言があります。その中で僕が最も印象に残った言葉が、「ラーメンは鶏ガラ・豚ガラ・人柄」。単なるシャレを超えた深みある名句です。
相模原の通夜会場の外には『ちゃぶ屋』の森住さんによってテントの仮設の厨房が作られ、森住さんと共に佐野さんや宇都宮さんたちが参列者に『ラーメンの炊き出し』を配り、武内さんの棺の中には、花ではなく『麺』が敷き詰められました。そして親族代表の挨拶でこのような言葉がありました。「伸は、人の十倍酒を飲んで、人の百倍ラーメンを食べて、逝きました」と。生涯で五千数百杯のラーメンを食べ尽くした武内さんの戒名は『麺伸』。まさに世界初の『ラーメン葬』でした。
お骨を拾いながら佐野さんが一言。「タケちゃん、喜んでるよな・・・」
ラーメン界にひとつ、大きな穴が空いてしまいました。
武内伸さんのご冥福をお祈りいたします。
第百〇五話 椎の花
2013年4月16日 火曜日 皆さんはお気づきでしたか?今年の春は、山々の椎(しい)の木(秋に細長いドングリの実をつける木)の花の当たり年だったということを。
今年は、見慣れた地元の山の山肌が、なぜか点々と淡い黄色に染められていました。佐賀の天山にヤマメ釣りに行ったときも、山の淡い黄色の景色は久留米や福岡と同じでした。不思議に思った僕は地元のお婆さんに聞いてみました。すると「あれは椎の花たい。私もここに何十年も住んどるばってん、椎の木がこげん花をつけたのは初めて見るばい」と。さらに「そう言やぁ、椎の花の当たり年は不吉なことがおきるっち、昔から言うね・・・」と。この話を聞いたのが五月。そして六月十四日、岩手・宮城内陸地震の発生・・・。東北の椎の花も当たり年だったのでしょうか、それにしても僕には、椎の花のいわれと今回の大地震との関係が、単なる偶然とは思えませんでした。
というのも、二年ほど前、家族で近くの神社にお詣りに行った際、いつも行く神社なのに、なぜかこの日に限って、雨も降ってないのに地面のあちこちからミミズが這い出しているのです。それを見た僕は、思わず子供たちに言いました。「今日は地震が来るかも知れんぞ。気をつけろ」子供たちは「何で?」「ミミズが土の中からこげん這い出とる。こいつらは微妙な地下の異変を感じて逃げ出しとるのかも知れん」僕はとっさに感じたことを言いました。そして皆で帰宅したその直後、本当に地震が発生。大した地震ではありませんでしたが、家族から僕はにわかに予言者扱いされたのを覚えています。
もうひとつ、昔から不吉な花と言われるのが「竹の花」です。竹は百二十年に一度開花(かつては六十年周期説が一般的だった)するそうですが、一度開花すると、その竹林は一斉に枯死してしまうそうです。竹の一本一本の寿命は十年ほどですが「竹林」として百二十年ちかく生き続け、開花と共にその竹林は寿命を終えるという不思議な植物です。その竹の花が咲いた年には不吉なことが起きるとされ、関東大震災の発生前にも、竹の花が咲いていたという話もあります。これもいわゆる「都市伝説」かも知れませんが、竹もミミズ同様、土中の地下茎で繁茂する生物です。何か人知の及ばぬ感覚を持っているのかも知れませんね。
しかしながら、岩手・宮城の被災地の惨状をテレビで見るにつけ、もうこれ以上の天災は起きないでほしい、ミミズが這い出さぬよう、椎の花や竹の花が咲き誇ることのなきよう、祈るばかりです。
岩手・宮城内陸地震の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
第百〇四話 ラーメン屋のブルース
2013年4月16日 火曜日 今回はテレビ「エンタの神様」の犬井ヒロシのノリで。
♪彼女とラーメン屋のブルース、彼女とラーメン屋のブルース聞いてくれ♪
♪好きな彼女と初めてのデートで、彼女イチオシのラーメン屋に行き、どのラーメンにしようかと迷ってると、イキナリ店員から「日本一のシューマイはいかがですか」と言われ、ラーメンに不安を抱かせるセールストークにとまどいながらも、彼女オススメのラーメンを注文し、初めて口にしたときの話やけど♪
「うっマズ、よう喰えへん」と思いながらも。彼女はおいしそうに食べてる。ここで「ウマいな」とウソ言いながら我慢して完食するのか、「俺の口には合わへん」と正直に言って、せっかくの初デートを一瞬で気まずくしてしまうのかは・・・自由だぁ!
♪完食 is freedom. 完食 is freedom.
~みんないっしょに~完食 is freedom.
ジャンジャンジャンジャンジャン E7・D#7・D7
・・・でも、彼女が「あれ?ラーメン屋さんを間違えちゃった」なんて言ったら、我慢して口に含んでたラーメン吹きだしてまうで。ジャンジャン・サンキュ~♪
パート2
♪ラーメン屋のオヤジのブルース。
ラーメン屋のオヤジのブルース聞いてくれ♪
♪リストラにあったオヤジが、あるラーメン屋に就職したら、
なんと三日目には客のラーメンを作らされてしまったときの話やけど。
「あの老夫婦、俺が作ったラーメンに箸も付けず、不思議な顔してラーメン見つめてる・・・何でやろ?」よく見ると「アカン!一杯のラーメンには麺を入れ忘れて、もう一杯はスープを入れ忘れてるやん!・・・。しかし待てよ、アレは夫婦やん、二人仲良う麺とスープを分け合って食べるやろ」と、自分の初歩的なミスの処理を、客にまかせて甘えきってしまうのか、「すんまへ~ん」と、正直に謝りながら麺とスープを持って行き、年期の入った職人の顔をしとるくせに、実は新人やということを露呈させるのかは・・・自由だぁ!
♪新人オヤジ is freedom. 新人オヤジ is freedom. ~みんないっしょに~新人オヤジ is freedom. ジャンジャンジャンジャンジャン E7・D#7・D7
・・・でも、その客がこの店の社長夫婦やったら、オヤジは首の皮一枚も残らへんで。ジャンジャン・サンキュ~♪
今回のネタはすべてフィクションでした。ジャンジャン♪