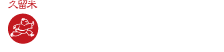山形県庄内町。山田洋次監督の時代劇「たそがれ清兵衛」の舞台にもなったこの町が「庄内藩」であったころ、藩主は武士たちに、武士のたしなみとして「釣り」を奨励していました。それは趣味としてではなく、剣の道に通ずる鍛錬という意味があったそうです。庄内の武士たちに釣りは深く浸透し、彼らは「刀同様、武士の魂である」と、釣り竿は自ら丹誠込めて手作りし、刀のように大切にしていたそうです。その武士の文化が、現在でも「庄内竿」とよばれる伝統工芸となって、この地方に息づいています。
実は僕の会社も、一〇年ほど前から社員に釣りを奨励しており、「懐麺隊」という名の社内の釣りクラブもあります。会社にはラーメン店のほかに懐石料理店もありますので、その二つを掛け合わせたクラブ名にしたのですが、そのカイメンタイという読みが、一部(特に婦女子)に大変不評で、クラブ活動中もその名を口にする者はいませんでした。現在は営業店の人手不足などの影響で、懐麺隊も長らく休止状態です。
話は戻りますが、剣と釣り、その極意の部分で相通ずるものは解るような気がします。相手が人であれ魚であれ、思いはすぐに相手に伝わるようです。ある剣道の達人から聞いたことですが、大試合であればあるほど「勝ち負け」に心がとらわれてしまい、その「心がとらわれた」瞬間に相手から打たれてしまうそうです。何事にも動じず、どんな大勝負でも「無の心」で戦える剣士が最強の剣士ということです。
釣りの世界にも同じようなことがあります。三年前の夏、僕は弟と二人で北海道にイトウ(幻の魚といわれる日本最大の淡水魚)を釣りに行ったことがあります。そこは日本最北の地を流れるサロベツ川支流。ここには、その前の年に初めて訪れていたのですが、そのときはイトウという幻の魚など恐れ多く、目的は「最北の地でサケ・マス属の魚を相手に竿を振りたい」それだけでした。要は、アメマスやオショロコマ、そして道産ヤマメでも釣れればよいのです。ところが、その川に入って最初に僕の竿にアタリがあり、直後、凄まじい引き。数分の格闘の末に釣りあげたのが、何と六〇センチほどの「イトウ」。紛れもない「幻の魚」でした。二人は驚愕。そして狂喜。興奮の中で魚をリリースしたのち、急きょ僕たちは「イトウねらい」に方針変更しました。しかし、二人の仕掛けは大物用ではありません。案の定、その後の最高のポイントで、今度は七〇センチオーバーのイトウに、目の前で僕のラインは切られてしまいました。
その一年後、二人はリベンジで再びその地へ訪れたのです。弟の意気込みはすごいものでした。仕掛けは「超大物仕掛け」。フロロカーボンの強力ラインに大型のスズキ針(海の仕掛け)。今年こそ自分も大イトウを釣りたいという強い思いで、目は血走ってます。それが僕にもヒヒシヒシと伝わってきたので、今回はいいポイントはなるべく弟に譲るようにました。ところが、どのポイントでも弟には何の魚信もなく、その後に糸を垂らした僕の方ばかりにアタリがあるのです。ひどいときには、弟の横で一服しながら放り出していた僕の竿にイトウが掛かったりしました。弟は僕と同じ釣り歴三〇年近いベテランです。技術の差もありませんし、ヤマメの大型記録では弟の方が上です。そう、読者の皆さんもすでにお解りのように、さすがイトウさん、人の殺気を川底深くから感じ取り、そのオーラを発するエサには見向きもしなかったのです。
僕の場合「無の心」というより、そのときばかりは、弟に釣らせたいという気持ちの方が強く、結果的に「殺気」が出てなかったのかもしれません。
ついにそのリベンジも、僕に釣れてしまった最大の(七五センチ)イトウでだけをキープし、弟としては未練を残しつつ最北の地を去るという結果になってしまいました(ちなみに、そのイトウは剥製になって、現在大砲ラーメン本店の壁におります)。
もしタイムスリップできるなら、いちど庄内の武士とイトウ釣りをしてみたいものです。
‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ
第九十四話 剣と釣り竿
2013年4月15日 月曜日第九十三話 「ラーメン」その名の歴史
2013年4月15日 月曜日 ときどき耳にすることがあります。「あそこのラーメンはラーメンじゃなかばい。あら“支那しな そば”ばい」すると別の人が「バカタレ、そこのラーメンは透明スープやけん、支那そばじゃなか“塩ラーメン”たい。“支那そば”ちゃ醤油ラーメンの一種で、支那そばやの佐野さんが作っとるアレたい」まあ、そんな会話ですが、
実は両方まちがいであります。~透明スープだから塩ラーメン云々~については、あながち間違いではありません(厳密にはもっと細かな説明が必要)が、“支那そば”という呼び名についての定義は違っています。
“ラーメン”という麺料理が、その名で呼ばれるようになったのは、先日お亡くなりになった日清の創業者・安藤百福氏が、世界で初めてインスタントラーメンを考案され、それが“チキンラーメン”という名で世に出た年の昭和三三(1958)年からなのです(いらんこつですが僕もその年生まれ。ラーメンとの因縁か?)。
それ以前は、東京のラーメンも九州のラーメンも皆“中華そば”と呼ばれていました。事実そのむかし、大砲ラーメンの初代である僕の父の屋台にも、暖簾
のれん
には龍の絵の横に“中華そば”と書かれていましたし、その頃の写真もあります。そしてその“中華そば”は、いつからそう呼ばれるようになったのかと言えば、戦後間もない昭和二四(1949)年頃と言われています。それまでが“支那そば”と呼ばれていました。その“支那”という言葉が使われ始めたのは、明治二七(1894)年の日清戦争の頃からといわれています。当時の中国は「清」の時代でしたが、英国からはすでにChina(チャイナ:秦が語源)と呼ばれており、それを聞いた日本人は“シナ”と発音し、“支那”という字をあてたとされています。やがて昭和二四(1949)年の中華人民共和国の成立をきっかけに、「シナ」を改め「チュウカ」と呼ぶようになったそうです。
そしてその“支那そば”以前にも呼び名がありました。それがラーメンの最初の呼び名といわれております。それは“南京そば”といいます。実は数年前、その呼称が記載された最古の資料が、北海道の函館で発見されました。それは“南京ソバ十五銭”と書かれた明治十七(1884)年の小さな新聞広告でした。これが函館・塩ラーメンの源流であり、そしてその広告主の“養和軒”という店が日本最古のラーメン店であるといわれています。
したがってラーメンの呼び名の歴史を時系列にならべれば
(1)“南京そば”明治十七(1884)年以降
(2)“支那そば”明治二七(1894)年以降
(3)“中華そば”昭和二四(1949)年以降
(4)“ラーメン”昭和三三(1958)年以降~現在に至る
となります。
さて、いかがでしたか?一口にラーメンといっても、その呼び名は時代と共に変遷の歴史を刻んできたのですね。ちなみに、ラーメンの四大源流とされる“醤油ラーメン”“味噌ラーメン”“塩ラーメン”“豚骨ラーメン”は、ラーメンの壮大な(?)歴史の中で、各地域に発生し根ざしていたラーメンを、近年になって研究者やマスコミが分類化し名称をつけたものであり、どこの地域でもラーメンはラーメン。中華そばは中華そばと呼ばれ続けていました。
ということで、今やラーメンは。RA-MENという単語で、外国の辞書にも記載されるまでになり、ついに世界に誇れる日本の国民食となった観があります。
はい、今回のコラムはとっても勉強になりましたね(入試には何の役にも立ちませんが)。一杯飲んでラーメンを食べるときの話のネタにでもして下さいませ。
第九十二話 第六感
2013年4月15日 月曜日 ちょっと前のNHKの朝の連続ドラマ「ちゅらさん」で、こんなコミカルなシーンが何度かありました。~孫のエリーから電話がかかる直前、それを事前に察知したオバアは、じっと電話機を見つめながら「鳴るよー」。その瞬間、電話が鳴り始める。家族が受話器を取ると、受話器の向こうからエリーの元気な声が聞こえる~ そんなシーンだったサー。ほとんどの皆さんは「ありえないけど楽しい場面」という感じで観ていたようですが、僕はそのシーンを観るたびに思いました。「あるある。自分も体験したサー」と。
昔から「第六感」という言葉があります。そう、人が通常持ち合わせている五感(視・聴・嗅・味・触の五つの感覚)を超えた感覚で、いわゆる「霊感」というものです。「ちゅらさん」のオバアは正にこの第六感の持ち主ということになりますが、残念ながら現代の科学では、そういう感覚の存在は認められていません。しかし、その科学では認められていないはずの感覚を、僕は若いころ何度も体験しました。
それは今から二〇数年前のこと。僕が二十歳過ぎたくらいでしたか、その日もバンドの練習から下宿に帰り、寝たのが深夜一頃でした。布団に入りウトウトし始めたとき、なぜか廊下の奥の公衆電話(下宿の共同電話)が、まぶたの裏に浮かびました。「鳴るぞ。それも俺あてに」そう思った瞬間、暗い廊下の片隅の電話が突然けたたましく鳴り始めました。僕は躊躇(ちゅうちょ)なく部屋を飛び出し、受話器を取ると・・・、受話器から男のうめき声が聞こえます。よく聞くと僕の名を呼んでいるようです。「か…香月?…オレ…」それはさきほどまで一緒にバンドの練習をしていたT先輩でした。そして「た…たすけてくれ」と。…とにかく僕は車に飛び乗り駆けつけると、Tさんが公衆電話の前で倒れてうめいています。すぐに僕は彼を抱きかかえて車の後部座席に放り込み、猛スピードで救急病院に担ぎ込みました。Tさんの診断結果は急性の結石ということで、命に別状はなくホッとしましたが、あとで思うに、Tさんは猛烈な痛みの中で誰かに助けを求めるときに、頭に浮かんだのは救急車ではなく、親しい僕の姿だったのでしょう。その強い思いが別の場所にいる僕に伝わり、電話が鳴る予感をさせたのだとしか思えません。
それから一年後のこと。今度は深夜というより明け方の時間帯でした。遅くまで飲んで先ほど寝たばかりの僕が、なぜかフッと目が覚め、またも感じたのです。「電話が鳴るぞ」さらに「俺の家族から」と思ったとたん、廊下の公衆電話が鳴りはじめました。やや朝日が差し込んだほの暗い廊下に駆け出し、受話器を取ると、相手は母親でした。「ヒトシちゃんね?ああよかった」いきなり僕が共同電話に出たので、母はびっくりしながらも、次の言葉が「ウチはガンになったばい。乳ガンげな」。晴天の霹靂(へきれき)でした。そして、この日を境に、僕のプロミュージシャンへの夢は終止符を打たれ、家業であるラーメン屋の道を進むことになるのです(その後母はガンの手術も成功し、お陰様で二〇数年後の現在も元気です)。それにしても、親子の思いも空間を超えて見事に伝わるものです。その後も「電話」に限らず、「人の思いの受信装置」みたいな、霊感のようなものの体験は続きました。しかし年を重ねるごとにその感覚は薄らいでゆき、いまはタダのラーメン屋のオヤジです。ただし「経営」という観点では、経営情報や経営技法以外の「経営の直感」という部分では、何となく、若い頃のその霊感らしきもののカケラが役に立っているのでは?…なんて思ったりするのは、ワタシダケ?
ということで、「ちゅらさん」のオバア的人間は存在するのです。
最後に余談ですが、秋の空のごとき「女ごころ」と、それにともなう「災難?」を事前に察知する霊感は、昔から、そして今も僕にはないようです。
第九十一話 雨の降る日に
2013年4月15日 月曜日 きょうは未明から雨が降っているようです。濡れた道を走る車の音で目が覚めました。午後になっても止む気配はなく、たまの休みも何をするでもなく、窓を開けると町並みが雨に白くかすんでいます。こんな日はテレビも消して、ただ外の雨音を聞いて過ごすことにします。
「ゆらぎ」というのでしょうか、不規則だけど心地よい雨だれの音に包まれていると、なぜか懐かしい気持ちになってしまい、心の底で色あせてしまった昔の記憶の端切れがフワリを舞い上がるときがあります。忘れていたはずの友の顔や風景が次々と現れては消え・・・。このコラムも、九九年四月に始まり早八年。もうすぐ一〇〇回を迎えようとしています。その間の懐かしい場面が、雨音と共に次々と去来します。
第一回ラーメンフェスタの群衆。陽気なラーメン店主。いかめしいラーメン店主。ワガママなラーメン店主。百面公園の北に横たう筑後川。TV愛の貧乏脱出大作戦の撮影。投げやりな修行者。怒る達人。矢部村・飯干小学校の校庭を裸足で走り回る子供たち。同校の廃校。校舎の解体工事。校舎の廃材で建てたラーメン店。そのラーメン店で行われたかつての先生の卒業式。先生の涙。徹夜で新作ラーメンを開発するスタッフ。国民文化祭のラーメンフェスタ会場に立ち並ぶ二十数店のラーメン店の壮観。トロフィーを受け取る一風堂の河原さん。酔っぱらった佐野さん。それを世話する大砲ラーメンの店長たち。フェスタ最終日の集合写真。スタッフの笑顔と泣き顔。ロサンジェルスのイベント出店。アミーゴしか言わない人の良いメキシコ人。喪に服すアメリカ中の半旗。独立する社員の希望と不安の顔。送別会の出し物で爆笑する社員。遅刻して頭を丸めた副長の照れ顔。結婚式ラッシュ。そして久留米初の全国封切り映画の撮影。二度に渡る撮影断念の危機と、その奇跡的回避。本番前の役者さんの顔。監督と方言指導のやりとり。新世界を走るリヤカー。夏祭りの行列。みぞれ降る冬の筑後川。一斗缶の焚き火。三日間徹夜でムクんだ助監督の顔。花束をもらったキャストの満面の笑み。クランクアップ直後の入院(ワタクシ)。娘の上京・・・と、無限の走馬燈のように現れます。その中に印象深い顔が二つあります。
それは僕が麺工房(製麺工場)を立ち上げた十年ほど前からお世話になりっぱなしで、去年の秋も台湾研修に同行していただいた製粉会社のMさん。そしてうちの元社員のF君です。彼は物静かながらも、ラーメンを作る姿がとても絵になる味のある青年でした。
映画~卒業写真~は、ある病院のホスピス病棟の六階フロアを借り切って撮影されました。後で知ったのですが、このお二人は、まさにその映画の撮影中同じ病棟で、Mさんは上の七階、F君は下の四階で亡くなっていたのです。しかも映画の主人公と同じような亡くなりかたで・・・。
たようで、ただ畏れ中に佇むだけでした。
でも、いま走馬燈に現れるお二人の顔は、とてもおだやかで優しい笑顔です。Mさんの後ろには幻想的な台湾の夜市の風景が見えます。F君の向こうには、立ち昇る麺釜の湯気と、おいしそうな顔したお客さんたちが見えます。
走馬燈はまだ廻り続けているようです。雨もまだ止みそうにありません。
第九十話 撮影現場の女神
2013年4月15日 月曜日 映画の撮影前、関係者は撮影中の安全を祈願して、お祓いやお参りをします。特に怪談ものやホラー系の映画には、それは欠かせないそうです。
さて映画「卒業写真」の舞台である久留米の撮影現場で起きた「不思議な現象」とは・・・、といっても、この映画は怪奇映画ではなく、こころ温まるヒューマンドラマであります。したがって現場で起きたのは「怪奇」現象ではなく、あくまで「不思議な」現象であります(ややこしい前フリでゴメンナサイ)。
それは先ず、筑後川・片の瀬対岸の河川敷で起きました。そこは主人公夫婦が故郷の自然を満喫しながら散策しているというシーンの撮影現場。夫婦の会話には、何気ないやり取りの中にも、物語上大切なキーワードが含まれているという大切なシーンです。そして二人の後ろには、すでに西に傾いた太陽の、その暖色系の光を浴びた雄大な筑後川の風景が必要でした。しかし!なんとその日は雨。しかも、みぞれに近い冷たい真冬の雨。それでもこのシーンはこの日に撮り終えないと、以降のスケジュールがすべて狂ってしまします。スタッフは寒風の中を黙々とセッティング作業をしています。大刀洗から来てくれた炊き出しのオバチャンたちも、寒さに震えながら熱い豚汁を作ってくれています。その間2時間。一向に雨の上がる気配はありません。皆、この日ほど太陽が恋しいと思ったことはありません。ついに主人公の奥さん役の羽田さんも到着しました。「おはようございまーす(午後でも現場ではこの挨拶)」元気な声と共にヒロインの登場です。そして羽田さんは、何気なく空を見上げました・・・。するとどうでしょう。何と、垂れ込めていた灰色の雲に穴がポカンと開いて、そこから待ち望んだ太陽の光がスーっと差し込んできたのです。そして雲のあちこちに穴が開き、まるで空は旭日旗(軍艦旗)状態。やがて雨も上がり、ついに太陽が現れました。何ということでしょう。羽田さんはまるで、天の岩戸からお出ましになった女神・天照大明神(あまてらすおおみかみ)でした。
実は羽田さんのこの神通力は、その後の草野町のロケのときも幾度となく発揮されました。不思議なことです。考えてみれば羽田さんに限らず、この映画自体、完成と配給決定に至るまでに様々な障害が立ちはだかり、何度も制作断念の危機に見舞われました。その都度、奇跡的に“神風”が吹き、窮地を救われたのも事実です。まさに“天に守られた映画”という気がしてなりません。それは、この映画を愛するすべての関係者の強い想いが天に通じたということでしょうか。
現在この映画は、今月二一日の(久留米T・ジョイ)公開に向けて最後の編集作業に入っているようです。僕もその現場でラッシュを見てみたい気もしますが、僕の網膜には、撮影現場で一生懸命に働くスタッフやキャストの姿が焼き付いています。公開の日まで、その網膜の美しい残像を楽しむことにします。
第八十九話 クランクアップ
2013年4月15日 月曜日 久留米発の映画“卒業写真”の冬編の撮影も、去る一月二十三日、ラストシーンからクランクイン(撮影の都合上ストーリーの流れとは関係なしに、各シーンはバラバラに撮影)しましたが、翌二月一八日、病室のシーンを最後についにクランクアップし、昨年の夏より始まった撮影もついに完了したのです。
全国公開は予定より早くなり今年の六月。そして久留米の皆さまには特別に、四月二一日よりT・ジョイ久留米にて全国にさきがけての先行上映が始まります。ただいま映画卒業写真を支援する会事務局で取り扱っております“制作協力券”がそのまま観賞券となります。その観賞券、今ならナント千円!事務局へのお問い合わせは〇九四二・三二・七六二〇まで。さあ今スグ!♪ゼロキュウヨンニィーサンニィノーナナロクニィゼロォー♪
いやー、それにしても映画のロケ現場は、テレビのそれとは全く違う空気がありました。まず映画のスタッフの数が(キャストも合わせると)五〇人近い大所帯ということ。それを地元のテレビ・ラジオ・新聞の取材スタッフが取り巻いています。さらに地元のギャラリー。あの草野町の静かな路地がそれらの人で溢れているのです。そして緊迫感。主人公夫婦が田園風景の中を散策するという、わずか十数秒のワンシーンのために、カメラの移動用レールを組み、マイク・照明やぐらの配置決をめ、美術さん背景に花を植え込み、一般車両の通行を一時的に止める係、近所の犬が吠えないように犬をなだめる係り、エキストラの動線を指示する助監督、出演者のメイク、それらのスタッフが整然と動き、手際よく全てのセッティングを完了させます。そこで初めて役者さんが入るのですが、それからも数回の芝居テストを繰り返します。そしてやっと本番となるわけです・・・が、その時はるか上空に飛行機が飛んでいると、録音班から「待ち」の指示が出ます。その間、役者さんもスタッフも全員がじっと息を潜めて飛行機が飛び去るのを待ちます。そしてついに監督の声がその静寂を打ち破ります。「本番!」すかさず助監督や各部署の担当者が「本番!」を連呼します。数秒のタメののち監督が「よォーい!・・・スタート!」。静かに役者さんの演技が始まりました。その動きに合わせて35ミリのパナビジョンカメラがレールの上を滑るようについていきます。緊張と静寂の中、聞こえるのは役者さんのセリフと鳥のさえずりだけ・・・。「カーット!」監督のこの一声で、役者さんは芝居を止めます。まず役者さんの演技の具合、そして周りのエキストラの動きやその他の不具合がなければ、「ゲートチェック」の指示の下、素早く撮影助手がカメラのゲート(レンズとフィルムの間の枠)にホコリなどの異物の付着がないか確認します(異物がこの部分に付着していると、それがフィルムに写り込み、このカットは台無しになる)。「ゲートチェック、オーケー」撮影助手のこの声を確認して、初めて、監督は「オーケー」を宣言し、わずか十数秒のこのシーン・このカットの撮影が完了するのです。
映画の撮影現場は、朝から深夜まで何日も、延々とこの作業の繰り返しなのです。クランクアップまでの最後の一週間は、ほとんどのスタッフが徹夜状態でした。僕たちがいつも、居間で寝っ転がって何気なく見ている映画も、こうやって作られていたのです。
プロの世界というのは、業種は違っても何か共通するものがありますね。そこでとって付けたようにラーメンの話はしませんが、芸術家も技術者も料理人も一流になればなるほど、モノ(作品)づくりに対する情熱に凄まじさを感じます。そこにはナントカと紙一重みたいなものさえ感じる瞬間があります。
またこれだけの人たちのエネルギーが結集する映画の撮影現場ですから、ときおり不思議な現象も起きるようです。ムフフ…何となく面白そうでしょう?聞きたいでしょう? それは次回のお楽しみ。
第八十八話 映画の方言指導(2)
2013年4月15日 月曜日 前回の久留米弁講座のハナシ、読者の皆さまには結構ウケたみたいです。特に「卒業写真」の久留米弁バージョンがご好評をいただいたようで大変恐縮しております。中には「お前が双璧という、もうひとつの名曲“なごり雪”の久留米バージョンも聴きたか」という声もありました。それで、調子に乗りやすい僕なので、それにお応えして少々・・・。
~応用編その2:「なごり雪」の久留米弁バージョン~
汽車ば待っとるお前ん横で オイは時計ば~気になってしょんなか
季節外れん雪どん降りよる 久留米で見っ雪ゃ こいがしまいばい ち
じゅつなかこつば お前や言いよろ
なごり雪でちゃ 振らにゃイカンごたるふうで
にやがり過ぎた季節んあとで いま春ん来て お前や うつくしゅうなったばい
去年よっか ガバ え~らしか。
(二番省略して最後のサビ)
お前の おらんごつなっしもたホームに まーだ俺ャおる
落ちちゃ~解けしよる 雪どん見よる いま春ん来て お前や うつくしゅうなったばい
去年よっか ばさらヨカおなご
・・・と、またもやってしまいました。なごり雪の伊勢正三さんごめんなさい。この前一緒に飲んだよしみで許してください。・・・しかし久留米弁というものは、どう聞いても全ての「美」を破壊する凄まじさがあります。 実は本日(一月二三日)ついいに映画「卒業写真」の冬編がクランクインしました。僕もこれからクランクアップまで「方言指導」としてロケ現場で各役者さんに久留米弁の指導をさせていただくわけですが、本日も主人公の津田寛治さんに、いくつか久留米弁のアドバイスをさせていただきました。さすがにプロの役者さんですね。台詞を数回反すうするだけでその部分のイントネーションはクリアされます。しかし、僕はそんな津田さんに感心しながらも、どうしても気になっていたのが、常に津田さんに寄り添っている奥さん役のヒロイン・羽田美智子さんの美しさです。その美しさゆえに、僕の口からほとばしり出る方言指導用の強烈な久留米弁が、羽田さんの「美」を一瞬のうちに壊滅させそうな気がしてなりませんでした。
しかしご安心下され。映画では、夫役の津田さんは久留米出身という設定ですが、妻役の羽田さんは東京育ちの女性であり、二人は東京で出会い、先日まで東京で暮らしていたという設定になっております。したがって、決して羽田さんの口からは久留米弁は出ないのであります。「美」は守られるのであります。
でももし、この夫婦が二人共久留米人という設定なら、夫婦の会話に僕はこんな方言を指導しなければならなかったかもしれません(以下のシーンは映画「卒業写真」とは関係ありません)。
~余命半年と宣告された夫、人生最後の終止符は自分が生まれ育った地で迎えたいと、献身的な妻の介護を得ながら故郷・久留米に帰郷していた~(夫は車椅子・妻はそれを押しながら冬の草野の田園風景を散策している)
夫「(車椅子を)ちゃ~んと押さんか。田んぼにおっちゃゆっとこやったやんか」
妻「しぇからしか。アタシャちゃんと押しよろうが、あんまい言うと ほたくって帰るばい」
夫「おっ、言うたにゃ、よかじぇよかじぇ 帰ってみ~」
妻「あ~帰っちゃるたい。そん前にあそこまで押して行っちゃる」
~車椅子のまま田んぼの中央部に取り残される夫。振り向きもせず去ってゆく妻。夫あぜんとしている。
雪が降り始める。カメラ次第に引く。遠景。山の中腹あたりから積雪(主題歌:なごり雪 途中、夫の台詞挿入)~
夫「がば さむか」 完
第八十七話 映画の方言指導
2013年4月15日 月曜日 このコラムでも何度かその存在を匂わせていましたが、初めて久留米が舞台となった全国封切りの映画「Watch with Me~卒業写真~」。その映画の後半の撮影が今月の半ばよりクランクイン、いよいよ大詰めを迎えます。完成はこの三月。全国封切りは来年の春に予定されていますが、地元・久留米の皆さまには今年のゴールデンウイークあたりに全国に先駆けて特別先行上映会が予定されています。広島の尾道ではありませんが、久留米もついに「ラーメンと映画のまち」として、食文化と映像文化で全国にその名を轟かせる日も夢ではなくなりました。今回の映画はラーメンとは直接関係はありませんが、縁がありまして、僕はこの映画を支援する会の地元プロデューサ一の一員として、陰ながら支援させていただいています。そんな折り、先日この映画の監督である瀬木直貴氏からナント「方言指導」を任命されてしまいました。以来、僕の頭の中は久留米弁でイッパイイッパイ状態。そこで不躾ながら、この紙面をお借りして「久留米弁の基礎と応用」の講座モドキをさせて下さい(地元の諸先輩、チェックをお願いします)。
~久留米弁:基本の単語~
●とっても(がば)●見苦しい(げさっか)●必ず(しゃっち)●~らしい(げな)●~のようだ(ごたる)●じゅつなか(つらい)●本当(ほんなこつ)●かたづける(なおす)●ケチだ(こすか)●だらしない(ずんだれ)●しなければならない(しぇにゃん)●ねー(にゃー)●~しよう(しゅーい)●ひとまとめ(ぐるめ)●ころんだ(さでくった)●なぐる(でやす)●なぐる(くらす)●うちまかす(しまやかす)●冗談じゃない(ぞーたんのごつ)●ほんのわずか(ハナクソんしこ)●器が小さい(のみのきんたま)●仲間に入れて(まじぇて)●どお?こお?そう!(どげん?こげん?そげん!)●歌をワンフレーズ口ずさんだ後に必ずつける意味不明の一語(ち)
・・・と、まあ、この他にも久留米弁の単語は沢山ありますが、ハッキリ言ってこれは日本語の域を完全に超えています。映画のセリフの完全久留米弁化はムズカシイですね(邦画なのに字幕が必要になる)。
さて、次は応用編です。例題として、今回の映画の主題歌でもあるユーミンのあの名曲「卒業写真」を久留米弁で訳してみました。
~応用編:「卒業写真」の久留米弁バージョン~
悲しかこつんあっと しゃっち開く皮ん表紙
卒業写真んアン人は やさ~しか目ばしとらっしゃる
街で見かけたときやら な~んも言えんやった
卒業写真ん面影がっさい そんままやったとよ
人混みん流されっしもて 変わっしまうウチやけん
アンタに たまにゃ がられたか
話かけよるごと ゆら~ゆらしよる柳ん下ば
通っとった道やら今はっさい 電車から見っだけばい
あん頃ん生き方ば あんたは 忘れんごつせにゃんよ
アンタはっさい ウチんシェーシュンそのもん
人混みん流されっしもて 変わっしまうウチやけん
アンタは たまにゃ ウチば でやして
・・・オソロシカですね。あの名曲が久留米弁になるとザマナカです。ユーミンさんごめんなさい。
どうなることやら「方言指導」・・・。
第八十六話 ラーメン界にもTOB
2013年4月15日 月曜日 最近、新聞の経済面を騒がしていました即席めん業界のTOB(株式公開買い付け)騒動。業界シェア四位の大手即席めんメーカーM食品が、突然ある米系投資ファンドから敵対的TOBのターゲットにされ「あわやM食品の運命や如何に」という瀬戸際に、業界最大手のN食品が白馬に乗ってさっそうと登場。このN食品とM食品が“友好的な”資本提携を結び、一夜のうちに業界シェア50%近い世界最大の即席めん会社(グループ)誕生か。かくしてM食品にカミカゼが吹いて、日本が世界に誇る即席めん文化に対する白人の植民地支配(?)から危機一髪で免れた…という話。
最後のたとえは少々大げさですが、TOBといえばITなど急成長でハイテクな業界のハナシ(製紙業界にも同様の騒ぎがありましたが)とばかり思っていました。即席めんとはいえ”ラーメン”というくくりで見れば僕も同業者です。さらに、何を隠そう、そのM食品さんはウチのブランドでカップめんを出していただいており、また、久留米のラーメン町おこしを最初からずっと支えていただいている素晴らしい会社なのです。そこにもついにアメリカ産マネーゲームの台風が直撃したのです。僕にとっても”対岸の火事”ではありませんでした。
株取引それ事態は、法的に整備された正当な経済活動であり、世界中の資本主義国の発展には欠かせない経済システムです。今回のTOBの行為も、それが“友好的”であれ“敵対的”であれ、法的には問題はないそうです。しかし!ラーメン屋の親父として解せないものがあります!ドラえもんによく似たニックネームの元IT会社の社長や、ギョロ目の元ファンド会社の社長の“商人としての品格”のなさ。このお二人に限らず、この手の人種の価値観はすべてカネ。相手会社の、創業から現在に至るまでの努力の歴史や人の思いなどお構いなしに、いやがる相手に対し平気で敵対的な買収に走る…。そこには義を重んじる日本の“商道”などみじんも存在しません。カネのためなら人の悲しみも一切感じない、いやそれを感じる脳の中枢すら退化しているようです。悲しいことに最近そんなタイプの若い経営者が増えてきているようです。
しかし、どこからそんな人種が排出されているのでしょうか?前述のギョロ目の元ファンド会社の社長は、小学生のときに父親から百万円の小遣いを渡され「これを資金に株をやってみなさい」といわれ、実際それで儲けたという原体験があったとか。小学校でも、ゲーム感覚で株取引の授業をやっている学校があるとか。いずれにしても小学生に株のことなど教える必要はないと僕は思っています。それは、小学生の柔らかい脳にマネーゲームの博打的快楽という麻薬を接種することに外なりません。子供たちに商売のことを教えるならば、松下幸之助氏の伝記を読ませるだけで十分です。そこには商道をとおしての日本人の大切な”心”が詰まっています。
先日から国会を賑わしている教育基本法の改正案にも、そのあたりを考慮してほしいものです。マネーゲーム人種増殖の予防のためにも。
第八十五話 日本人の礼節
2013年4月15日 月曜日 剣道の世界に「打って反省、打たれて感謝」という言葉があるそうです。剣道の試合は瞬時に勝敗が決まります。そこで勝者はガッツポーズを取るわけでもなく、敗者は首をうなだれる訳でもなく、勝敗が決したとたん両者は向き合ったまま静かに竹刀を腰に収め、互いに頭を下げ静かに去ります。何と美しい所作でしょう、そこにあるのは「謙虚」と「感謝」のみ、そう、「打って反省、打たれて感謝」の心です。まさに「武士道」です。
剣道以外でも「~道」と呼ばれる日本独自の修行の世界には、どれもその淵源に武士道精神が流れています。「~道」では技術の習得以前に「礼節」をたたき込まれます。僕は礼節とは、単にカタチ上の礼儀と節度ということではなく「謙虚と感謝の心が感じられるふるまい」のことだと思っています。どんなに優れた技でも、礼節を欠いていれば、それは技として認められません。相撲の取り組みでも、勝った力士がガッツポーズをとれば、その瞬間「負け」になるそうです。勝った力士が、土俵からころがり落ちた相手力士に手を差し伸べて起こしてあげる姿をよく見ます。土俵は神聖な場所です。そんな「神域」で、勝った力士は決して(どこかの若いボクサーみたいに)「どんなもんじゃい」などとは言いません。そこにはやはり厳格な礼節があります。
「礼節」それは日本が世界に誇る精神文化です。ユネスコの世界遺産に「精神文化」というジャンルがあれば、当然登録されるべき美しい文化です。
ところが最近この文化さえも、やがてこの日本から消え去ってしまうのでは?という危機感があります。最近聞いたことですが、小学生の子供に「給食代を払っているから“いただきます”は言わなくていい」という親が増えているとか・・・。この耳を疑いました。「カネは払ったのだから、学校は当然それに見合う給食を子供に提供する“義務”があり、子供はそれを食べる“権利”がある。ただそれだけのこと。そこで子供に“いただきます”を強制する“権利”は誰にもないし、子供はそれに従う“義務”はない」そういうことなのでしょうが、まさに「権利と義務」だけの世界です。そこには礼節どころか、謙虚も感謝も、思いやりのカケラもありません。この先、そんな親が増えてくるのでしょうか?以前、「授業の始まりにも終わりにも、生徒に“起立・礼”をさせない小学校」の話を書きましたが、まさに同質の話です。「勉強を教える側・習う側」「給食を提供する側・食べる側」その両者の間にあるのは「権利と義務」という“物質”のみ。“心”は微量も存在しません。一体、誰が何の目的でそのような国にしてしまおうとしているのか、僕には理解できません。
でも、うちのラーメン屋に来てくれるお客さんは、“心”ある人ばかりです。もしかしたら、まだ間に合うかも・・・。