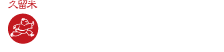十数年に及ぶラーメン屋台から、昭和四二年、ついにオヤジは小さいながらも念願の「店舗」を持つことができました(現在の本店)。僕は小学三年生、今でもその頃のことはハッキリ覚えています。
その店舗の立地というのは、町の中心部から外れた、古くて淋しい住宅地でした。屋台であれ”明治通り”という、まち一番の賑やかな商業地から一転、商売に極めて不向きな土地への移転ということは、当然オヤジは承知の上。それなりに覚悟していました。
それは、こんないきさつがあったからです。
屋台時代、我が家は六畳一間のオンボロ借家住まいでした。その家はとても古く、雨が降るたびに雨漏りとの戦い。狭い部屋のあちこちに空き缶を置いて、その隙間で食事したり寝たりするという家の中のアウトドア生活。梅雨の時期などは、雨漏りの湿気で畳が腐り、そこから白いキノコが何本か生えていました。僕は友だちを呼び寄せ、それを見せては「ほら~、ウソじゃなかろうが~。ホンナモンのキノコが、ちゃんと家の中に生えとろうが~」と、それを信じなかった上流家庭の子(現在A幼稚園のF園長)に自慢していました。
オヤジと母は、そんな僕があわれに見えたのか「均、待っとれ。そのうちキノコの生えないふつうの家を建てるけん」と心に誓ったそうです(ついに僕の実名登場)。
でも僕としては、雨の降る夜に聞こえる、空き缶に落ちる水滴のリズミカルな音色は、いい子守歌であり、白いキノコと共に好きな家でした。
そんなある日、東の空が白み始める明け方、突然けたたましいサイレンの音で僕たち家族は目を覚ましました。皆で外に飛び出すと、空が炎で真っ赤に染まっています。火事です。すぐ近くの家がメラメラと音を立てて燃え上がっています。近所の人たちも皆外に出て、心配そうに火の行方を見守っています。母はなぜか枕を抱きしめて立ちつくしています。僕は怖いながらも、慣れ親しんだキノコの家との別れを覚悟していましたが、やがて消防士や消防団の皆さんの懸命の消火活動のおかげで、何とか火は収まり、家とキノコは焼かれずにすみました。
ほっとしながら母を見ると、相変わらず枕を抱きしめたまま。オヤジは母を見て「火事場で枕ひとつ抱えて飛び出す慌て者のハナシはよう聞くばってん、お前はホンナコツそれを地で行っとるにゃ~、しかもそれは俺の枕ばい。げさっか~」と大声で笑い、近所の人たちもつられて笑っていました。皆から笑われた母は、何かを押し隠すようにただ苦笑いするだけでした。
実はその枕が、その後の僕たち一家の危機を救ってくれるのです。
‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ
第七十三話 初代熱風録・その5
2013年4月14日 日曜日第七十二話 続・初代熱風録
2013年4月14日 日曜日 オヤジは母との出会いをきっかけに一念発起し、テキ屋稼業からキッパリ足を洗い、夫婦でラーメン屋台を始めました。
初日の売上はわずか一八杯。当時のラーメンは六〇円でしたから、その日のラーメンの売上は千と八〇円。酒が何杯か出たとしても千二〇〇円か千三〇〇円といったところでしょう。テキ屋時代ならひと口上で稼ぐ額です。 それでもオヤジは覚悟の上。大砲の弾のように、一度飛び出したら再び過去に逃げ帰ることは一切しないという信念で、屋号を「大砲ラーメン」としたのです(このコラム七年目にして、ついに自分の店の実名登場)。翌日はその売上を手に汽車に乗り、熊本まで良質の豚骨と豚肉を仕入れに行く、そんな日が続きました。ある日、こんなことがあったそうです。
仕入れの帰り、オヤジはいつものように汽車の網棚に、仕入れた豚骨と豚肉を包んだ袋を置き、その下の席で腕を組んだまま居眠りしていたそうです。前々回のコラムにも書きましたが、オヤジの顔は黙っているときは金剛力士の吽形(うんぎょう)像、口を開けば阿形(あぎょう)像のような、どちらにしても恐ろしい顔をしていました。この時の居眠りの顔も間違いなく吽形像そのものだったことでしょう。しばらくすると何やら腕に冷たい物を感じて、吽形像は目を覚ましました。見ると自分の組んでいる腕が血で赤く染まっているのです。一瞬、いつものクセで「俺は今日、誰かデヤした(殴った)か?」と思ったそうですが、上の網棚を見ると、紙袋の中の凍った豚骨がいつの間にか溶けて、豚肉の血と共に袋の破れ目からしたたり落ちていたのです。「こらイカン」と思った瞬間、その顔は吽形像から阿形像の顔にシフトしました。オヤジがその顔のまま前の乗客を見ると、新聞を拡げたお爺さんがいて、その新聞の一面には大きな見出しで「バラバラ殺人事件」の記事が。オヤジの隣の若い女性は、前の新聞見出しと、上の網棚の血のしたたり落ちる不気味な袋、そして顔が吽形から阿形へとメタモルフォーゼするモノノケのようなオヤジを見た途端、「ギャッ」と叫ぶなり、真っ青な顔をして隣の車両へ逃げ去ってしまいました。 前のお爺さんは、さらに流出量を増した袋から落ちる豚の血を、悪魔のミサのように浴び続けながら一段と凄まじい形相になったオヤジと思わず目が合ってしまい、恐怖のあまり金縛り状態。新聞を持つ指だけが小刻みに震えています。やがてそのお爺さんも、新聞を拡げて座ったままの格好で、カニのように横に移動を始め、やがて遠くへ消えてしまいました。 気が付くと、テロリストのような金剛力士像の周囲には誰もいなくなっていたそうです。
さすがのオヤジも次の駅で緊急下車。袋の問題を何とか処理して帰宅し、その夜は何事もなかったかのように、吽形像の顔でラーメンを作っていたということでした。メデタシ、メデタシ。
オヤジには他にもこんなヘンな話がまだまだあります。ということで、くるめすたいるの筒井さん、ノッてきたので次号も続けてヨカですか?
第七十一話 初代熱風録(下)
2013年4月14日 日曜日 しかしオヤジは、ただの「優しさを秘めたランボー者」ではなかったようです。僕が知る限り、ケンカ以外にも色んな才能がありました。まず「絵」がうまい。正式に絵を学んだわけでもないないオヤジでしたが、画用紙と鉛筆一本持たせると、サラサラといとも簡単に風景画を描くのでした。それがまた素晴らしい絵でした。余談ですが僕が幼年期、屋台の歩道にチョークで絵を描くのが好きで、長じてグラフィックデザインをかじったりしたのも、オヤジの血だったのかも知れません。
絵心という感性は、そのまま料理の感性に通ずるものらしく、それがのちにオヤジは、久留米のラーメンの最大の特徴と言われる「呼び戻しスープ」を生み出すのです。さらにオヤジはその感性に加えて、ケンカで磨いたのでしょう、人の心理を瞬時に読みとる「読心術」を併せ持っていました。なんか、ここまで言うとスーパーマンみたいですが、要するに屋台の前職は「テキ屋の天才」でもあったのです。
話は少々さかのぼって、そのころのオヤジの口上をひとつ。
ー(ときは昭和二十年代後半。ある街角の人だかり。その真ん中にはオヤジが一人あぐらをかいて座っている。足元に拡げたゴザには何かを包んだ紙の小袋が無数に並べてある)「さぁサァ寄ってらっしゃい見てらっしゃい(フーテンの寅さんのノリ)。取りィ出したりますコノ袋、中身はこんな黒い粉。ところがコレはそんじょそこらの粉じゃーない。私のふるさと信州は春里村(ウソ。そんな村も存在しない)そこでとれた猿。そのとれたての猿のアタマを焼いて焦がして粉にした、万病のクスリであります(これも真っ赤なウソ。ただの木炭の粉)。名付けて”サルノクロヤキ”(そのまんま)コレがまた良く効くスグに効く。男は精力絶倫!不妊でお悩みのご婦人は、コレを飲んだト月トォ日後がサァお楽しみ、オギャァと産まれる玉の子黄金(くがね)の子。そんな奇跡の小袋ひとつ、今ならナント五十円!・・・ん?お兄ちゃん、高い??見上げたもんだよ屋根屋のフンドシ、そんじゃぁ四十円!サァ買った買った。(そこですかさずサクラのオヤジの妹が現れて)ひとつ下さーい。おっと、お姉ちゃん!好きな彼氏にプレゼント?ありがとね、はい四十円ー と、まあ、その絶妙なタイミングで登場したサクラに背中を押されたように、僕も私もと本物の買い手が群がり、あっという間に完売。途端、オヤジはそそくさと荷物をまとめて足早に退散。人々が「ダマされた!」と気づいたときは、オヤジはすでに遠い町で「見上げたもんだよ屋根屋のフンドシー」なんてやっている。
これは五十年も前の話なので、もう時効ということでお許し頂きたいのですが、当時はそんな商売が当たり前のように横行していた時代であり、まんまと乗せられた客も、まがい物の代金は「口上という芸の見物料」という感覚で楽しんでいたという、良き時代でもありました。こんな具合に、群衆の心理を掴みとる術に長けたオヤジでしたから、のちにテキ屋から足を洗い(?)ラーメン屋台を始めても、その才能は遺憾なく発揮されました。それはとても面白いオヤジ伝説として皆さまに紹介したいのですが、このシリーズも今号で最終章です。・・・でも「そうかい、そんなに続きを聞きたい?見上げたもんだよ屋根屋のフンドシ、そんじゃーこの話、次号に続けよう!」なんと無計画な執筆。
第七十話 初代熱風録(中)
2013年4月14日 日曜日 そんな「三度の飯より酒とケンカが好き」という父でしたから、たまの休みに飲みに出ても、毎回ケンカで殴った相手の返り血を浴びた姿で帰宅していたそうです。母は「あん人に新品の白シャツを着せても、帰ってきた時にゃ赤シャツになっとる」と、いつも嘆いていました。幼児の僕にはオヤジの顔が、絵本で見た金剛力士像とダブってしまい、オヤジが黙っているときの顔は吽形(うんぎょう)像に、怒って叫ぶときは阿形(あぎょう)像に見えて仕方がありませんでした。
ちょっと話はそれますが、オヤジの屋台は明治通りの佐賀銀行前にありました。その銀行の裏、明治道りに沿うように、古い街道の跡と言われる細い道があります。その道の傍らに、お地蔵さんが三つか四つ列んでいました(今では小さな石碑だけ)。そこは幕末の頃、数人の勤皇の志士が斬り殺された場所で、そのお地蔵さんは、志半ばで斃されたその志士たちを祀ったものでした。当時の僕にはそんな歴史的なことは解りませんでしたが、幼心に「このお地蔵さんは、オヤジにやられた人たちに違いない」と思っていました。
そんなランボー者のオヤジにも、ちょっとした優しい一面を見ることもありました。
それはある日のオヤジの屋台での出来事です。ガランとした屋台に一人の男の客がフラリと入って来ました。オヤジよりちょっと年下くらい。彼はあちこちのポケットをさぐりながら五円玉や一円玉をカウンターに並べ、ようやく数え終わると「オヤジさん、酒ば冷やで一杯くれんね」(昭和三十年当時は酒一杯六十円、ラーメンも同額)「はいよ」オヤジは七勺コップをカウンターにトンと置くと、一升瓶で並々と酒を注ぎました。コップの口から溢れんばかりに揺れる酒の表面張力を見る彼の嬉しそうな顔を見て、オヤジは「こいつ、相当の酒好き。俺の仲間ばい」なんて思ったそうです。
ところが真の酒好きなら、その貴重な表面張力を壊さぬよう「口」から行きます。しかしその彼は「手」を出してしまった。オヤジが「やばい」と思った瞬間、案の定表面張力は壊れ、さらにそのもったいなさに慌てたのか、コップそのものを倒してしまったのです。後日オヤジはその光景をいつも僕に語りました。「ありゃ、やっぱり酒好きばい。コップが倒れた瞬間、コップの口がカウンターに触れる直前に引き起こした。俺の伝説の左パンチ同様、そりゃ目にも止まらぬ早業やった」
ところが物理の世界は非情なもので、酒好きの神技を以てしてもコップの中に酒は存在していませんでした。いっときの沈黙。カウンターに広がる酒を見つめてうなだれる彼。屋台を開業したばかりのオヤジは一瞬考えました。「今日の客はこの兄ちゃんが始めて。こんな時間やから、この一杯が今日の売上かも知れん。ここで仏心を出したら今日は赤字(実際そんな時代でした)。ばってん、俺も男たい。同じ酒好き同志たい」オヤジはうなだれる彼の前の空コップに、ふたたび並々と酒を注ぎました。
「兄ちゃん、これが一杯目の酒」その時の、彼の至上の喜びの顔と、その一杯を飲み干したときの満足気な顔がオヤジの心にずっと残ったそうです。
しかしその彼が、オヤジの屋台に再び現れることはありませんでした。
第六十九話 初代熱風録(上)
2013年4月14日 日曜日 久留米や博多の方なら当然ご存知の「ラーメン屋台」。のれんをくぐるとすぐカウンターがあり、せまい長椅子に座れば、隣のお客さんとの肩が触れ合うような小さな空間。湯気の向こうには無愛想な店主と言うより「オヤジ」がいる ・・・大体こんな感じですね。
そこで皆さんにイメージしていただきたい。まずオヤジ側から見た屋台の店内を思い浮かべてください。皆さんの目の前にはスープの釜があります。そしてその湯気の向こうのカウンターには二人の男性客がいます。そのうちの一人の男性客がラーメンを食べ終わり、そろそろ「お勘定」という頃、突然もう片方の一人が、のれんの外に、座ったまま忽然と消えてしまいました。驚く間もなく、外から聞こえる鈍い音、うめき声、そして走り去る足音・・・。さて一体何が起きたのでしょう?
これは五〇年ほど前の実話です。当時僕の両親がやっていた屋台での出来事です。目撃者は僕の母で、人間消滅(?)の真相は次のとおりです。外の物音とうめき声を聞いた母があわてて外に出てみると、さっきまで横にいたはずのオヤジがそこにいて、拳を握り締めたまま仁王立ちしていたそうです。母は恐る恐るオヤジに尋ねました。「何があったとね?」オヤジ曰く、「お前は気づかんやったろうばってん、実は…」
~男性客が一人でラーメンを食べているとき、別の男が入ってきた。ふつう先客がいれば離れた席に座る。ところがその男は先客の横にくっつくように座った。最初は「つれ」と思ったが、先客の迷惑そうな顔を見たら、そうではないらしい。そのうちあとから来た男が先客の耳元で何かささやいた。すると先客の迷惑そうな顔が、みるみる恐怖の顔に変わった。そのときカウンターの下でキラッと光る物が見えた。「そいつはドスでカツアゲしよったったい」・・・ナイフでの恐喝である。
そこでオヤジは忍者のごとく裏からそっと出て表へ回り、のれんの割れ目からスッと手を差し入れ、男の襟をつかむと、思いっきりのれんの外へ引き倒した?ということで、母が見た「人間消滅」はこの瞬間で、直後に聞こえた鈍い音とうめき声は、路面に引き倒された男が、オヤジからお仕置きを受けている音風景だったのです(当然「走り去る足音」とはその男が逃げ去るときのもの)。
しかし今では想像もつかない荒っぽい話ですね。でも当時は、敗戦でまだまだ国民の心がすさんでいた時代です。そんな時代にまして夜の屋台を営むには、それなりの覚悟と腕っ節の強さが必要でした。 オヤジにはそれが見事に備わっていました。というかオヤジの場合腕っ節が強すぎて、明治通り中の屋台の用心棒的存在でした。あちこちの屋台でトラブルが発生する度に、オヤジに「出動要請」があり、本業より忙しい有様でした。
第六十八話 弁当の想い出
2013年4月14日 日曜日 20年程前のある時期、僕はサラリーマンでした。そこの僕の上司というのがA係長(歳は40過ぎ)という、結構変わった人で、能力はあるのに仕事にそれを発揮しない。背も高く一見ダンディなイケメンなのですが、いつも鼻毛を抜いては書類に並べてボーっとしています。頭の中は酒とギャンブルと女のことばかり。そんな上司と僕とが、ある日のこと。
A係長:「おい、かのかっちゃん(この人が勝手にけた僕のあだ名)。今日の昼は何食おうかにゃー」
僕:「まだ朝礼中ですよ」
A係長:「あそこのアレもうまそうやし、そこのコレも食いたかにゃー」
僕:「部長がこっち見てますよ」
A係長:「そうやアレば食いに行こう」
僕:「・・・・・」
A係長:「それでよか?」
僕:「僕は今日は弁当です」
A係長:「フン、愛妻弁当?新婚さんはよかにゃー」
ここまではまだよかったのですが、次のセリフが決定的でした
A係長:「そんな弁当やら、食ったフリして中身だけ捨てて帰れ」僕は強烈にムッとしました。
僕:「Aさんは奥さんが一生懸命作った弁当を、そんなことできますか?」
A係長:「俺はいつもそう。女房は空の弁当箱見て安心する。それが思いやりやろ?」
僕:「思いやり?それは奥さんをダマしてるだけじゃないですか!毎晩飲み屋の姉ちゃんとのバカ騒ぎで遅く帰って遅くまで寝ているAさんのために、奥さんは朝早く起きて弁当を一生懸命作っとるんでしょう!その弁当をよくゴミ箱に捨てれますね!捨てるとき奥さんの姿が目に浮かばんとですか!」
A係長:「若僧が何を言うか、お前はまだ人生がわかっとらん!」
僕:「Aさんは人の道がわかっとらん!!」
互いに興奮して怒鳴り合う二人は、ついに部長に呼び出されてしまいました。部長に叱られながらもA係長は、今夜の飲み相手のお姉ちゃんのことでも考えているのでしょう、カエルの面に水、ケロリ、ケロケロとしてます。僕は僕で、弁当にまつわるある想い出がよみがえっていました。
― 僕はその数年前、オヤジの反対を押し切って、なかば家出同然で上京しました。
その旅立ちの日、僕が挨拶してもオヤジは知らんぷりでラーメンを作っていました。母は忙しい店とオヤジの目を気にして、息子の見送りもできないようでした。僕は仕方なく出発しようとすると、慌てて母が駆け寄ってきて、わずかな小銭と弁当を僕に渡しました。淋しそうに見送る母の姿に後ろ髪を引かれながら、僕は東京行きの夜行列車に飛び乗りました。そして車窓を流れ去る故郷の風景を眺めながら、何気なくその弁当を開くと、それは間違いなく母の弁当でした。砂糖多めの甘い卵焼きとピーマンの油炒め。僕が中学・高校の六年間食べ続けた、その弁当です。朝から晩までラーメン屋の仕事と、家事・育児、そして酔っぱらいオヤジの世話。仕事に追われ、疲れたら台所の床で仮眠しながら働き続ける母…。そんな母の姿がこの弁当の中に浮かんでは消え…、僕は涙があふれて止まりませんでした。僕はその弁当に誓いました。「俺、頑張って仕事して、いつか楽にしてやるけんね」 ― そんな弁当の想い出です。
僕はその話はA係長にもしませんでしたが、何か伝わるものがあったらしく、その日A係長は奥さんの弁当をカエルの顔で食べていました(弁当持って来とるやないかい!)
やがて僕もオヤジになりましたが、今でも釣り場で食べる弁当はホカ弁よりも、やはり古女房の愛妻弁当が一番ありがたいと思っています。
第六十七話 心に残る一杯(下)
2013年4月14日 日曜日 「はい、お待ちどうさま」怪しいカウンターの下から現れたのは、紛れもない味噌ラーメンでした。厚手の白い丼に茶褐色のスープ。麺は黄色い極太の縮れ麺。トッピングは厚めのチャーシュー(枚数は忘れた)と炒めた玉ネギと太モヤシ。この環境と調理のシチュエーションで疑い深くなった僕は「いやいや、見てくれにダマされちゃイカンばい、喰わにゃーわからん」と、スープをすすってみました。「・・・」さらに麺を一口。当時こんなコトバはなかったけど・・・・
「マイウ~!」とにかく旨い。新妻も同感。
赤味噌ベースのスープは、やや焦げた赤味噌の香りと深いコク。噛みごたえのある極太麺のモチモチした食感と、とろけるように柔らかい豚バラチャーシューとの絶妙なバランス。
僕はかつて、味噌ラーメン、特にそのスープにはある種の嫌悪感を持っていました。
味噌汁のようで味噌汁でない、ラーメンのようでラーメンにあらず。そんなどっちつかずのスープにストレスを感じ、その度に注文したことを後悔したものです。インスタントの味噌ラーメンなどはその極みで、そこ10年程食べてもいませんでした。
しかし!この目の前の味噌ラーメンは、インスタントなんかとんでもない、本物の見事な味噌ラーメンです。僕のそれまでの味噌ラーメン観は、完全に覆されました。
読者の皆さまには予想通りの展開だったかも知れませんが、やはり北海道という土地はタダモノではありません。こんな場末のスナックのような店(ごめんなさい)で、こんなに旨い、プロ風に言えば「最高の商品力」を持ったラーメンが当たり前のように出てくるという驚き。さらにママがポツリポツリと語るには、このあたりでは一般家庭でも、お母さんが手作りのラーメンをこれまた当たり前のように作るそうで、寒い日は子供たちにとって最高のご馳走だとか。ママ自身も子供の頃からお母さんの作る味噌ラーメンで育ったそうです。 この町では「お袋の味」とは、味噌汁ではなく味噌ラーメンということです。当世流行の「ラーメンご当地」なんてどこかのラーメン通やメディアが仕掛けたような薄っぺらなものではなく、この地は正に気候風土と人の生活そのものが、ラーメンに適した土地なのです。
そんなママの話を聞きながら、僕たちはスープも残さず完食したことは言うまでもありません。
やがてその「斜里の名店」をあとにしながら僕は、昔小説か何かで読んだ「子供から年寄りまで「町の住人全員が泥棒」という話を思い出し、思わず想像してしまいました。「ひょっとしたらこの町は住人全員がラーメン屋なのかもしれない…恐ろしか」と。
それから19年の時が流れてしまい、僕も女房もその店の名をどうしても思い出せません。
その後そのママと店がどうなったのかも当然わかりません。
来年で結婚20年。この節目にもう一度、二人であの斜里の名店を訪れてみたいと思っています。
第六十六話 心に残る一杯(上)
2013年4月14日 日曜日 「ラーメン屋さんでもヨソのラーメン食べるんですか?」と、お客さんによく訊かれます。「はい、よく食べますよ」と答えると、意外な顔して「へ~そうなんだ」そして、その後に続くのが「今まで食べた中でどこのラーメンが一番おいしい(または好き)ですか?」という質問です。これにはいつも、こうお答えします。「味の好みは十人十色。お客さんと僕が同じ好みとは限らないので、お答えしてもインターネットのいい加減なランキングと同じでアテになりませんよ。でも“心に残るラーメン屋さん”ならお答えできます」と。
今回はそのお話。
それは一九年前、僕の新婚旅行は初めての北海道でした。と言っても、綿密なスケジュールに縛られ、食事まで決められているツアーではなく、レンタカーで自由に北海道を一周しようというものでした。テーマは「大自然の釣りと温泉そしてラーメンの気ままな旅」と、ほとんど僕の好みに合わせたワガママな新婚旅行です。
道中、渓相のいい川を見つけるたびに車を停めて釣り糸をたれる僕に、文句も言わず付き従う初々しい新妻(今では小言ばかりの古女房に化けた)とフラリと立ち寄ったのが「斜里」という名の小さな町でした。近くの川でオショロコマという北海道の渓流魚が面白いように釣れているうち、ふと気づいたら陽も高くなっていました。そろそろ昼飯でもと、町で食べ物屋を探したのですが、閑散とした通りにそれらしい店は一つもありません。町の人に尋ねると、ラーメン屋さんなら一軒あるとのこと。「おっ、あるぢゃあないか、それもラーメン屋!」
僕たちは空腹と戦いながら何とかその場所を見つけたのですが、しかしそこにはラーメン屋らしきものは見あたりません。あるのは古びた一軒のスナックだけ。僕は尋ねてみようと、とりあえずそのスナックのドアを恐る恐る開けてみました。のぞいてみると、誰もいない薄暗い店内には赤茶色のカウンターにペルシャの絨毯みたいな壁紙。棚には古びたキープボトルが並んで、どう見ても昭和三〇年代の場末のスナックです。「す…スミマセン」引き気味に声をかけると、カウンターの奥の暗がりの置物が動きました。「…はい…いらっしゃい」それは人間でした。いきなりオレンジ色の照明が点灯し、か細い声で現れた女性は、昭和三〇年なら若かったはずの“ママ”でした。僕が「あの~このあたりにラーメン屋さんがあるって聞いたんですけど…」と尋ねると、ママは「はい、味噌ラーメンね」と言いつつ、おもむろにラーメンを作り始めました。何とこのスナックは味噌ラーメン専門店だったのです。そしてママは何やらカウンターの下でゴソゴソとやっています。
ちょっと不安になりました。僕もプロのラーメン屋ですから、ラーメンを作るにはそれなりの設備と厨房スペースが必要なのは知っています。それをカウンター下のわずかなスペースで、こちらからはよく見えないのですが、あたかもオイルサーデンの缶詰でも温めるようにチマチマとラーメンらしきものを作っているのです。 僕は新妻と顔を合わせて目で言いました。「こりゃイカン。ありゃインスタントばい。しもた~(しまった)」と。
第六十五話 カリフォルニアにて
2013年4月14日 日曜日 ♪ Welcome to the Hotel Californiaーとイーグルスの“ホテル・カリフォルニア”を思わず口ずさんでしまいました。そう、ここは若いころ夢にまで見たアメリカの西海岸です。まぎれもないカリフォルニア州L.A.(ロサンジェルスの略。現地で「ロス」と言ったらイナカモン扱いされるので要注意)です。
それは去年(平成16年6月)の話。
L.A.郊外の静かな町トーランス、日系企業が多く集まるこの町の、あるスーパーの催事に僕たちは招かれました。それは一週間という短い期間ですが「自分たちのラーメンが太平洋を渡る」という一事だけでもその価値アリと判断(本音はアメリカに行ってみたい!)。僕も店長たちも、喜び勇んで行かせていただきました。
結果としては、お客さまは現地の日本人や日系人の方ばかりでしたが(中には青い目のお客さまもチラホラ)、やはりラーメンは「なつかしい祖国の味」なのでしょう、連日ラーメンフェスタのような行列でした。感謝。
太平洋の向こうでもラーメンにはパワーがありました。Thanks!
さて、何と言ってもここは花のカリフォルニア。6月下旬という日本では梅雨のうっとうしいこの時期でも、ここの風はさわやかでカラリとしています。ヤシの木の街路樹の上は西海岸独特の青い空。♪ Warm smell of colitasーと、コリタス草の甘い香りがほのかに漂ってきそうな気分です。
そんな悦に浸った僕を見てか、スーパーの会長さんが「せっかくだから」と、ドライブに連れ出してくれました。
砂漠へ向かうフリーウェイを飛ばす車。その窓越しに流れるアメリカの町並みを見ていた僕は、ちょっとしたことに気づきました。
それは、あちこちのビルや住宅に、やたらと星条旗が掲げてあるのです。それも半旗。会長さんに尋ねると、先日のレーガン大統領の国葬以来、アメリカ中が喪に服しているとのこと。続けて会長さん曰く「この国では、自国民は当然、外人であろうとアメリカに住む全ての人には、幼児期の最初に国旗・国歌を覚えさせ、祖国への忠誠を刷り込まれるんです。私の孫が通う日系人の幼稚園でもそうです。だからアメリカ人はどんな場所でも、国歌が流れると自然に直立不動ができる、それも虐げられてきた黒人でさえ。だからこそ有事の際にはアメリカ国民は一丸となれる」と。
これはアメリカに限らず、世界中の国が「自国への忠誠を教育の基本」としているのは事実です。戦後から国旗・国歌を否定する“自虐思想”が教育の基本となってしまった現在の日本は、世界でも例外中の例外です。
・・・しかし「祖国を離れて、あらためて祖国の姿を知る」とでもいいますか、 かつてはアメリカ以上に愛国者で溢れていたはずのわが祖国・日本のあわれな現状を、L.A.の青い空の下で考えてしまいました。
そしてまたもイーグルスの歌が聞こえてきそうでした
ー ようこそホテル・ニッポンへ ここは素敵なところ いい人ばかり
そこで僕は支配人に告げた「ワインを持ってきてくれないか」
すると彼は言った「そのようなスピリットは1945年以降 一切ございません」
ようこそホテル・ニッポンへ ここは素敵なところ いい人ばかり・・・ ー
(少々アレンジ)
第六十四話 ラーメンの大臣賞
2013年4月14日 日曜日 ラーメンフェスタでおなじみの久留米・ラーメンルネッサンス委員会が、先日(1月26日)何と「平成16年度 地域づくり総務大臣賞」を受賞いたしました。
これも関わっていただいた全ての皆さま、そして市民の皆さまのお陰です。
同委員会の一メンバーとして、心から御礼申し上げます。
思い起こせば98年、市内の某大手ゴム会社の経営危機により、久留米は一気に不況の嵐にさらされました。その最中、さらに国からは「緊急雇用対策地域」という、全国で五地域しかない、しかも関東以西では唯一という「不景気のまち」のレッテルが貼られてしまいました。
その頃、そんな故郷の衰退を憂う四人の男たちが居酒屋で一杯飲りながら「何とかせにゃイカンばい」と、ヨッパライ頭をひねっておりました。いま思えばそれがラーメンルネッサンス構想の始まりでした。
それから足掛け7年、そのヨッパライたちの構想が、昨年は国民文化祭という国家事業となり、そして今回、かつて不景気のレッテル「緊急雇用対策地域」を指定した同じ政府から同じまちが、今度は地域づくりの「大臣賞」をいただいたのです。
いま手元に、このコラムの第1回目(99年4月号)の原稿があります。その一節をご紹介します。
~終戦直後の久留米のまちで、ふるさと復興の原動力となってチカライッパイ働いたお父さんたちのお腹を満たしてくれたのが、屋台で食べる1杯40円の豚骨ラーメンでした。
時は流れ、現在の久留米のまちに当時の面影はありません。
あの頃の元気はどこへいったのでしょう。
そこで僕たちは考えました。
「もしかしたら”ラーメン”が再び久留米復興の原動力になってくれるかもしれない」と。~
このコラムの予言(?)が的中したかどうかは判りません。また、焼け跡の終戦時と平成の不況時代、「ラーメンが二度まちを救ってくれた」と、ラーメン屋の僕が思ってしまうのも傲慢なことかも知れません。
しかし少なくとも、ラーメンが「闇と中にポツンと灯るランプ」のような、小さいけれどホッとする気持ちを、このまちに与えてくれたのではと思っています。