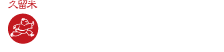先日ある新聞に、日本の子供の学力が低下しているとありました。特に正しい日本語の使い方を知らない若者が増えているとのこと。何か解る気がします。元々学力が低い僕が言うのもおかしい話ですが、サービス業、中でも飲食店の若いアルバイトさんの接客用語に乱れを感じます(恥ずかしながら、僕の店でも時々見受けられます。その都度指導しているのですが…スミマセン努力します)。
それはまず「過去形の乱用」とでも言いますか、席にご案内している最中なのに「こちらでよろしかったですか?」。商品を提供する時も「これでよろしかったですか?」現在進行中なのに全てが過去形。お解りのように、この場合は「~でよろしいですか」という使い方が正しい日本語の使い方ですね。
またこれも商品提供時、最近よく使われる言葉に「こちら~になります」というのがあります。正しくは「こちら~でございます」ですね。
その他にも様々な日本語の乱れを感じる時がありますが、この現象は最近の若者気質の現れでしょう。まず「過去形」現象は「面倒なことは聞きたくない」早くこの状況を「過去」にしたいという逃避願望です。また「~になります」というのは「~でございます」と、キッパリと言えない、または言いたくないという「責任逃れ」の心理です。
そして、若者の一般会話で「質問型」というのもあります。それはある焼鳥屋さんで、ある若者が僕に話しかけてきたときのこと。自分のことを相手に話すのに、語尾を上げて相手に質問するように話す。たとえば「俺?朝起きた?歯みがいた?痛かった?虫歯かも?病院?行きたくない?怖いから?それにお金も?無いから?」こんな調子で僕に「尋ねる」ように、しかも首をかしげながら、ただ朝の自分の「報告」をするのです。これには参りました。「お前、鏡とでも話ししろ」と言いたかったですね。
この「質問型」は、自分の行動の善し悪しを自分で判断できずに、他人に判断を委ねる「依存型」の心理ということでしょうか。若者気質と活字離れ(学力低下の一要因)が絡み合った独特の現象です。
さらにこの日本語の乱れと比例して増えてきているのが「正しくお箸を使えない若者」です。箸をX型に持ったり、人差し指だけ飛び出していたり…。最近の若者たちとの飲み会で、半数近くの子がそんな状況でした。
次の入社試験では「箸の持ち方の実技試験」を組み入れようかと真剣に考えています。ここがお箸の国なのかと情けなくなります。
最後に、この話に登場した、そうなってしまった若者たちに責任はありません。
親と周りの大人たちにすべての責任があります。
この国はどうなってしまったのか?
そして、どこへ向かおうとしているのか?
そんなことを、ラーメン屋の一親父が憂いております。
‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ
第六十三話 お~い日本語
2013年4月14日 日曜日第六十二話 ラーメンフェスタが国家プロジェクトに(下)
2013年4月14日 日曜日 去る十一月七日、史上最強・最大のラーメンフェスタが、大盛況のうちに無事終了しました。参加ラーメン店二十一店舗、ラーメン提供数三万二千杯、二日間の延べ来場者約十五万人という、今回はまさに世界最大級のラーメンの祭典でした。
まずはご来場の皆様、出店店舗の皆様、協力していただいた市民の皆様や企業の皆様、誠にありがとうございました。そして企画・運営に携わった全てのスタッフ、ボランティアの皆様、本当にお疲れさまでした。
しかし「祭りのあと」というのは、何ともいえない寂しさがあります。
フェスタ終了翌日の朝、招待ラーメン店の方々をホテルのロビーで見送った後、何気なくフェスタの会場跡が見たくなった僕は、ひとり百年公園に向かいました。
そこはまさに兵(つわもの)どもが夢の跡。
数万の人がラーメンを食べ、今は無人と化した巨大テント。調理機材はすべて撤去され、ただの箱に戻った店舗ブース、その裏の長大なバックヤードにも当然誰もいません。ほんの昨日までラーメン店の人たちが仕事の合間に食事をしたり、店舗間の交流の場でもあったところです。足もとには、無造作に積み上げられた行列プラカードがもの悲しく秋の風にゆれています。
さまざまな人たちの声や顔が浮かんでは消え、胸に迫るものを押さえながら僕は会場を後にしました。
来年のフェスタ?・・・もういいでしょう。
少なくとも僕個人はそんな気持ちです。
構想から七年。六回に及ぶこのフェスタの開催によって、久留米はとんこつラーメン発祥の地であり、全国に誇れるラーメンどころという事実は日本中の知るところとなりました。すでに「不景気のまち」というイメージはラーメンが払拭してくれたと思っています。
僕はラーメン町おこしを考えた当初から、フェスタそのものは打ち上げ花火のつもりでした。花火はいつまでも上げ続けるものではありません。まして最大級の花火を打ち上げたならば、それはフィナーレであるべきです。
ラーメン町おこしの次なるステップはラーメンの「モニュメント」づくりだと考えています。それは「とんこつラーメン発祥」の碑を設置したり、市内の中心部にエリアを設定し、少しづつラーメン店を誘致して、やがてラーメン横丁のような界隈を作り上げていく・・・そんな、地味だけどかたちとして残るものをつくっていけば、やがて毎日がラーメンフェスタ状態となり、各地から沢山の人が久留米の地を訪れるでしょう。
そんなまちづくりを、実は七年間思い続けていました。
「ラ・マンチャの男」かな?
第六十一話 ラーメンフェスタが国家プロジェクトに(上)
2013年4月14日 日曜日 今から6年前の1999年11月、最初の“ラーメンフェスタin久留米が”久留米百年公園にて開催されました。それを記念するかたちで連載を始めたこのコラムも、今回で六十五話目を迎えます。
第三話までは、「ラーメンフェスタ」という、市民には聞き慣れない新しい祭りの開催予告というのが主な内容でしたが、今あらためて読み返してみますと、何やら心に甦るものがあります。
当時、数人の有志が集まり“久留米・ラーメンルネッサンス委員会”という団体を立ち上げたものの、ラーメンフェスタという全国でも例のない事業を推進するにはあまりにもデータがなさすぎました。「千人なのか百人なのか」来場者の予測すらできない状況で、この前代未聞の祭りの成功をただひたすら祈りながら東奔西走する有志たちは、まさに幕末の志士でした。
そんな彼等の苦難と町を愛する想いは、やがて市民の心をとらえ、ついに“第一回ラーメンフェスタin久留米”は開催されました。
結果、この九州の片田舎のラーメン祭りは、驚くべきことに来場者十四万人という途方もない人を集め、凄まじい盛り上がりをみせながら「久留米」の名を全国に発信したのです。
このフェスタの成功は、その後全国のラーメンご当地への刺激剤となり、北は北海道函館から南は鹿児島串木野まで、そのノウハウは“久留米型”ラーメン祭りとして各地に伝播し、地域おこしの一助となっています。
実は、今年で六回目を迎えるこのフェスタ、今回は何と「国民文化祭」という国家事業として開催されることになりました。
国民文化祭(略して国文祭)とは「国体」の文化祭版というもので、都道府県持ち回りで開催される日本最大の文化の祭典です。
今年は福岡県が国文祭の開催県ということで、久留米のラーメンフェスタが、県を代表する食文化の祭事として認められ、国文祭の一事業という位置づけで開催されるのです。 国の事業、そして四七年に一度という機会に恵まれた今年のラーメンフェスタの概要は以下のとおりです。
名称(通称)は「国民文化祭・ラーメンフェスティバル」。
十一月六(土)七(日)久留米百年公園にて開催。
出店ラーメン店は、全国有名店(北海道から沖縄まで順に、すみれ・マメさん・味平・花の季・でびっと・ちゃぶ屋・ちばき屋・雷文・くじら軒・大文字・支那そばや・魁龍・一風堂・みその・通堂)のそうそうたる名店十五店と、地元店七店を加えた計二十二店という過去最大の店舗数。
また目玉として、四人の達人が分野の違うラーメン(たとえば支那ぞばやの佐野氏が豚骨ラーメンを作る)で競い合うという、フリークならずとも垂涎モノの企画もあります。
予想来場者は空前絶後の二十万人。とにかく「史上最大最強」のラーメンフェスタであります。
第六十話 日本の異常発生新種
2013年4月13日 土曜日 僕も若い人たちの結婚披露宴によく招かれますが、ここ最近思うところがあります。
それは“できちゃった結婚”が何と多いことか!この数年、招かれた結婚披露宴の新婦のほとんどは“妊婦”でした。
「今の若いモンは!」などと古来定番のオヤジセリフは使いたくありませんが、やっぱり「今の若いモンは結婚を何と心得とるか!」と、怒鳴りつけたい気分です。
結婚が決まれば、入籍前から当たり前のように子供をつくる。または、とりあえず妊娠したからと、とりあえず結婚する。
後者が一番なっとらんですな。それは若すぎるカップルに多いようです。
“とりあえず結婚”したカップルは、すぐに“とりあえず離婚”するようです。彼等にとって結婚はまさにゲーム感覚。残された子供はゲームのあわれな犠牲者です。その子供は、両親が力をあわせて子供(自分)を守る姿を見ることなく、共に老いてゆく夫婦の自然な姿も実感しないまま成長してしまいます。その子もやがて結婚の時期を迎えるでしょう。「子は親の轍を踏む」といいますが、そこに最大の不幸を感じます。このさき子から子へと因果の鎖が繋がれてしまうのかもしれません。
僕は両親がそろっていない家庭がすべてダメと言っているのではありません。何年も努力を重ねた結果、どうしようもない理由で離婚してしまう夫婦もいるでしょうし、事故や病気で親を失う子もいるでしょう。それはどうしようもないことです。僕が言いたいのは、“とりあえず”や“何となく”“しょうがなく”で、簡単に子供をつくって結婚し、すぐに離婚するバカップルが多すぎるということです。この新種の日本人は今や全国に異常発生しており、さらに増殖中であります。これがまた「俺はバツイチ」「私もバツイチ」と恥ずかしげもなくのたまい、寂しがりやの彼(彼女)らは夜の巷で次のゲームの相手をさがしまくるというタチの悪さ。
いま、そんなバカップルたちに声を大にして言いたい。「ナニは一切するなとまでは言わんが、女は気分次第で簡単にサセルな!男は放出だけが目的ならフーゾクに行け!また(男女共)ホレた相手には理性をもって接しろ!」と。
最近の日本の離婚率はアメリカ並みとききます。かつての日本人の理性や貞節はどこにいってしまったのでしょう。
それもコレも、戦後アメリカのサル真似をした日本の節操のない自由教育のツケというところでしょうか。
ある意味、バカップルも戦後教育の犠牲者かも知れません。
第五十九話 日本の絶滅危惧文化
2013年4月13日 土曜日 ~町からフラリとやって来た見ず知らずのラーメン屋のオヤジに、元気良く「こんにちわー」~そんな、山奥の小学校の素晴らしい子供たちがきっかけになって、やがてその小学校をテーマにした一軒のラーメン店が誕生したという物語は、幾度となくこのコラムに登場しました。その全校生徒わずか十三名の「矢部村立飯干小学校」は、もうその山村にはありません。この古き良き“日本の小学校”は四年前に廃校になってしまいました。
一方、これは現在、ある町のある小学校の話。
~六年生のクラスで一時間目が始まろうとしています。
教室に先生が入って来ました。「おはよう」先生は生徒に挨拶しました。ところがほとんどの生徒は知らんぷり。そのまま先生は教科書を開き、授業を始めました。そこには「チャイム」も鳴らなければ、生徒の「起立」「礼」の挨拶もありません。
いつのまにか始まった授業、生徒はワイワイガヤガヤ、好き勝手なことをしながら授業を“やり過ごして”います。
やがて一時間目が終わりました。やはり「起立」「礼」はありません。いつの間にか始まり、いつの間にか終わる授業。そこには何のけじめもなく礼節もありません。生徒の胸には決められているはずの「名札」もありません。教室の床を見ると、あちこちにゴミが落ちています。誰も拾おうともしません。掃除の時間じゃないから?掃除の当番ではないから?生徒は皆「無関心」。
勉強を教えてくれる先生にも、足下のゴミにも、イジメる子にも、イジメられる子にも、「無関心」~ これが町のある小学校の現状です。
「自由」と「無秩序」を履き違えた教育現場です。
学校側は「チャイム」も「起立」「礼」も「生徒に自主性を持たせるために廃止した」といいます。じゃ、なぜ(小学生よりは)自主性があるはずの中学や高校でそれが廃止されていないのか?
子供たちに「おはよう」の挨拶ひとつさせることが出来ない教育の現場が、何が「自主性」でしょう。
そんな教育を受けてしまった子がやがて社会に出て、会社の名札もつけない。上司にもお客様にも挨拶ができない。社内のゴミも拾えない。始業終業のけじめもない。仕事で悩んでいる同僚や部下が目の前にいても無関心。
こんな人間を雇う会社がどこにあるでしょう。
当然、そんな人間に育ってしまう原因は、その子たちの家庭環境にもあるでしょうし、それが大きなウエイトを占めているのは事実でしょう。だからこそ、そんな家庭があるからこそ、学校は親と地域三位一体となって子供たちを正しく導くべきではないでしょうか。
親兄弟・目上の人を敬い、目下の面倒をみる。人と会えば元気な挨拶。そんな素晴らしい日本の文化を、残念なことにいまの教育現場は、意識的に滅ぼそうとしているように思えてなりません。僕は軍国主義でもないし政治思想家でもありません。しかし、戦後教育は特に近年、日本文化の素晴らしさや日本人としての誇りよりも、日本人として生まれたことへの自虐精神を、子供たちに植え付けようとしているように感じます。
冒頭の矢部村の立飯干小学校には、元気で礼儀正しい小学生らしい小学生がいました。そんな子供たちを育てるこわくて優しい本物の先生がいました。
そして、そんな先生と生徒をいつも見守る村がありました。
第五十八話 アジアのラーメン(下)
2013年4月13日 土曜日 前々回より、アジアの食にこだわり続けた“アジアのラーメン”シリーズもついに最終回となりました。
いま、新・長門石店では“タイ風カレーつけ麺”なる新メニューを限定販売しています。「Tラーメン伝統の“呼び戻しスープ”が、タイの魚醤ナンプラーと南国のスパイスに出会った」というコンセプトの商品(作品?)です。そう、この店の“亜と和の融合”というテーマに沿ったラーメンです。
基本的にこのラーメンは、秋までの期間限定とする予定ですが、次の“作品”も、やはり「アジアの風を感じる」ものにしたいと考えています。しかしそれは“つけ麺”ではなく、温かいスープの“醤油ラーメン系”。
それは何故か?…実は、ラーメンバトル用の“勝負の一品”とするためです。対戦相手は、ガチンコの佐野さん・一風堂の河原さん・そしてタレントのデビット伊東さん。
知る人ぞ知るこの話、そのドリ-ムバトル(ラーメンフリークの間ではこう呼ばれている)企画の発端は去年の十一月、“ラーメンフェスタin久留米”の開催中、数千人の人が見つめるイベントステージ上でのことでした。
その三人と僕を含めた四人で“ラーメン談義”の真っ最中、イキナリ佐野さんが「久留米の豚骨ラーメンはクサイ。俺がクサくない豚骨ラーメンを作ってやろう」と切り出したのです。僕は ~失礼な!このニオイは久留米人には“いい香り”ばい~ と思いながらも、なぜか口では「そんなら僕は“クサイ醤油ラーメン”でも作ろう」と返してしまいました。すると佐野さん、「“醤油ラーメンでも”とは何だ“でも”とは!」さらに「ようし勝負だ!俺は負けねぇからな!」とイキまいてきました。それを聞いていた河原さん、「それは面白い!俺もまぜやい(仲間に入れろ)」やっぱり食いついてきました。しかも「俺は“塩ラーメン”で勝負させやい。そうや、デビ(デビット伊東さん:河原さんのラーメン弟子)、お前は“味噌ラーメン”で勝負しやい」と、全員を巻き込む始末。
僕は、ラーメン店主という立場でこのステージにいるものの、「はたして、この企画は実現できるのか?」などと、フェスタの運営側としての現実的なことを考えていました。するとデビット伊東さんが一言。「Kさん、何黙ってんの?九州男児はイモ引いちゃイカンですよ」これを聞いた僕は思わず、「わかったワカッタ!やってやるよ!」と、勝負を受けてしまいました。
かくして次回ラーメンフェスタの目玉企画が、数千の聴衆の前で、なしくずし的に決定してしまったのです。
河原さん・デビさん・僕という豚骨ラーメン専門の店主が、それぞれ塩ラーメン・味噌ラーメン・醤油ラーメンを作り、醤油ラーメンの達人の佐野さんが豚骨ラーメンを作る…。全員が異文化のラーメンで他流試合するという前代未聞のこの話は、フリークの口から口へと、瞬く間に全国に広がっていきました。
~果たし状~
「時は本年十一月六日と七日、第十九回国民文化祭ふくおか ラーメンフェスティバル・久留米百年公園特設会場に来られたし」
第五十七話 アジアのラーメン(中)
2013年4月13日 土曜日 先日(四月二十一日)リニューアルオープンした長門石店の謎・その一「なぜ今回のコンセプトは“木造校舎”ではないのか?」
それは、木造校舎をコンセプトにした合川店・小郡店誕生の裏には、まず廃校が決定した矢部村の飯干小学校の子供たちや村人たちとの出会いと、心のふれあいがありました。 その結果として廃校後の校舎を譲っていただくことになり、お陰様で二つのお店が誕生したという“物語”があります。 校舎の材木はまだ残っていますが、だからと言って「評判がよかったからそのシリーズでいつまでも店舗展開する」というのは、矢部村の人たちとの出会いの感動を商売に利用するような形になってしまいます。僕にはそんな商根はありません。
謎・その二「じゃ、なぜ“アジア”なのか?」
僕は以前から「日本のラーメン文化のルーツは中国だけではない。アジアの玄関・九州でラーメン屋を営む者として、もっとアジア、それも南方に目を向けてみたい」そんな思いがありました。
話が少し飛びますが、九州のとんこつラーメン屋さんが、たとえば“毛色の違う新メニュー”として、“清湯(ちんたん:澄んだ)スープの醤油ラーメンを開発する場合、その味の開発目標になるのは、ほとんどが関東首都圏の名店のラーメンです。かつては僕もそのひとりでした。四年前、期間限定で発売した“しょうゆ柳麺”も、やはり首都圏の醤油ラーメンの名店の味が開発目標になっていたのを憶えています。いわば全国の清湯系ラーメンが、首都圏レベル(?)を目指している状況といえるでしょう。
そんな風潮をみるにつけ、最近僕は「日本中の清湯系ラーメンが知らぬ間に皆“関東顔”になってしまうのでは?」と思い始めました。
僕は九州のラーメン屋です。“関東顔”にはなりたくありません。そこでアマノジャクの僕は、皆が目指す“東方”に背を向け、あえて“南方”を見つめてみたいと思いました。 そう、東南アジアです。たとえは悪いのですが、旧日本軍が豊かな南方資源をそこに求めたように、資源のみならず東南アジアには、豊かな食文化があります(もちろん素晴らしい麺文化も含めて)。タイ料理を代表するトムヤムクンなどは、フランスのブイヤベース、中国のフカヒレと並び“世界三大スープ”の一つとされていて、余談ながらコレがまた僕の好物でもあります。また、タイやベトナムで醤油といえば“魚醤”、ナンプラーやニョクマムのことで、これらの国のほとんどの料理に使われています。それは日本の秋田の“しょっつる”や石川の“いしる”と同じ、魚と塩で作る発酵調味料ですが、日本のそれよりニオイが強く、その分コクがあります。
そしてスパイス。東南アジアはスパイスの宝庫ですが、特にスパイスの聖地インドに隣接するビルマには、中国の麺文化とインドのスパイス文化が出会い、そして産まれた料理“カレーラーメン”(現地語では“オーノスカウェー”)が日常的なメニューとして存在しています。
その他、東南アジアの食文化を語るにはこの紙面ではキリがなく、また僕も勉強中なのでここでは割愛しますが、要は「そんな素晴らしい南方の“食の文化圏”に近い九州の地にいながら、東方(関東)ばかり目指すのは、何ともったいないことだ」と気づいたということです。それは、ラーメン屋がいきなり東南アジアのメニューを出すということではありませんし、ましてラーメンの奇をてらうことでもありません。
これからさらに進化していくであろうの日本のラーメン文化に、もっと広がりと深みがほしい。その一助となりたいだけのことであります。…謎の答えになったかいな?
第五十六話 アジアのラーメン(上)
2013年4月13日 土曜日 「アジアから九州へ、そして九州からアジアへ」
~とんこつラーメンの聖地で、その発祥地でもある九州は、一方“アジア食文化の玄関口”でもあります。中国大陸の麺文化をはじめ、東南アジア諸国の様々な食文化は、古くからこの九州へ上陸し、やがて日本中へと広がっていきました。その“外来の食文化”は長い時間の中で、日本人の手によって日本人好みの食へとアレンジされました。特に、いまや日本の国民食といわれるラーメンはその代表格といえるでしょう。そのような九州の地で、そのようなラーメンにたずさわる僕は、今、ラーメンという食そのものの原点とその本質を、アジア人の一人として見つめ直したいと考えています~
と、いうのは、実は先日(四月二一日)にリニューアルオープンした僕たちの長門石店のコンセプトです。何だかPRじみて恐縮ですが、引き続きその店の紹介を少々。
「アジアの中の日本。時空を越えた無国籍で不思議なラーメン空間」
~新・長門石店の商品構成は、当然定番のとんこつラーメンを中心としながらも、今後はこの店のオリジナルメニューとして、伝統の“呼び戻しスープ”をベースに“アジアの香り”のするエスニックなラーメンを定期的に開発し、提供させていただく予定です(五月中旬以降)。
また、日本古来の“薪で炊いたカマド飯”も、新・長門石店だけのものです。「亜」と「和」の融合がお楽しみいただけます。
それらのラーメンたちを取り巻く空間は、アジアから日本へ伝播した“麺の道”をイメージしました。店の外観も内装も、日本家屋と中国や東南アジアの家屋が連なる無国籍な“町”に見えるようにデザインしました。 その町角に高くそびえ立つ煙突からは、カマドの煙が立ちのぼる、そんな不思議な町です~
余談ですが、実はこのデザイン、以前子供と見たアニメ映画“千と千尋の神隠し”で、千尋の両親が豚になるシーンに登場する不思議な町や店の風景がヒントになったのです。
何だかホントに商売の宣伝になってしまいましたが(ゴメンナサイ)、今回なぜそんなコンセプトの店にしたのか?なぜ“木造校舎”シリーズじゃないのか?etc、そんなことを書きたかったのですが、紙面の都合でそれは次回ということでゴメンナサイ。
第五十五話 宮さまの替え玉(下)
2013年4月13日 土曜日 さすが皇族、一目でわかるその品の良さ。殿下は笑みを湛えながら僕らに軽く会釈をされ、側近の方々に囲まれながら店内に入られました。店の周りはSPの包囲網。なんと物々しいラーメン屋でしょう。
実はその直前、店内ではある“事件”が起きていました。それは「さあ殿下のご到着」という時のこと、突然厨房の奥から悲鳴が聞こえたのです。驚いたO店長が駆け寄ると、バックヤード(裏方)が、何やら薬品的な異臭に満ちていました。見るとそこには、ずぶ濡れになったアルバイトのM君とT君が呆然と突っ立っていたそうです。
O店長 :「どげんしたとか?」
M君 :(異臭の中、ずぶ濡れで)「何でもありません!」
O店長 :「うそつけ、その姿だけで何かあったのはバレバレやんか!」
状況はこうでした。
~T君が“酢”の補充のために、頭上の棚にある酢のコンテナの蛇口をひねろうとしたところ、何と蛇口そのものを引き抜いてしまい、大量の酢が吹き出した。手伝っていたM君も同時に全身酢まみれになってしまった。“ずぶ濡れ”と“異臭”の原因は“酢”であり、“悲鳴”は“蛇口が抜けた瞬間”の時のものと判明~
O店長は、殿下がお帰りになるまでバックヤードを閉鎖し、“酢自爆テロ”の二人はその“酢のガス室”に隔離することにしました。 そんな騒ぎを知る由もない殿下は、奥のカウンターにお座りになりました。同時にスーツ姿の九人の店長たちは速やかに店内の配置につきました。麺揚げ担当・スープ担当・盛り付け担当・提供担当etc、そして僕は“殿下担当”。
一杯のラーメンのための前代未聞のオールスターです。殿下のご所望は「昔ラーメン」でした。
店長たちは早速調理開始。提供をお待ちになる間、殿下は「とんこつラーメン発祥の地・久留米のラーメンを、私は楽しみにして参りました」などと、僕に気さくに話しかけられました。世が世ならば、御簾(みす:宮廷のすだれ)の向こうの方です。僕はそんな殿下のお人柄につい引き込まれてしまい、久留米ラーメンの色々な話をさせていただきました。
やがてラーメンをお出ししたら、一口いただかれて一言「…美味しいですね」。有り難いお言葉でした。そして殿下は先に麺だけ食べられると、何と替え玉を所望されたのです。驚いた僕は厨房の店長に伝えました。
「殿下は替え玉げなばい」
「えっ?あの方はニセモノですか?」
「バカタレ!その替え玉じゃなくて“替え麺”のことたい。ばってん麺だけやったら失礼やにゃー…。この際スープも入れてくれ。それも何か素ラーメンみたいで失礼やにゃー…。ええい、具も全部乗せてくれ!」
ということになり、思わず「“替え玉”という名の“一杯の昔ラーメン”」を作ってしまいました。殿下は「久留米の替え玉は変わっていますね」と思われたかどうか、それでも見事にスープも残さずお召し上がりになりました。 その後僕は殿下との記念写真を撮っていただき(皇族の食事中の撮影は不可。食事後専属のカメラマンによる撮影のみ可という決まりがある)、殿下のラーメンお食事は無事終了と相成りました。
ご満足気にお帰りになる殿下を店長全員整列でお見送りしながら、僕は「この方は本当にラーメンがお好きなのだな、そして何よりも庶民がお好きなのだ」と、殿下の後ろ姿に深く感じたのを憶えています。
その高円宮憲仁親王殿下は、このひと月後の平成十四年十一月二十一日、四十七歳の若さで急逝されました。
僕の中では、高円宮殿下は平成の黄門さまです。本店には、あの日の殿下との記念写真を飾らせていただいています。
庶民が作り、庶民が食べるラーメンを、平成の黄門さまは今も優しく見守ってくれています。
殿下のご冥福を心からお祈りして、このシリーズを終わらせていただきます。
第五十四話 宮さまの替え玉(中)
2013年4月13日 土曜日 高円宮殿下のご所望とはいえ、何の設備のない宴席に今すぐラーメンの出張料理というのは不可能です。畏れ多いことですが、僕は側近の方に丁重にお断りしました。
すると、あろうことか殿下は
「それでは私がお店に参りましょう」
と宣(のたま)われたのです。瞬間、店長全員に戦慄が走りました。皇族がラーメン屋に赴くなどとは前代未聞です。店長たちは
「皇族の人が、ラーメンやら食べてよかと?ましてトンコツばい。”呼び戻しスープ”ばい。しかもクサイばい」
「お腹壊されたら俺たちゃ百タタキかいな」
「バカたれ、ハリツケ獄門たい」
などと口々にワケのわからぬことを言っております。
今偶然にも店長会議の真っ最中。うちのラーメン職人のトップ九人が勢揃いしています。そのうえ全員がスーツにネクタイ姿。僕は「これも何かの縁」と感じ、意を決して「お待ち申し上げます」と側近の方に伝えました。
殿下ご希望の「本店」の閉店時間は(夜)九時、ご来店時間は十時です。僕は九時に一旦閉店した後、素早く店内外の清掃を終えさせ、「高円宮殿下お出迎えの儀」と称して店長全員と共に店舗玄関の外に整列し、直立不動でお待ちしました。でもあまり人相のよくない店長たちです。おまけにスキンヘッドの店長までいます。こんな連中が黙って並んでいると、まるでヤクザの親分を出迎える子分たちのようで、日頃静かな田舎の住宅街は騒然。
やがて十時きっかり、黒塗りの高級車が現れました。殿下と思いきや、車内から黒スーツの御仁がぞろぞろ現れ、その中のひとりがイキナリ僕の横のスキンヘッッドの店長に駆け寄り、
「何者か?」
と詰め寄ったのです。僕は慌てて
「この者はうちの店長です。決して賊でもテロリストでもありません」
と弁明し、彼を一番後ろの目立たない列に並ばせました。その後も続々と黒塗り高級車が現れ、小さなラーメン屋は表から裏まで黒スーツのSPたちに完全に包囲されてしまい、田舎の住宅街はさらに騒然となりました。
僕はつぶやきました「こらホンモノばい」。 そして最後の車が到着。店長たちは固唾を飲んでその車を見つめています。側近の方が後部ドアを開くと、とても品のいい紳士が現れました。高円宮憲仁親王殿下でした。