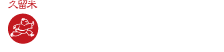久留米のまちと屋台を舞台にした本格ラーメンムービー「ラーメン侍」が、ついに今月22日に(久留米はTジョイ)公開されます。そこで読者の皆様にだけ、この映画の見どころを「こそ?っと教えちゃあたい」
見どころその1、渡辺大君扮する主人公・光(父・昇との二役)の麺上げシーン。これは一切「手タレ」を使わず、本人がやっています。実は大君、クランクイン前に横浜の大砲ラーメン・ラー博店で1ヶ月修行をしたのです。さすが大君、そのわずかな期間に麺上げの技術を見事に習得しました(僕よりうまいかも?)。
見どころその2、大御所・津川雅彦さん扮するヤクザの親分の家で、ヒロイン・嘉子役の山口紗弥加ちゃんが夫・昇の命乞いをするシーン。脚本では、ただただ泣き落としの命乞いをするということでしたが、本番直前、紗弥加ちゃんが「それだけでは面白くないので、途中から開き直っていいですか?セリフはアドリブでやります」と。監督の了解を得て、さあ本番、それは凄かった。「さあ殺せ!アタシゃあ死んだちゃよかとです。ホラ早よう鉄砲でここば撃ちんしゃい!ほら!・・・・」福岡出身の女優ならではの素晴らしいアドリブが延々と続きます。そこで津川さんが頃合いを見計らって大声で制します。「もうヨカヨカ!しぇからしか!もう帰って、その酒も昇にのませりゃあよか!」・・・これは名シーンです。
見どころその3、日本全国の有名ラーメン店主たちが随所に出演します。有名処では西の横綱と言うべき「一風堂」の河原成美さん、この人は一風ラーメン店主という役で、爆笑シーンを見事にこなしてくれました。一方、東の横綱は「支那そばや」の佐野実さん。役はデザイン事務所の部長で、セリフは「いい加減にしろ!お前ら!」この一言を大声で怒鳴るだけ。まさにハマり役でした。そのほかにも「ちばき屋」の千葉さんや「くじら軒」の田村さん、「なんつっ亭」の古屋クン、その他、総勢14名のラーメン店主さんに出演していただきました(感謝!)。映画ファンのみならず、ラーメンフリークにとっても垂涎の映画でもあるのです。
ほかにも数々の見どころや、撮影ウラ話など盛り沢山なのですが、それはまたの機会ということで。それでは読者の皆さん、10月22日、Tジョイ久留米に大集合、ヨロシク。
‘ラーメン今昔物語’ カテゴリーのアーカイブ
第百四十二話 映画「ラーメン侍」ついに公開
2013年6月11日 火曜日第百四十一話 奇跡のコラボラーメン2011
2013年4月18日 木曜日 先日、KBCの番組企画で、九州全県数万店のラーメン店を対象にしたランキングというものがありました。そのベストテン内に、何と久留米のラーメン店が3店ランクインしたのです。ランクインした店は、皆様お馴染みの龍の家・大砲・モヒカンです。これは当世流行りのツイッターによるランキング方式で、よくある「組織票」が介在しないリアルなものということでした。ところが、番組も無事オンエアされてこれで終わりと思いきや、番組制作の方から「久留米で3店のランクインというのは快挙で面白い。このネタを何かにつなげたい。ちなみにこの夏、久留米の百年公園でKBC主催の『水と緑の物語』と銘打ったイベントが開催されるので、ぜひその3店に出店してほしい」という打診がありました。
そこで3店の店主たちと番組のディレクターとで協議した結果、「3店のラーメンのそれぞれの持ち味を活かした至極の一杯。この日この場所でしか味わえない究極のとんこつラーメンを提供しよう」ということに決定しました。
思えば去年の8月、龍の家と大砲がコラボを組み「グリーンラーメン」という創作ラーメンを開発し、東京・銀座で開催されたラーメンコンテストにエントリー、おかげさまで最優秀賞を頂きました。それから丸1年、今年は新たにモヒカンが加わり、とんとつラーメンのメッカ久留米で最強のとんこつラーメンを創り上げます。
名付けて「奇跡のラーメンコラボ・三味一杯」
来る八月六日(土)朝八時~夕方六時
久留米百年公園へ来られたし。ご期待あれ。
第百四十話 息子からの電話(2)
2013年4月18日 木曜日 すると、前の方から黒い人影がこっちに向かって歩いて来ました。その人影はなんだかモヤモヤしていて輪郭がボヤけています。やがてその黒い影は息子の右を通り過ぎました。息子は嫌な予感がして振り返ってみると、そこには人影はなく、暗い夜道が続いているだけ。そして前を向くと、今度は黒い人影が2つ、こっちに近づいて来るのです。その2つの影は息子を挟んで左右を通り過ぎると消えました。さらに今度は白い影が目前に現れ、やはりすれ違いざまに消えたそうです。当然、息子はパニック状態。長崎の長い坂道を猛ダッシュで駆け上り、自分のアパートに飛び込んだようです。息子曰く、先日からの怪我や病気は、公園の横で見たその影たちと何か関係があるのかも、ということで僕に相談の電話をかけてきたのでした。そこで僕は四国にいる知り合いの霊能者に相談しました。早速、霊能者は霊視をしてくれて、翌日には直接息子に電話をかけてくれました。その霊能者が言うには、そのモヤモヤした影は、やはり霊で、原爆で亡くなった人たちの地縛霊であると。しかしその霊たちは人に憑依はせず、ずっとその地にとどまっているということ(息子に聞くと、やはりその公園は爆心地に近かった)。そして、先日の両足の怪我に続き、風邪までこじらせたという現象は、何と、今回の映画「ラーメン侍」に関係があったのです。読者の皆様ならご存じのこの映画、6年前のこのコラム(「初代熱風録」シリーズ)をネタに、若い頃の僕の父をモデルにした映画です。そして、今までやり続けた「まちおこし」の集大成という思いも込めて、僕の家族も会社も一心不乱に映画の完成を目指しました。実はそんな僕たちの姿をみて、36年前に亡くなった僕の父方の祖父の霊が、「息子の昇ばっかり」と、少々ヤキモチを焼いたみたいなのです。そういえば、映画のクランクインの際、水天宮で撮影の安全と映画のヒットを願って、キャスト・スタッフ一同で祈願しましたが、僕個人は、先祖へのお参りも何もやってなかったのです。そして祖父の霊は、魂のパワーが強過ぎる(らしい)僕にではなく、心根の優しい僕の息子にサインを送ったのだそうです。それを聞いた僕は早速、祖父のみならず、すべての先祖に対し、今回のお詫びと、父から僕へ、そして息子へと命をつないでいただいた感謝の気持ちを祈りました。
世の中、不思議なこともありますね。
第百三十九話 息子からの電話(1)
2013年4月18日 木曜日 このタイトル、決して「オレオレ詐欺」の話ではありません。この春、僕の息子は晴れて大学生となり、長崎市内で1人暮らしを始めました。3月末の引っ越しのときには、手伝いを終えて久留米に帰る僕たちを、アパートの前で1人ポツンと見送る姿が、とても寂しそうでした。
それから2ヶ月、息子からの電話はリンとも鳴らず、たまに来るメールには「友だちもたくさんできました。この前は、音楽サークルをフラリとのぞいて、かるくギターを弾いたら、先輩たちから『君は天才!是非うちのサークルへ!』などといわれました。毎日が夢のように楽しいです」というような、とりあえず寂しかったのは、1人暮らし第1夜だけのようでした。息子は、とにかくあの地獄の受験戦争を乗り越えたあとの開放感を満喫しているのでしょう。僕としては、いまはあえて「学生の本分はどうの」とは言わずに、ハメだけは外さぬように見守っております。
ところが先日、息子から突然電話がありました。僕が何気なく電話に出ると、何やら深刻そうな声で話すのです。内容は、まず、いまのアパートのことが気になると。聞くと、引っ越してすぐ、アパートの中で右足のかかとを怪我した。それはさほどの怪我ではなかったけれど、その怪我が治ったと思ったら、今度は左足のかかとに、同じような怪我をした。さらにその怪我が治ったら、風邪をこじらせて1週間寝込んでしまった。その頃から、どうもこのアパートに何かあるのでは・・・、そう思い始めた。それでも毎日が楽しいものだから、夜に帰って寝るだけのアパートのことは、さほど気にはならなくなったようです。ところが先日、ついに生まれて初めての、強烈な心霊現象に遭遇したとのこと。それは深夜1時、友人のアパートから帰る途中、ある公園にさしかかったとき起きたそうです・・・。
第百三十八話 国難
2013年4月18日 木曜日 憤懣やるかたない。昨今の政治に対してそんな気持ちです。
東日本大震災という戦後最大の国難に対して、いまの政権でどう太刀打ちできるのでしょう?そもそも現政権のトップたちは、かつて国旗・国歌の制定に反対した人間たちです。要するに「日の丸」も「君が代」も「軍国的だ」として否定し、数千年に及ぶ日本の伝統や文化を消滅させようと必死になってきたグループなのです。そんな反日政権が如何にしてこの国の復興をなし得るのか、はなはだ疑問です。言うならば、いまの政治自体もまさに国難です。しかし、その政権を誕生させたのは我々国民です。戦後六十六年に亘って推し進められてきた反日教育の申し子である我々国民です。もういい加減私たちは目を覚ますべきです。 これからは、政治家に「志」があるかどうかを見抜かねばなりません。「志」とは人のため、国のためという滅私の心です。それに対して「野心」とは地位や利権などを貪ろうとする私的欲望です。いまの政治家たちを観て如何ですか?与党も野党も右派も左派も、その中に本物の「志」を持った政治家が何人いるでしょうか。
かつて幕末・維新の若い志士たちは皆、命を賭すほどの強い志を持った者たちばかりでした。坂本龍馬しかり、西郷隆盛しかり。そして新撰組も立場は志士の敵でありながら「勤王」という志は志士たちと、ある意味同じものでした。そんな彼らが、この国を、列強による植民地化から救い、明治の近代化、そして日本が世界の一等国へとなる道筋をつくったのです。
いまの日本の為政者に、幕末・維新の志士たちのような強い志を持つ者が、これまた何人いるでしょうか。お笑い芸人やスポーツ選手に政治家になるなとは言いません。しかしその人に高い志があるかどうかを見抜く力を、これから我々国民は持つべきでしょう。
この国難を乗り切るために。
第百三十七話 映画「ラーメン侍」
2013年4月18日 木曜日 このコラムが映画になります。実は4年前、このコラムの「初代熱風録」というシリーズ(バックナンバーtaiho.net)が、映画「卒業写真」の撮影で来久していた瀬木監督の目にとまり、「これは面白い。映画になる」という話が持ち上がりました。以来、4年の構想期間を経て、今年ついに実現する運びとなったのです。内容は昭和40年代、町中が元気に溢れていた時代、久留米の1軒のラーメン屋台の店主とその家族が織りなす人情喜劇というもので、主人公は僕の父がモデル(当然人名と屋号は架空)です。主演は渡辺謙さんの息子・渡辺大君、ヒロインは福岡出身の山口紗弥加ちゃん、脇を津川雅彦さんや淡路恵子さんという大御所たちで固めるという豪華キャストになっております。
クランクインは去る3月1日、クランクアップが同月21日という超タイトなスケジュールの中で、久留米およびその周辺でのオールロケという過酷な撮影でした。また、撮影半ばで起きた東日本大震災は、現場に深い衝撃を与えました。「こんなときに映画なんか撮ってもいいのか?」と、自問するなか、被災地・福島に住む監督の知人から「撮影頑張ってくださいという」メールに力づけられ、「こんな時期に撮影した映画だからこそ、観る人を元気にする映画にしたい」監督のそんな思いで撮影は粛々と進み、ついに撮影のクライマックスというべき、菜の花の咲く筑後川河川敷で主人公が自分の屋台を燃やすシーンをもって、無事クランクアップとなりました。
伊丹十三監督の「タンポポ」以来20数年ぶりの本格ラーメンムービーとされるこの映画、最大の特徴は、全国の本物の有名ラーメン店主たちが、随所にエキストラで登場するというところです。まさに映画界、ラーメン業界初の快挙といってもいいでしょう。公開は今年の10月下旬、九州全県の東映系(Tジョイその他)を皮切りに、全国、そして韓国、台湾での公開を予定しております。
12年前にラーメンによる町おこしとして久留米で開催した「ラーメンフェスタ」。これは全国で初めてのラーメンイベントでした。そして今年、その究極型ともいうべき「ラーメン映画」が久留米から全国へ、そしてアジアへと発信されます。・・・感無量です。
第百三十六話 初代熱風録エピソード4
2013年4月18日 木曜日 先生は、その女の叫び声は2階の僕の部屋から聞こえたと思いました。「ついにアイツら、タバコだけに飽き足らず、とんでもないことを始めやがった」そう思いながらも、よく聞くと、その叫び声は下のラーメン店から聞こえていたのです。先生はスワ事件かと、思わず店に駆け込みました。するとその声の主は何と僕の母で、ヨッパライに迫るように叫んでいるのです。その状況、後で母に聞いた話では、そのヨッパライは、酒をたらふく飲んだあとラーメンを食べて、さてお勘定というとき「おいコラ、幾らか?」母が愛想良く「○○円です」と言うと、ヨッパライ「そうか」と言いながら財布から1000円札を抜き出すと、母の鼻先にヒラヒラさせながら「そげんカネが欲しかなら、市の上(地名)のオレの家まで取りに来い」それを聞いた母は、さすがに堪忍袋の尾が切れて。「何でいま持っとるカネをアンタんがたまで、もらいに行かないかんとか!ラーメン屋をバカにするな!」するとその光景を見ていた僕のオヤジが、そっと後ろから母に近づき、ニヤニヤしながら耳元でささやきました。「デヤされろ。俺が先に手を出したら、今度こそ懲役やけん、お前が先にデヤされろ」それを聞いた母はヨッシャとばかりに「ホラ叩け!叩かんか!」と、ヨッパライに顔をすり寄せながら叫んでいたのでした。その叫び声を聞いて店に駆け込んだのは、先生だけではありません。2階でたむろしていた僕たちの耳にもその叫びが聞こえ、何事かと、くわえタバコで駆け下り、店に飛び込んだのでした。店内には叫ぶ母、ニヤニヤしながら出番を待つオヤジ、くわえタバコの中学生たち、生活指導の先生、これらが渾然一体となった異様な空間です。ヨッパライはさすがにひるみ、いたたまれなくなって逃げ帰ってしまいました。やがて皆、何事もなかったように、オヤジは厨房に戻り、母は洗い物を始め、僕たちは2階に戻り、先生は去りました。
そのとき先生は思ったことでしょう。「中学生を補導する…、そんな問題ではない。ここは治外法権の別世界なのだ」と。
第百三十五話 初代熱風録エピソード3
2013年4月18日 木曜日 五穀神社前の大砲ラーメン本店は、僕の両親が長い屋台時代を経て、昭和42年にようやく出した最初の店舗です。以来40数年に亘り、建て替えや改装を繰り返して現在に至っております。いまでこそ3階建てのビルになっておりますが、最初は木造モルタルの2階屋でした。現在の店前の狭い駐車場が当時の店舗で、その後ろにくっつくように建っていた2階屋が僕たち家族の住む家でした。その家には沢山の思い出があります。その家に住んだ時間よりも、そこを出てからの時間のほうが遙かに長いのですが、いまでも夢に出てくる家はその家だけです。やはり成長期に住んだ家というものは、思い出の中に深くすり込まれるのでしょう。今回そのころの思い出話をひとつ。
それは僕が受験を控えた中学3年生のころ。当時2階の僕の部屋は、お勉強がとってもキライなお友達の集会場でした。日が暮れるころになると、どこからともなく、ひとり、ふたりとそんなお友達が現れ、夜には6畳の部屋は、そんなお友達でいっぱいでした。同時に部屋は煙でいっぱい。僕が学校から帰ると、もうすでに何人か勝手に上がり込んでいてタバコをプカプカやっている(もう時効ということでご勘弁を)というようなことも日常的でした。両親は下の店で商売に一生懸命で、バカ息子のことなど構うヒマなどありません。したがって、自然にそんな場所にはそんな連中が集まるようになります。集会場というより不良の溜まり場、またはワルの巣窟状態の僕の部屋でした。そんなある日、どこから情報を得たのか、学校の進路指導のコワイ先生が僕の部屋に目を付け、物陰から僕の家を監視していました。いわゆるハリコミです。先生は僕の家に吸い込まれるように入っていく生徒の名を手帳に書き始めました(まるでテレビのドキュメントそのもの)。と、そのとき!僕の家から女のけたたましい叫び声が!
第百三十四話 初代熱風録エピソード2
2013年4月18日 木曜日今回からこのコラムの作者名をイニシャルから実名へと変えさせていただきます。というのも、もう皆さんには僕の正体はバレバレですし。また、前回の「小説風・初代熱風録」の紹介の中に ~舞台は昭和40年代のラーメン屋台。登場人物の「昇」は僕の父、「嘉子」は母、「光」は小学生の頃の僕と思って下さい~ というくだりがありましたが、ある読者の方から「両親は本名なのに、なぜ息子のお前だけ違うのか?」というご質問がありましたので、この場を借りてお答えいたします。実はン十年前、僕が生まれたとき、その名を「光(ひかる)」と母が提案したそうです。母曰く「香る月の光りばい。まるで映画俳優の芸名のごたろうが、よかち思わん?」親父も「そうやにゃ、そりゃよか名ばい」と納得し、そのときから親父も母も、そして周りの親戚たちも、僕を「光ちゃん、光ちゃん」と呼んでいたそうです。やがて出生届けの締め切り日も近づいたある日、親父は1人で出生届けに行き、帰ってきた親父に母は確認のために聞きました。「アンタちゃんと光っち書いてきたね?」親父「うんにゃ、均史っち書いてきた」母は唖然。「なんね、そのヒトシっちゃ!そりゃ映画俳優どころか、まるでお笑いの植木等やんね!」落胆する母を見ても、親父は何食わぬ顔。母はいまでも「光がよかった」と悔やんでいます。しかしなぜ親父はイキナリ「均史」にしたのでしょうか、その親父が他界した今となっては知る由もありません。僕自身もやはり「光」がよかったと、最近特にそう思います。だって「100円ショップ」に行けば、僕の名だらけです。叫びたくなります。「均一・均一」って、オレは百円かよ!
第百三十三話 初代熱風録エピソード1
2013年4月18日 木曜日 このコラムで過去、読者の皆様から最も好評をいただいたシリーズ「初代熱風録」。
実は、このシリーズのイメージを膨らませて、僕がひっそりと書き下ろした小説があります。その目的は、機会をみて皆様にはお知らせいたしますが、今回はその物語の一部を紹介いたします。
(舞台は昭和40年代のラーメン屋台。登場人物の「昇」は僕の父、「嘉子」は母、「光」は小学生の頃の僕と思って下さい)
~昇は嘉子に商売の提案をしていた。
「にゃ、思わんか?ショウガ抜きにしてくれだの、ネギ抜きにしてくれだの、ほんに客はしぇからしか。だけん、ショウガもネギもカウンターに置いといて、客に自分で入れさせるったい。そげんすりゃ好かん奴は入れんやろうし、何ちゅうても、俺たちの手間がはぶけろうが」
*(光)『お客さんより、自分の都合を優先するところが、父ちゃんの商道でした』 (中略)
その夜、雪を被った弾丸ラーメンから昇のどなり声が聞こえる。
昇はカウンターの客を指さしている。
「こらぁ!そこの学生!ネギば入れすぎネギば! コラコラお前、お前たい!ショウガの入れすぎ、スープが真っ赤やんか!」
客は皆、恐れおののいている。割り箸を割る手が震えている者もいる。
「タダやけんちゅうて、ガバガバ入れるな!バカタレどんが!」
昇の後ろには、光の古い黒板が掛けてあり、そこには〈ネギ・ショウガはご自由にどうぞ〉と書かれている。
昇のどなり声が雪の夜空に吸い込まれてゆく。
*(光)『父ちゃんの辞書には〈おもてなしの心〉という言葉はありませんでした。そして翌日父ちゃんは、カウンターのネギとショウガを引っ込めてしまいました。』。~
いかがでしたか?このシーン、実は実話(笑)なのです。こんな親父の話が映画などになれば面白いと思いませんか?・・・・ムフフ。