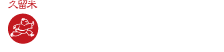去年の春でしたか、このコラムで矢部村のお話をしました。そう、幻の食材“干し竹の子”探しの果てに、僕が出会った“福岡県内最後の秘境”といわれる山村と、そこに棲む素晴らしい人たちの話でした。その文中に「この出会いは“ただならぬ出会い”になる予感に包まれた」という一節がありましたが、今回はその後日談をひとつ。
それは二年前の冬、例の“干し竹の子”件で矢部村の村長さん宅を訪れた日のことです。村長さんのご長男T氏との世間話の中で、地元の子供たちが通う、全校生徒13名という小さな小学校の話になり、そこの卒業生でもあるT氏にその学校を案内していただくことになりました。
その学校の名は“飯干(いぼし)小学校”。
矢部川最上流域のこの村の学校の中でも、最高(標高)地に位置するその小さな小学校は、うっそうとした森に囲まれた急斜面の狭い通学路を、ひたすら登り詰めた高台にありました。 ちょうど休み時間だったのでしょう、懐かしい木造校舎の中から元気な子供たちが飛び出してきました。瞬間、その子供たちの姿に僕は驚きました。この小雪がちらつく渡り廊下を、何と裸足で駆け回っているのです。そして見ず知らずの僕にも「こんにちはー」と元気なあいさつ。 もはや都会の小学校がなくしてしまった、日本の小学校とその子供たちの素晴らしい原風景がここには残っていたのです。感動している僕に、T氏が一言。
「実はこの飯干小学校もこの春には廃校になり、校舎も取り壊されるんです」
…少なからずもショックでした。聴くところによると、飯干小学校は明治十四年、現在地より低い集落の近くに創立されたものの、七十六年後の昭和二十八年、日向神ダム建設による校舎水没のため現在の高台に移転。そしてその四十三年後の平成十二年、村の過疎化による生徒数減少により、本年三月の廃校が決定し、百十九年の歴史を閉じることになったそうです。 二十歳過ぎから約二十年、全国の渓流を釣り歩いていた僕にとっては馴染み深い、そして大好きな山村の風景の一部がまた失われようとしています。何とも残念で、悲しい気持ちでした。
日本の美しい清流の源流域に息づいてきた山村の典型的な運命、それは戦後の経済成長と共に始まりました。下流のまちを洪水から守り、そのまちへ電力を供給するために、山に棲む人々が太古から開墾し代々守り続けた土地が、ダム湖の底に沈められるのです。その恩恵で下流のまちは栄え、人口が流入し、山の若者までもが職を求めて村を捨て、華やかなまちへなだれ込みました。かくして山村はいっそう過疎化するという、この悪循環のなかで、この国から少しずつ、しかし確実に山村はその姿を消し始めました。日本の山村は、まちへ水と電力、そして若者まで供給し続けながら消滅しようとしているのです。この飯干小学校の運命は、まさに日本の山村の運命の縮図でした。
そんなことを考えながらT氏の寂しげな横顔を見ているうちに、僕の中にある想いがふつふつと沸き立ち、思わずT氏に突拍子もないことをお願いしてしまいました。それは…
‘ラーメン今昔物語’ カテゴリーのアーカイブ
第四十二話 木造校舎のラーメン屋・上
2013年4月13日 土曜日第四十一話 ラーメン屋の中のドラマ・パート2
2013年4月13日 土曜日 今回は、ちょっと古いけど“まんが日本昔ばなし”風に。
~ むかーし昔のことじゃった。ある小さな町の片隅に、これまた小さなラーメン屋があったそうじゃ。もうその店はなくなってしもうたので、このはなし、話しても差し支えないじゃろう。
そのラーメン屋は、変わり者の夫婦が二人でやっとったそうじゃが、なぜかたいそう評判で店の前にはいつも長い行列ができとったそうな。それは、夏のとても暑い昼下がりのこと、この日もこの店には長い行列ができとったそうじゃ。陽炎に揺れるながい長~いそんな行列の最後に、幼い男の子を連れた母親がそっと並んだそうな。炎天下で木陰もない行列はなかなか前に進まず、その母親は自分の影でその子の日除けをつくりながら、ひたすら入店の番を待たそうじゃ。
半時(約1時間)も待ったじゃろうか、母子はやっとの思いで、冷房の効いた涼しい店内に入ることができたそうじゃ。ところがじゃ、母子が入るやいなや「いらっしゃい」どころか、店のオヤジはいきなり「帰ってくれんか」といったそうじゃ。母親が驚いてその訳を訊くと、オヤジは黙って店内の張り紙を指さした。そこには「子供連れお断り」と書いてあった。母親は、それは知らなかった。でも暑い中、長時間並んでやっと店に入れたのだから、せめてこの子にだけでもラーメンを食べさせてほしいと哀願したそうじゃが、「わしの店の掟じゃ」と、ラーメンどころか水の一杯も与えず、けんもほろろにその母子を追い出したそうじゃ。周りの客は皆、そんな母子を見て見ぬ振り、知らん顔じゃったそうな。なんと悲しい話じゃ。
そのオヤジは何かと“掟”が好きらしく、ある客が「替玉」を注文してもオヤジは知らんぷり。大きな声で何度注文しても、知らんぷり。たまりかねて怒鳴ると、オヤジは黙ったまま張り紙を指さすそうじゃ。そこには「『替玉』”ではなく『替麺』と言って下さい」と書かれていたという。掟と張り紙が好きなオヤジは、掟を忠実に守る客しか客と見なさぬらしく、やがてそんな客たちの会ができ、その会員はなんと忠実度で“階級分け”までされていたそうじゃ。驚くべきことじゃ。その後、その店とそのオヤジ夫婦がどうなったかは、なんせ遠~い昔の遠~い町のはなしじゃから、とんとわからん。 ~
と、まあこのはなし、実話か作り話かは皆さんのご想像におまかせするとして、この店の雰囲気は何となく、先々月このコラムに登場した“北の国から”のラーメン屋に(行列以外は)基本的に似てますね。もしかしたら倉本聡氏もこの店に行ったのかも…?
ところで「先月登場したお前の店のバイトのM君はどうしてるか」って?はい。元気に頑張ってます。彼は将来ラーメン屋になりたいそうです。
第四十話 ラーメン屋の中のドラマ
2013年4月12日 金曜日僕の店Tラーメンの本店に、M君という高校生のアルバイトさんがいます。小柄で童顔な彼は、とても高2には見えない幼い容姿をしていて、高校入学直後アルバイトを始めたばかりの頃など、彼には大きすぎるエプロンをつけてチョロチョロ動く姿を見たお客さんから「小学生を働かしちゃイカンばい」と言われたほどです。その頃のそんなM君のお話。
ある日、Tラーメン本店はその日の営業も終わりに近づいていました。客席には最後のお客さん(小学2年生くらいの男の子とそのお母さん)ひと組だけでした。やがてそのお客さんも帰られ、閉店時間の9時になりました。スタッフが外の照明を消し、後片付けを始めようとしたその時、突然M君が消えたのです。慌てたスタッフたちが店中を探しても、どこにもM君の姿は見あたりません。騒然となったスタッフたちでしたが、やがて誰かが近所の公園でポツンとブランコに座っているM君を見つけました(まるで黒澤映画「生きる」のラストシーン)。
T副長が駆け寄ってそっとのぞき込むと、M君はなぜか泣いているのです。T副長は安堵しつつも一瞬「俺、今日Mに何かやかましく言ったやろか?」と心配になり、自らを問うてみても、思い当たるフシはありません。そこで優しく尋ねてみると、M君は涙をポロポロ流しながら話し始めました。
以下、M君談。「さっき、お母さんと子供のお客さんがおっちゃった(いらっしゃった)でしょ。僕がお水を持っていったら、お母さんが『昔ラーメン二杯でいくらですか?』ち訊かっしゃったけん『900円です』ち答えたっですよ。そしたら、そんお母さんは財布から小銭ば全部出さしゃって、一枚づつ数えらっしゃったとです。そいが、何円か足らんやったごたるふーで(足りなかったみたいで)注文のラーメンは一杯になったとです。そして僕が運んだ一杯のラーメンば二人で…、小皿に分けて、少しずつおいしそうに…ほんなこつおいしそうに食べよらっしゃったとです。僕はそげな子供とお母さんば見よったら、なんか知らんばってん、可哀想になって、悲しゅなって…、涙ん出てきたけん外に出たとです。すみません」
それを聞いたT副長はそんなM君の優しい心にとても感動し、「その時おれに一言その母子のことを言ってくれれば…」と言いかけたものの、子供のように純粋なM君の目からこぼれる涙を見ていると、それ以上何も言えなかったそうです。
テレビドラマの中にはしばしばラーメン屋が出てきますが、現実のラーメン屋の中にはテレビドラマより素晴らしいドラマがあります。この話、もう少し続けさせてください。
第三十九話 ドラマの中のラーメン屋
2013年4月12日 金曜日 先日、僕の一番好きなTVドラマ“北の国から”が最終回を迎えてしまいました。21年も続いたこのドラマの熱烈なファンは多く、皆さんも僕同様、とても名残惜しい思いをしてることでしょう。“北の国から”シリーズには、その長い年月のなかで数々の名シーンがありました。その中のひとつ“北の国から’84夏”より僕が印象に残ったシーンを、つたない記憶のままに紹介させて下さい。
(シナリオ調で)~ある夏の日の夕暮れ時。兄の純と妹の蛍はまだ小学生。二人は父・五郎と三人で、閉店時間間際のひなびたラーメン屋のテーブルに座っている。五郎がラーメンの注文を終えると、わずかな沈黙が流れる。薄暗い店内には、やる気のない女性店員一人と客の五郎たち三人のみ。テレビの音だけが無機質な音で流れている。
先刻より元気なくうなだれていた純が静かに喋り始める。
純「父さん、ごめんなさい…。最初に(事故を起こした)イカダに乗ろうと言い出したのは僕の方で…」
純は五郎に隠していたことを、懸命に涙をこらえながら告白し始める。五郎は黙って聞いている。店員がラーメンを持ってくる。
店員(迷惑そうに)「もう閉店の時間ですから早くしてくださいよ」
投げやりにラーメンを置かれて、五郎はぺこりと頭を下げる。五郎と蛍はラーメンを食べ始めるが、純はうつむいたまま話を続けている。店員はカウンターに座って退屈そうに煙草をふかしている。
純「それから…(友人の)パソコン雑誌を黙って持ち出したのも僕で…」
純はまだラーメンに手を付けず、告白を続ける。涙があふれている。
いつしかテレビが消され、三人の帰りを促すように店内の電気が消される。三人はわずかな明かりの下でテーブルを囲んでいる。
純「僕は卑怯で…」
純の涙が床にこぼれ落ちている。五郎は、自分もかつて純から「父さんは最近パワーがなくなった」と指摘され、そのことで気づかせてもらったことを素直に純に伝える。
そこで店員が、うんざりしたように言う。
店員「ねえ、まだですか?」
五郎は再度店員に頭を下げる。蛍が兄をいたわるように優しく言う。
蛍「お兄ちゃん、食べよう」
ようやく純はのびたラーメンを食べ始める。しかし涙でのどを通らない。五郎は店員を気遣ってポケットから小銭を取り出し、先に勘定を済ませる。
すると店員は食べ終わってない純の丼をいきなり下げようとする。そんな店員に、静かな五郎が初めて興奮する。
五郎「こ、子供がまだ食ってる途中でしょうが!」
驚いた店員は、思わず丼を床に落としてしまうが、そのままプイと立ち去ってしまう。店員がいなくなった暗い店内。三人は床にしゃがみ込み、割れた丼を片づけている。妹は兄を、そして父親は息子をいたわるように…(テーマ曲IN F・O)
いかがでしたか?皆さんはこのシーンを思い浮かべながらどう感じました?
第三十八話 函館・塩ラーメンサミット・その4
2013年4月12日 金曜日 かくして、久留米からやって来たペテン師に煽られた(?)地元函館の有志たちは立ち上がりました。委員会の発足です。その名は“函館塩ラーメンサミット実行委員会”。
委員長には函館製麺組合理事長の宮川照平氏が選任されました。当初はわずかなメンバーで発足したこの委員会も、町を活性化したい一心で東奔西走する岡田さんや宮川さんたちの情熱に打たれたのでしょう、日を追うにつれメンバーは次第に増えていき、その数約50人という、町中のあらゆる業種を巻き込んだ大所帯の委員会になりました。
やがて、その年の11月、久留米のラーメンフェスタ会場に函館の委員会の視察団が大挙して訪れました。それも何と函館市長の親書を携えて!その親書は、フェスタの会場で函館の宮川委員長によって久留米の白石市長の手に華々しく手渡されました。そうです、この列島南北の二つのまちに、ついに行政交流がはじまったのです。ただし、この函館の視察団が久留米のラーメンフェスタ会場で目の当たりにしたものは、2日で10万人という、空から見れば巨大な怪物のような群衆と、長さ数百メートル・待ち時間6時間という人気ラーメン店に並ぶ怪物の尻尾のような長蛇の列でした。視察団はただ呆然、ひたすら唖然。視察団にとって久留米の視察は、「これから自分たちがやろうとしていることはトンデモナイことかも知れない」という恐怖感を抱かせる結果となってしまったようです。
しかしながら!函館に戻ってからの委員会は、久留米で体感したその戦慄を、逆にエネルギーにして、それこそ“まちおこしの鬼”と化したのです。そんな鬼たちの大所帯委員会ですから、意見は十人十色、その議論は常に白熱した激論となり、本番ひと月前に訪れた僕の方が戦慄を感じるほどでした。
そして今年の5月24日、ついにその日がやって来ました。開催期間3日間、2会場にラーメン店15店舗という久留米の規模を越えた“函館塩ラーメンサミット&函館塩ラーメンフェスティバル”は、白石勝洋久留米市長の親書が井上司函館市長の手にしっかりと渡されて開幕し、来場者3万7千人という北海道最大のラーメンイベントとして道内の話題を独り占めしながら大成功のうちに幕を閉じました。最終日の打ち上げでは、函館の委員会メンバーは皆、感動して泣いていました。いい歳したオジサンたちが、手を取り合って顔をクシャクシャにして泣いている姿を見て、久留米のペテン師も思わずもらい泣きでした。思えば、熱海の温泉で偶然出会った函館と久留米のラーメン屋のオヤジの世間話が、2つのまちの民間交流を生み、いつしか行政交流へと発展し、南国から北国へと巨大なフェスティバルを伝播させてしまったのです。
“ラーメン”のパワーって、何なのでしょう?僕自身、怖くなるときがあります。
第三十七話 函館・塩ラーメンサミット・その3
2013年4月12日 金曜日 熱海で出会った数日後、岡田さんはさっそく両手一杯のお土産を提げて久留米に来られました。もちろん目的は「ラーメンフェスタin久留米」の調査・研究です。僕の事務所には、過去2年分のフェスタの膨大な資料があります。僕はその資料を1つひとつ説明しながら、中でも運営上必要と思われる資料はコピーして岡田さんにお渡ししました。(フェスタは営利目的ではないので一般の会社のような機密事項はありません)。
岡田さんは、その資料を宝物のように大切に持ち帰られました。
そして、ひと月後の8月でしたか、「愛の貧乏脱出大作戦」の収録を終えたばかりの頃、今度は僕が函館によばれました。岡田さんの声がかりで集まった函館市内の製麺組合の方々や、僕と同じラーメン屋さんの方々に、町おこしとしての“ラーメンフェスタの効果”を伝えるためです。しかし!“たった2日で10万人の人を集める”というラーメンの持つパワーを、会場のほとんどの人が信じようとしません。「それは久留米だから出きたことだべー」とか「北海道のお客さんは外に並んでまでラーメンを食べてぇとは思わんしょー」等々否定的な意見ばかり。でも、考えてみれば、僕自身、2年前に初めてこのフェスタを企画したときは、とにかく不安ばかりで「だーれん来んかったらどげんしゅー」また「事業予算が1千万円げな、こりゃ赤字こいたら夜逃げせなんばい」・・・こんなことばかり考えていました。まさか、10万人の人が押し寄せ、マスコミが押し寄せ、あんなに異常な盛り上がりをみせるとは、夢にも思いませんでした。函館の人たちにとって、話には聞いても、実際のフェスタを目の当たりにしてないものですから、信じがたいのも無理はありません。僕の姿が“南から来たペテン師”に見えたことでしょう。
長時間の質疑の末、最後にペテン師は熱く語りました。「函館と久留米には、“不景気の町”というあまり嬉しくない共通点があります。ばってん、函館の方が絶対的に優位な部分があります。それは北海道でも指折りの観光資源と、そこに集まる年間5百万人という観光客です。一方、久留米には観光客どころか観光資源すらありまっせん。でも、観光資源ちゅうのは、いわゆる名所旧跡や景観だけを言うとでしょうか?“文化”は観光資源にはなり得んとでしょうか?否!その答えをラーメンフェスタが証明してくれたとです。最後に、函館と久留米にはもう1つだけ共通点がありました。それは塩と豚骨、各々のラーメン発祥の地という文化財産です。ラーメンフェスタ、やりましょう!」
第三十六話 函館・塩ラーメンサミット・その2
2013年4月12日 金曜日 目をこらしてよく見ると、その湯気の向こうのオヤジ型の座敷わらしは、実はオヤジ型のラーメン屋でした(なら最所から「ラーメン屋のオヤジ」って言えよ!お前もそうやん!)その人は、函館の塩ラーメンを全国にブレイクさせた“マメさん”というラーメン屋さんのご主人で、大きな製麺会社の社長でもある岡田さんという、立派な初老の紳士でした(座敷わらしとか言ってゴメンナサイ)。
互いに初対面だったのですが、岡田さんの方は、僕が支那そばやの佐野さんと共演したテレビを見ていただいてたらしく、「その後奥さんはどうですか?もう300日もかかる買い物には出られてませんか?」などと、僕のとっても恥ずかしいプライベートまでご存じなのです(テレビカメラの前でペラペラ喋ったのは自分やった、忘れとった)。
そんなことより、岡田さんが一番興味を持たれたのは、僕が“久留米でラーメンフェスタを仕掛けたラーメン屋”という部分でした。一昨年、新横浜ラーメン博物館の出店をきっかけに全国に函館の名を知らしめた氏にも、かねてより「なんとか“塩ラーメン”で函館の町全体の活性化ができないか」という強い思いがあったそうです。氏が言われるには「それがある日、函館の町である史実が発見されたんです。それは、“南京ソバ15銭”と書かれた明治17年の小さな新聞広告でした。これは、函館(塩)ラーメンの始まりを示すものであり、この広告にある“養和軒”という店が、何と今までのラーメン史を覆す、日本最古のラーメン店ということが判ったんですよ」ということでした。
そうです。久留米が“豚骨ラーメン発祥の地”なら、函館は“塩ラーメン発祥の地”だったのです。北海道の函館と九州の久留米、この南北1500kmの隔たりがあっても、同じような“ラーメン文化の素晴らしい史実”を持った2つの地域。その2つの町のラーメン屋のオヤジが、それも「ラーメンで町おこしをしたい」という同じ志をもった者同士が、なんと両者の中間地点のような静岡・熱海の温泉宿の風呂場でばったり出会ったのであります。
「これを運命といわずして何といふ」であります。
第三十五話 函館・塩ラーメンサミット
2013年4月12日 金曜日 久留米の皆さんはご存じ「ラーメンフェスタ」。そう、毎年11月に久留米百年公園で開催される日本最大のラーメン祭りです。去年の第3回フェスタには、市内を代表するラーメン店7店に加え、かの有名人“ガチンコ”の鬼師匠・佐野実氏の「支那そばや」、その弟子の「ラーメン道」そしてTVチャンピオン3連覇・河原成美氏の「一風堂」という錚々たるゲスト店が勢揃いし、10万人の人がそこに押し寄せたという、まさに日本一の賑わいを見せたラーメンイベントでした。
実はこのラーメンフェスタが、何と!北海道の函館でこの5月(このコラムは5月中旬執筆)24日~3日間に開催されるというのです。といっても、これは函館の地元有志による実行委員会が企画したもので、そのフェスタの正式名称は「函館塩ラーメンサミット&函館塩ラーメンフェスティバル」といいます。内容はパネルディスカッション(佐野氏・河原氏・他)を中心とした「函館塩ラーメンフォーラム」と、“花より団子”バナシよりラーメンの貴兄お待ちかねの食体験型(久留米型?)「函館塩ラーメンフェスティバル」という2部構成。そのイベント会場のラーメン店出店数はゲスト店を含めて14店(久留米は10店舗)で、さらにそのイベント会場を市内2会場に分けて実施するという、その規模・予算は久留米のフェスタを遙かに上回るという、恐るべき企画のラーメン祭りであります。
~そのフェスティバルの成否やいかに・・・次号乞うご期待~などと人ごとのように終わりたいのですが、この函館の企画、実のところ僕も無関係ではないのであります。
♪(「喝采」のメロで)~あれは1年前、泊まる、熱海、湯船の中~♪と、ヘタな替え歌で始まってゴメンナサイですが、それは去年の梅雨入りしたばかりの6月のことでした。なぜか僕は“貫一お宮”で有名な伊豆・熱海温泉の古びた旅館におりました。なぜそんな処に僕が居たのか?それは定かではありません。そんなことより、その日僕は、夕暮れの露天風呂で暮れかかる湯煙の庭を眺めながら、一人悦に浸っておりました。昨夜北の強い風で散った広葉樹の葉が一面に浮かんで地面と区別がつかない露天風呂に僕一人が浸かっている、その光景を端から見れば、落ち葉で覆われた地面から、まるでキノコのようにオヤジの生首が生えているようなものでしょう。次に入ってくる人が驚いて叫び声を上げる前にと、僕は落ち葉をかき分けながら室内の洗い場に戻ることにしました。
すると、貸し切り状態で誰もいないはずの洗い場のどこからか、ささやくような声が聞こえてきたのです。「・・・Kさん・・・Kさん」目をこらすと湯煙の向こうにボンヤリ人影のようなモノが見えました。こ、これは座敷わらし?いや、それにしてはやや大振りで歳くってる。オヤジ型の座敷わらしか(おまえがそうだよ)?
第三十四話 『昔ラーメン完成』
2013年4月12日 金曜日 福岡県八女郡矢部村。この村は、清流・矢部川の源流域に位置し、大分との県境にそびえる高峰・釈迦岳(1231m)の山懐にひっそりと息づいてきた“秘境”の名にふさわしい谷あいの小さな村です。 村の主幹産業はもちろん農林業。世帯数はわずか642世帯で、村民1,884人の過半数を高齢者が占めるという典型的な日本の山村であります。僕がこの矢部村を訪れたのが平成十二年の寒い冬の日でした。
山肌にへばりつくようにうねった矢部川沿いの道を、足のすくむような日向神峡を眼下に見ながら、 ひたすら車を走らせてようやくこの村に辿り着きました。 この日、僕は知人の紹介で村長宅におじゃましたのですが、この村長さん(厳密にはこの翌年に村長になられた方なのですが 文中ではあえて“村長さん”とします)が、また素晴らしい方でした。初対面で、しかも僕のようなイキナリ都会(?)から やってきたラーメン屋のオヤジを、怪しみもせず家族総出で迎えていただき、日本一の栄誉に輝いたという八女茶で もてなしてくれました。
僕はこれほど旨い茶を過去に飲んだことがなく、その感激に酔いしれながらも、僕がここに来た目的である“干し竹の子探し”の話と“昔ラーメン”にまつわる亡き父の話を熱っぽく語りました。
ところが僕は自分の話を真剣に聞いてくれる村長ご一家についつい甘えてしまい、いつしか時間の経過を忘れてしまったようです。 ふと気づくと、懐かしい縁側のガラス窓越しに見える向かいの山が、すでに夕日の色に染まっていました。 あわてて僕は、このもてなしの謝意を述べ、今日はひとまず辞そうとすると、すかさず村長婦人が「夕食もどうぞ」。 僕は「トンデモナイ」と重なるご厚意に恐縮しながらも、チャッカリご馳走になってしまったのでありました (自家製の酢味噌で食べる山菜は絶品でした)。
帰路、すっかり暗くなった山道を走りながら、 僕は3年程前のこのコラム「北海道ラーメン行脚」以来の辺境の村と、そこに棲む“タダモノではない”人々に出会った感動、 さらに、この出会いは単なる食材の取引で終わりそうもない“ただならぬ出会い”になりそうな予感に包まれたのを憶えています。
やがて冬も終わり、釈迦岳山頂の雪も消え、早春の雪渓に咲くフキノトウが山菜の主役をタラの芽に譲るころ、 僕は再び矢部村を訪れました。実はこの日、村長さんの息子さんの計らいで、干し竹の子の件で村中の農家に集まって いただいたのです。当然僕は、前回村長さん宅で語ったとき以上の情熱でその場に臨みました・・・
ところが、 その村長さんの息子であるTさん自信が、僕の思いを、ある意味では僕以上に熱く語ってくれたのです。 おかげでその会合は、唖然とする僕を尻目にスルスルと進行し、やがて全会一致で、Tラーメンのための干し竹の子生産 (年間数トンに及ぶ)が決定してしまいました。何とも表現し難い、有り難い気持ちでした。 “干し竹の子”これが一杯のラーメンに乗っかると“シナチク”という名のわずか十グラム程の食材になってしまいます。 でも、このひとつまみの食材には、実に沢山の人たちの努力や思いが宿っているのです。
“昔ラーメン”。 その昔、僕の父が作ったラーメン、その復活には長い道のりがありましたが、沢山の人たちの温かい協力のおかげで、ついに完成しました。このラーメンの完成も、またこのラーメンの開発がきっかけとなって誕生した店昇和亭も、父はその完成を見ることなく他界してしまいました(昇和亭開店八ヶ月前)。 もし父が生きてたらこのラーメンをどう評価するでしょう。僕には聞こえてきます。 もし皆さんがTラーメンで昔ラーメンを食べる機会があって、ふとこの物語を思い出していただけたら有り難いです。
その時Tラーメン初代の声が聞こえるかもしれません。
第三十三話 昔ラーメン誕生秘話 その3
2013年4月12日 金曜日 かくして昇和亭は「一杯のラーメンが一軒の店舗を生み出した」というストーリーが評判をよび、お陰さまで“昔ラーメン”は 大ヒット商品となって、昇和亭の看板ラーメンになりました。
やがてお客様からは 「Tラーメンの原点と言うべき“昔ラーメン”が、新店でしか食べれないのはおかしい、何で他店(特に本店)で出さないのか」 という声が訊かれるようになりました。
実は、僕たちはその声を待っていました。お客様のその要望がピークに達した頃、全店一斉に昔ラーメンを発売する予定で、 その準備を進めていたのです。 オープン以来、昇和亭の厨房は社内的に“昔ラーメン調理実習研修所”として全社員の新技術習得の場となっていました。
やがてすべての社員がその技術を習得し、昔ラーメン全店展開のための厨房用具・機器の手配も完了したころ、 僕はある人からスルドイ指摘をされました。
その人は僕の母。すでに現役から退き、夫亡きあとの残された人生をエンジョイ中の、悠々自適の温泉バーサンです。 バーサン曰く「ひとっちゃ(僕のこと)、昔ラーメンにノットット(乗っかってるもの)、あら違うばい。 あらシナチクじゃなかばい。」
僕・・・・ 「そらメンマたい。」
バーサン・・「メンマちゃ何ね?」
僕・・・・ 「タケノコたい。シナチクちゃ何ね?」
バーサン・・「タケノコたい。」
僕・・・・ 「オンナシ(同じ)やろーもん。」
バーサン・・「んにゃ、ちごとっ(いや、違ってる)。」
・・・
と、まあこんなやりとりでありましたが、その途中で僕はハタと気づきました。 そういえば母の言う“シナチク”とは“支那竹”のことで、昔の久留米のラーメンにはコレが乗っていました。 らーめんが“支那そば”と呼ばれていた戦後間もない頃は、久留米の屋台のオヤジさんにとってメンマなどの中国食材など手に入れる術もなく、“やむなしメンマに似て非なるもの”、いわるる“シナチク”を代用としていました。 それは決して“支那の竹”ではなく、“八女”の竹でした。久留米の隣町・八女特産の“干し竹の子”を水で戻し、千切りにしたあと塩と若干の醤油で味付けをして、油で炒めたものです。
さらに、それは食紅で真っ赤に染められて“シナチク”という名で“支那そば”にトッピングされていたのです。 しかしその八女の“干し竹の子”も、昭和三〇年代後半から次第に姿を消し始めました。 そこで、これまた“シナチク”の代用として、久留米の屋台のオヤジさんたちが次に白羽の矢を立てた食材が、 皆様ご存じ“紅しょうが”であります。 「とんこつラーメンには“紅しょうが”」という現在のラーメン界の常識、このルーツが何と、八女の“干し竹の子” だったのです。
僕はショックでした。 完成したと思っていた“昔ラーメン”には、トッピングの部分で大きな落とし穴があったのです。自慢の大リーグボールが、花形満にかるくホームランされてしまった星飛雄馬のような衝撃を受けた僕は、 目前の昔ラーメン全店展開の計画を中止し、“干し竹の子”探しの一人旅に出ました。(実は隣の八女あたり)。
そして長い食材探しの行脚(?)の果てにたどり着いた村が、福岡県内最後の秘境と言われた「矢部村」でありました。 ~だが、そこにはトンデモナイ事態が待ち受けていた!