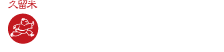実は、僕たちのこの“日本初のラーメン”開発の一連の現場には、この情報を目ざとくキャッチした 某テレビ局の取材クルーが、当初からベッタリ密着していたのであります。当然カメラは回しっぱなし。誰かがひとこと口を開けばその顔を、チョット失敗すればその手元を、忍者のように忍び寄るカメラが 素早くドアップで捕らえます。そんな状況下での試食会でした。
僕たちは、テストキッチンで調理したラーメンを素早く隣室の試食室に運びました。後ろからは忍者の取材クルーたちがスルスルとついてきます。白いテーブルの上に置かれた黒い漆の丼。紫檀色のスープから立ちのぼる淡い湯気と薄茶色の蓮粉の麺(T商店が開発)。部屋には、和風ダシの潮の香りとほのかな中華ダシの香りが溶け合った何とも言えない良い香りが漂っています。食欲をそそらせる条件はそろいました。
まず、テイスターのラーメン研究家・H氏が「待ってました」と、スープを一口すすりました。
・・・(無言)
続いて殿様ご兄弟も一口。
・・・テイスターは全員無言。
いったいウマいのかマズいのか?
この沈黙は僕たちを不安に駆り立てました。いや、粒粒辛苦の果てに作り上げたラーメンです。絶対マズいはずはありません。
やがて長い沈黙を破るようにH氏の口が開きました。忍者のクルーたちは一瞬のうちに、カメラと集音マイクと照明をH氏の顔面に浴びせました。
・・・H氏はひとこと。 「コクが足らんごたあですな」
殿様ご兄弟もうなずきながら、「味は良かばってん・・・」
清湯スープの“味”の追求のみにとらわれすぎて“コク”を見失っていたことに気づいた僕は、自慢の大リーグボール3号を打たれた星飛雄馬のような衝撃で、顔中から冷や汗が吹き出しました。 忍者たちはすでに、僕の顔の毛穴に集中してます。追い打ちをかけるようにディレクターがイジワルに質問します。「どうしました?」窮地に立った僕は「どぎゃーんも、こぎゃーんもなかっどー。ホー」と、とりあえず筑前博多の忍者たちには 聞き慣れないであろう、肥後熊本の方言でごまかしてみました。
すると突然、和風ダシ担当の懐石料理人がキッチンに消え、グリルの前で何かやり始めたと思いきや、 数分後一杯のラーメンを手に彼は試食室に戻ってきました。「コレを食べてみて下さい」 テイスターたちは、彼に勧められながらも半信半疑でそのスープを口にしたところ、
H氏が開口一番・・・「ウマい!このスープに清き一票!」
と、感動的名言。そしてテイスター全員、異口同音で絶賛という結果となり、かくしてこの試食会は危機を乗り越えながらも、 最終的にはどうにか満足できる結果で終わることができました。
ところで懐石料理人は、スープにどんな手を加えてコクを出したのか? ラーメンフリークの読者諸氏はズバリ興味津々でしょう。今回だけ、そんなアナタにだけコソ~っと教えちゃあたい。実は、彼がやったのは、それまでトッピングしていた鴨のミンチを、手鍋に小分けしたスープで煮込んだだけ、 ただそれだけのことです。この簡単な作業が、テイスターを絶賛させる“スープのコク”を生み出しました。至って単純な答えですが、プロのコツとはそんなものです。
それから数日後の、旧柳川藩主邸・御花で盛大に執り行われました「立花柳麺(りゅうめん)発表会」も、お招きした200名を越す各方面の方々から、有り難くも沢山のお褒めのことばをいただきながら、 無事成功裏に終わることができました。かくして、Tラーメンのラーメン研究会という無謀なラーメンバカたちが創り上げてしまった “日本初のラーメン”。このラーメンはその後、柳川から里帰りして、再び彼らの手で改良が加えられました。麺も自社の麺工房で生まれた“黄色いちじれ麺”に変更され、ついに「しょうゆ柳麺」という商品として 完成してしまいました。 とんこつラーメン発祥の地・久留米で、今、新種のラーメンが発祥したのです。くだんの忍者たちのテレビ番組も、ドキュメンタリータッチで感動的に描かれ、視聴者からも好評でした。 (見た方も多いでしょう)。 ・・・実はそのラーメン、一日百杯限定ではありますが、僕たちの店、“TラーメンS亭”で 絶賛販売中であります
。期間限定につきお早めに一度、ご賞味あれ。
‘ラーメン今昔物語’ カテゴリーのアーカイブ
第二十二話 「しょうゆ柳麺」誕生
2013年4月12日 金曜日第二十一話 続・九州生まれの醤油ラーメン
2013年4月12日 金曜日 プロジェクトメンバーたちは、まるで、“開かずのゲート”がイキナリ開かれて「待ってました」とばかりに一斉に駆け出した若い競走馬たちのようでした。しかし、その若馬たち前にはいくつもの障害が待ち受けていたのです・・・。彼らが三百年前のラーメンの食材探しに取り掛かかるべく、ラーメン研究家・H氏の協力で古文書のレシピを入手したものの、手にしたレシピにはあまりにも情報が少なすぎました。このプロジェクトは、前述のように“麺以外の全ての開発”を担当してますが、その古文書には、スープの食材名はただ一つ“火腿(ホウタイ)”とあるだけ。あとは、「薬味として“五辛(ウーシン)”が添えられていた」・・・これだけでした。スープの食材“火腿”とは、いわゆる金華ハム(中国ハム)のことで、中国料理の世界では、このハムでとったスープのことを“上湯(シャンタン)”と呼び、清湯(チンタン:澄ましスープ)系スープの中でも最高級とされています。しかしながら、たとえ高級といえど、この火腿だけでとったスープは今の日本人の舌には合わないでしょう。まして他の調味料のたぐいは一切記載されてません。とにかくスープに使う火腿は、あくまで補助的な食材にして、メインはやはり清湯の基本である“豚骨”と“鶏ガラ”でないとイカンということになりました。
あとはもう想像を逞しくするしかありません。メンバーA曰く「開発コンセプトも“柳川の歴史と風土を生かした、食べて美味なる云々”やろ?朱舜水も柳川におったなら、地元の特産物は当然口にしとろうし、その食材をラーメンに用いても不自然じゃなか。要するに地元食材をふんだんに使ったウマかラーメンば創ればよかっちゃろうもん。」 と、まあ“開き直り”にもとれますが、的は得てます。そしてメンバーBが「そうやん、ダシもとれる柳川の特産物ち言うたらヤッパシ有明海の魚介類やろ!中華スープと有明海の魚介スープのブレンドでいこう!」と提言したところ他のメンバーもこの意見に全員賛成。ようやく基本方針が定まったプロジェクトのスープ班は、“わらすぼ”“うみたけ”をめざして柳川の魚河岸へさっそうと出陣しました。
かたや“五辛(うーしん)”の担当メンバーである懐石料理店店長は、その現物の入手に奔走していました。五辛とは、川 椒(中国四川省の山椒)・白芥子(白からし)・黄芽韮(黄にら)・青蒜絲(葉にんにく)・香 菜(中国パセリ)の、これら中国の二つの香辛料と三つの香味野菜のことです。これらの食材は、知人の中華のシェフや漢方薬店の協力で何とか手に入りました。しかし、はたしてこの五辛をそのまま小皿に盛ってラーメンの薬味に添えたところで、一度口にした人は、二度との次の箸は出さないでしょう。それほど、今の日本人にはなじみのない強い香りや苦みがあるのです。
どっこいそこは百戦錬磨の懐石料理人。とりあえず、黄にらや葉にんにくなどの比較的口になじみのあるものは、細かく刻んでネギとまぜてトッピングすることにしました。あとは強烈なクセを持つの中国パセリと残りの香辛料類です。これも摺り下ろして何か他の食材と絡めて使いたいのですが、これと調和する、うま味が強い食材が必要です。何かいい食材はないか・・・。
ヒラメキました。「そういえば、このラーメンの発表の舞台になる柳川御花といえば名物は・・・“鴨”たい!」このアイデアから生まれたのが“五辛を隠し味にした鴨のミンチ”でした。“ピンチがチャンス”料理の世界も同じです。この懐石料理人の発想の産物は、やがてこのラーメンを大いに救うことになります。
かくのごとく、メンバーたちはプロジェクト発足以来、二ヶ月ほどの間、来る日も来る日もスープの試作を繰り返してきました。そしてようやくスープの原型が完成してきたのが発表会の直前でした。そこでメンバーたちは、それなりにウマいスープに仕上がったということで、とりあえず本番前に、殿様ご兄弟やラーメン研究家・その他関係各位をお招きして小さな試食会を催そうということになりました。
やがてその試食会の日。我がプロジェクトが手掛けた生まれたての新型清湯スープに、T商店が開発した“蓮粉の麺”を入れて本番同様の姿のラーメンを、お歴々にご試食していただいたのですが・・・
そこにはトンデモナイ事態が!
第二十話 九州生まれの醤油ラーメン
2013年4月10日 水曜日 申し訳ない!前号で「次回は“ガチンコ・ラーメン道”のお話」などと言っとりましたが、やはり、柳川の殿様の勅命で完成したというラーメンの話を今回も引き続き書かせていただくことにしました。というのは、そのテレビ番組を語るうえで恐らく出るであろう「久留米のとんこつラーメン屋の弟子が、なんで東京ラーメンを修行しとるのか?」というナゾにお答えするためにも、まずは柳川のラーメン話が先かな?と思ったからであります。どうかご容赦いただきたい。
さて、僕のラーメン屋では一年ほど前に、あるスタッフの発案で「とんこつ以外のラーメンも勉強したいと思ってる人寄っといで」を合い言葉に、社内の有志が集まって“ラーメン研究会”なるものが発足しました。彼らは定期的に厨房屋さんのデモキッチンを借り切っては自主的に醤油ラーメンや味噌ラーメンの研究をしておりました。当然僕のラーメン屋はとんこつラーメンの専門店です。たとえそれら毛色の違うラーメンが見事に完成したとしても、“ワンブランド・ワンコンセプト”を大切にしている僕の店では定番商品としての発売はできないことを彼らは知っていました。にもかかわらず、彼らのラーメン研究に対する情熱は衰えるどころか、ついには福岡・桜坂の懐石料理店の店長(身内ではありますが)まで巻き込んでしまう程の熱心さでした。
やがて彼らの情熱は“地元食材をテーマにした清湯(ちんたん/澄まし仕立てスープ)系の醤油ラーメン”という素晴らしい“作品”を生みだしたのです。しかし不憫なのは、そのラーメンの生みの親である彼らです。その情熱に打たれた僕からは、“社内で自由に創作活動ができるテストキッチン(実験厨房)の新設”という褒美を得たものの、せっかくそこで誕生した作品も、その発表の場がありませんでした。
そんな折り、例のラーメン研究家のH氏を介して、かの柳川の殿様T氏にお目通りをいただく機会がありました。その場所は旧柳川藩主邸・御花、その一角にある静かなレストランでした。大きな窓の外は名勝・松濤園。やや緊張しながら待っていた僕の前に現れた殿様(社長)と弟君(専務)はとても穏やかなひとでした。ところが殿様ご兄弟はともかく、この場を設定したH氏とその仲間の仕掛け人たちの間で、あるもくろみがなされていたのです。それは、くだんの柳川藩と水戸藩のラーメン論争は僕も知っていましたが、なんと僕たちに、その論争の中心人物である“朱舜水”(しゅしゅんすい)のラーメン・レシピをもとに柳川独自のラーメンを、この柳川で創ってみてはどうか?というものでした。実は僕にとって、これはとてもタイムリーな話でした。あのラーメン研究会の作品に発表の場が与えられたのです。しかも朱舜水が作ったのラーメンのスープは、研究会が創った“清湯”に近い“上湯(しゃんたん/中国ハムでとったスープ)系”なのです。話はトントン拍子に進み、作品の名称が決まりました。
その名は「立花柳麺(りゅうめん)」コンセプトは「単に古文書どおりに再現した資料館展示用のラーメンではなく、柳川の歴史と風土を生かした、食べて美味なる幻のラーメン」です。そして、「朱舜水の蓮粉(レンコンの粉)の麺はT商店が担当し、スープ・その他の具材は僕たちTラーメンが担当」という役割分担が決まり、また「幻である以上一日限りの作品発表とし、発表会場は御花の大広間とする。尚、発表会の招待客は地元有識者を中心に二百名とする云々」と御前会議よろしく粛々と勅令が下知されました。僕がこの話を社内に持ち帰るや否や、がぜん喜んだのはやはりラーメン研究会の有志たちです。さっそく僕は、それまで同好会扱いだったラーメン研究会を、正式な社内プロジェクトチームとして発足させました。当然彼ら有志たちはプロジェクトメンバーとして、意気揚々と立花柳麺開発の任務に就いたのは言うまでもありません。
第十九話 幻のラーメン(下)
2013年4月10日 水曜日 ラーメンを初めて食べた日本人は、はたして水戸の黄門様か?はたまた柳川の殿様か?ときは平成十一年一月二十日。天下分け目のラーメン合戦は、ホラ貝ならぬニュースステーションのテーマ曲を合図に、イキナリ柳川藩主(直系の子孫)T氏と水戸の郷土史家(?)の一騎打ちとなりました。
まずは先手を取った柳川のT氏が「朱舜水は水戸に招かれる前に何年も柳川藩に世話になっていた。当然そのお礼にラーメンを献上したはずだ」と切り出しました。水戸側はすかさず「こっちには、その朱舜水の記録もラーメンのレシピも残っている」と、くやしかったらこれ以上の証拠を見せてみろと言わんばかりに切り返す。
すると行司役の久米氏が「ということは、柳川の負けですか?」と、あおり立てる。
すると柳川藩主は「この無礼者!手討ちじゃ!」・・・とは言いませんでしたが、ただ静かに「柳川でラーメンを食べてないという証拠もない」と論破。
~やがて両者一歩も譲らぬ果てしなき戦いの様相となるも、放送時間の都合であえなく終了。ついに軍配はいずれにもあがらず此度(こたび)のいくさは幕切れと相成り候~かくのごとく日本最古のラーメンは“幻”のまま、遙かな歴史の深奥に封印されてしまいました。
ということで、二年ほど前のラーメンにまつわる楽しいエピソードを書いてみました。そこで歴史の話が出たついでといっては何ですが、恥ずかしながら私めの「ラーメン史」の基礎講座(?)を少々。サテ、日本のラーメンは明治四年の日清修好条約後、横浜・神戸・長崎に置かれた中国人居留地(南京街:今の中華街)に誕生した中華料理店の麺料理が、一般的にはそのルーツといわれてオリマス。ところが、ラーメンは中華料理店で食べる中国の麺料理からいつのまにか独立してしまい、いまや新たな日本の国民食になってしまった感があります。
そのラーメンが南京街を飛び出したのが明治の後期、“支那そば(または“南京そば”)”という名で東京の屋台に ちらほらと姿を現しはじめ、やがてその味は、日本人の手で日本人に合うように改良されて、現在のラーメンの原型が形づくられてきたのであります。
やがて“支那そば”は戦後“中華そば”そして“ラーメン”と、その名を変えながら現在に至っておるのす。ちなみにそのラーメンを“九州ラーメン”“東京ラーメン”“札幌ラーメン”と、大きく三つの源流に分けると、その発祥の“店”は次のようになります。
まずは明治四十三年東京・浅草の「来来軒」。横浜の中華街を飛び出した支那そばがこの店で大評判となりました。この支那そばが、東京ラーメンの原型といわれています。
次に大正十二年、札幌農大(現在の北海道大学)前にあった「竹家食堂」。農大の中国人留学生のために出していたこの店の“拉麺”が現在の札幌ラーメンの源流といわれており、またその“拉麺(ラーミェン)”が“ラーメン”の語源となったという説もあります。
そして最後の源流は、久留米の屋台「南京千両」を発祥とする“九州ラーメン”。この店は、旧日本軍が中国・南京を占領した昭和一二年に開業しており、創業者・宮本時男氏が当時の戦勝記念の意味を込めて命名したこの屋号には、そのまま日本の歴史を感じることができます。さらに、その発祥の屋台が現在でも営業されているというのは、ラーメン史の奇跡とまでいわれてオリマス。・・・と、チョットばかりアカデミックな話をしてしまいました。しかしまあ自分も、とんこつラーメン発祥の地は久留米だクルメだと、ワイワイ騒ぎながらまちおこしなんぞやっとりますが、上には上、昔には昔があるもんです。まして三百年前の黄門様からは「まだまだ青い」と一笑に付されそうです。
ところで「頭の足しよりハラの足し。その柳川のラーメンはいつ食わるっとや?」という貴兄の声が聞こえてきます。心配ご無用。実は、恐れ多くも柳川のお殿様より私めへ「日本初のラーメンを作れ」という勅命をいただいたのでアリマス。そして苦労の末それは完成しました。その味を文字で表すと「九州山海珍味盛沢山的清湯系醤油柳麺」といったところでしょうか。
詳細報告はいずれかの機会に。 本日はこれにて。
第十八話 幻のラーメン(上)
2013年4月10日 水曜日 突然ですが問題です。
「初めてラーメンを食べた日本人はいったい誰でしょう?」
さっそくですが答えです。
それは・・・「ええい控えおろう!そのかたは天下の副将軍・水戸光圀公にあられるぞ、控え!控えい!」・・・ということで、その答えは水戸黄門でした。
いきなり歴史のクイズで始まってしまいましたが、今回は皆さまを“ラーメンと日本史の世界”へといざないましょう。それは寛文五年(1665)といいますから、今から三百三十五年も前のことです。日本中のお茶の間でお馴染みの、水戸のご老公のツヨーイ家来、あのカクさんは、安積覚兵衛という名の実在の人で、本職は中国語の通訳でした。実はこの人が書き残した文献の中に、水戸黄門がラーメンを食べたという事実が書かれていたのです。当時は“ラーメン”という言葉はなかったので、その見た目から“うんどん(うどん)のごとく”と表現されていました。その“うんどんのごとき”ラーメンを作って黄門さまに献上したのが、明(当時の中国)から亡命してきた儒学者・朱舜水(しゅしゅんすい)でした。そのラーメンのレシピも古文書に記載されており(ちなみに新横浜ラーメン博物館の館内には、その古文書をもとに再現された“日本最古のラーメン”のレプリカが展示されてます)、それに目をつけたのが黄門さまのお膝元・茨城県水戸市のラーメン屋さんの有志たちでした。
さっそく、その有志たちによって“黄門さまが食べたラーメン”をコンセプトにしたラーメンが開発され、やがて水戸市内の各ラーメン屋さんで“水戸藩ラーメン”と銘打たれた新ブランドのラーメンがデビューしました。
このニュースは、新たなご当地ラーメンの誕生としてテレビなどで取り上げられ、全国に紹介されました。久留米が“とんこつラーメン発祥の地”ならば、水戸は“日本のラーメン発祥の地”というところでしょうか。はたして水戸のまちで一大ラーメンブームが巻き起こるか?と思いきや、それに待ったをかけたのが、九州・柳川でした。
異論を唱えたのは、九州屈指のラーメン研究家H氏。旧柳川藩主立花家の家臣を祖先にもつ氏曰く 「そもそも水戸黄門にラーメンを食べさせた朱舜水の最初の亡命先は九州・長崎であり、その後六年間、朱舜水の九州での逗留生活を支えていたのが柳川藩の儒学者・安東省菴であったという史実がある。やがて水戸藩に招かれた朱舜水が水戸黄門にラーメンを献上したのなら、その前の九州逗留時代、自分の生活を支えてくれた柳川藩の安東省菴もしくはその主君にも、同様の御礼をしたに違いない」というのです。
当然このH氏の異説にもマスコミは飛びつきました。“東軍・水戸藩と西軍・柳川藩・ラーメン戦国時代到来”こんなノリでテレビ討論の企画が組まれました。戦場は関ヶ原ならぬ、あの久米宏のニュースステーション。水戸市と柳川市にテレビカメラをセットしての生中継。開戦を目前にラーメン研究家の軍師H氏は戦略を練りました。 氏は「水戸藩は例の古文書を盾にして、歴史上のスーパースター・水戸黄門を前面に押し出してくるであろう。多勢に無勢、どうみても相手方軍勢に利がある。よし、それならば我が方は、実在の柳川藩主のご子孫にご出陣願おう。これがかなえば千万の兵を得たも同じ」と考え、世が世ならお目通りもかなわぬ旧藩主のご子孫であるT氏に直訴。あまり乗り気のなかったT氏も、かつての家臣の子孫H氏の切望を無下にも断れず、やむなく承諾。その本陣を旧立花邸お花とし、テレビカメラがセットされました。
かくして東西ラーメン合戦の火蓋は切られたのであります。
第十七話 ヒミツのお話・もういっちょ
2013年4月10日 水曜日 前回のコラムで、ラーメン界の鬼才・佐野さんのエピソードを書きました。実はその直後、ある広告代理店のお世話で、その佐野さんご本人と、博多一風堂の社長・河原さんを久留米にお迎えし、僕を加えた三人で一席設けていただきました。一風堂の河原さんと言えばご存知の方も多いと思いますが、テレビのラーメン職人王選手権で三連覇されたラーメンチャンピオンであります。かたや佐野さんも前述どおり、貧乏脱出大作戦の名物師匠。この日本のラーメン業界をリードする東西のカリスマ二人が会したその席を、もしラーメンフリークが知れば、まるで“豪華二大スタア垂涎の宴”でありましょう。僕も、このお二人とは久しくお付き合いさせていただいてるおかげで“とりあえずの久留米代表”ということになり、その末席に加えていただきました。このメンバーです。話の中身は、言わずもがなの“ラーメン談義”。
~ 以下は、三人の会話(敬称略)~
河原:「佐野さん、いまラ博(ラーメン博物館)で出しとうラーメンはどんな作り方しようと?」(ひそかにサグリをいれるチャンピオン)
佐野:「そうねー麺はね、国産の小麦粉にイタリア産デュラム(小麦粉の一種)をまぜて打ってる。コレですごくコシが出る。カンスイはTラーメンのK君(筆者)も使ってる匂いの少ないモンゴル産だね、これは麺生地が滑らかになる」
H.K :「そう、そう」
河原:「ほー、デュラムねー、オモシロかねー。それでスープは?」(誘導尋問が得意なチャンピオン)
佐野:「スープは“トリプル”でやってる。まず、烏骨鶏や名古屋コーチンなど、全国各地から取り寄せた五種類の地鶏でとったスープ。次に、とんこつの清湯(ちんたん:白濁させない澄まし仕立て)スープ。そして、羅臼昆布や土佐の鰹節、その他諸々の海産物でとった和風ダシ、これも各地へ出向いて吟味して取り寄せたものでね。この三つのスープをブレンドして、一杯のラーメンスープに仕立ててる。」
H.K :「ほう、ほう」
佐野:「ところで河原さん、最近一風堂は味噌や醤油をやめてとんこつ一本になったみたいだけど、なんで?」
H.K :「そう、そう」
河原:「それはね、とんこつのラーメン屋としての原点に帰りたいと思ったと。とんこつスープの基本をもう一度じっくりと見つめ直した上で、今のスープを一層進化させたい、そんな思いで、とんこつ一本に絞り込んだと」
H.K :「正解、セーカイ」
河原:「それで、実はウチもスープはダブルでとっとる。ばってんウチの場合二つ共とんこつで、部位(スネ・バラ・アタマなど)で分けてブレンドしよったい。それとK君が得意な久留米とんこつスープの伝統的なやり方“呼び戻し(前日の古いスープに。きょうの新しいスープをつぎ足して味を調えるやり方)”も研究しよるっちゃん」
H.K :「ありゃ、いつのまにー」
河原:「K君、さっきから相づちばっかりやないね。なんかしゃべりやい。」
H.K :「そーやね・・・(以下略)」
このあとも延々と互いの“ヒミツのレシピの大公開”で盛り上がっていきましたが、今回僕が一番印象に残ったのが、以下の佐野さんのことばでありました。
佐野:「ガンコな職人でも、勉強しないガンコはダメだナ。勉強熱心な弟子に追い越されるのがコワイから何も教えねーんだ。オレはいつも弟子たちに言ってるよ。すべて教えてあげるけど、オレと同じものは絶対できねえ。でもオレを越えるものはできるってね」
・・・と、まあ今回この“ヒミツのお話”シリーズを三ヶ月に渡ってエピソードを五つ書かせていただきました。もう皆さんはお気づきと思いますが、僕が言いたかったのは、単に「とにかく秘密は良くないから相手かまわずノウハウを教えまくろう」ということではありません。実際、長年苦労して築きあげた高い技術を持つ練達の老職人が、その素晴らしいノウハウを入門したばかりの弟子に無節操に与えることはありません。
たとえば、自分でラーメン屋をしたいと思っている若者が、とりあえず支那そばやとか一風堂などの有名ラーメン店に潜り込んで、手っ取り早くノウハウを盗み取って短期間で独立開業しようとしても、それは不可能でしょう。そんな弟子の肝など、佐野さんも川原さんもすぐに見抜いてしまいますし、仮に、そんな弟子が師匠の忠告を無視してたとえ開業したとしても、その店は永くは続かないでしょう。師匠が弟子に“最高の秘伝を伝授する”ということは、その弟子の“心の器”とその“時期”を見極めて、はじめてなされるべきものです。その“心の器”とは、まず「本質を見抜く目」を備えているか?ということ。それは、小さな技術や簡単な作業の裏に隠された深い意味と、その技術を確立するまでの、師匠や多くの先輩たちの苦労を感じ取る心を備えているかということ。そして、自分を育ててくれた両親を含む周りのすべての人たちに「ありがとう」という感謝の気持ちが、その弟子の心に自然に備わっているか?また、その心を一生宿し続けるだけの器量があるかということです。川原さんも言ってました「親に心から“ありがとう”と言えない奴が、店を出してお客さんに心から“ありがとう”が言えるか?」と。そして師匠が最後の秘伝を伝授する、その“時期”とは、弟子が目指す「独立したい」または「一流になりたい」という心の中の目標が、“欲望”から“夢”に変わったときです。“欲望”は自分本位です。“欲望”で目標を達成した人の陰には必ず何人もの傷ついた人たちがいます。“夢”で成功した人は、本人も気づかないうちに、周囲の人たちを幸せにしています。弟子が本当の意味でこのことに気づいたときがその“時期”でしょう。血気盛んな若い時代には、なかなか難しいものもありますが・・・。
長くなりましたが、やはり「与える人」と「与えられる人」ではなく、「与えさせていただく人」と「与えていただく人」という両者の思いやり、この調和が一番大切な心のルールということですね。
今回の五つのエピソードの主人公たちは皆「両者の思いやり」という名の心のルールを大切にし、それを一生貫こうとする「信念」という共通の“ヒミツの「心のレシピ」”を持っていました。ヒミツのお話はこれにてオシマイ。
第十六話 ヒミツのお話・下
2013年4月10日 水曜日ヒミツのお話 その3
かつて日本料理の世界に、“田村平治”という名料理人がいました。
この人は、豊富な料理経験と神業的な調理技術、そして人としての器、どれをとっても日本料理界の最高峰と謳われた人でした。私事で恐縮ですが、福岡の桜坂に、ある懐石料理店がありまして、実は、僕の弟にそこの店長をやってもらってるんですが、その弟のかつての修業先が田村平治さんのお店、東京のつきぢ田村でした。以下は弟から聞いた修行中のお話。
ある日、弟は平治さんに訊ねました。「大旦那、なしてそげ~ん食材やらレシピやら、ホイホイ誰(だ)っでんに教ゆっとですか?企業ヒミツでっしょもん。ここん味ばガメラるっですばい」 と、上京して間もないこのイナカッペ青年の失礼な質問と難解な久留米弁に対し、平治さんは怒りもせず、静かな口調で、「知りたいモンにはナンボでも教えたる。しかしな、同じ食材を使って同じレシピで調理をしても、料理人によって味は十人十色なんや。わしの味はわしにしか出せん。また、お前の味はお前にしか出せん。よう聞け、お客さんはナ、料理人の“レシピ”を食べに来はるんやないで。その料理人の“味”を食べに来はるんや」そして、この関西出身の日本料理の大御所は最後に一言、「わしゃあ、その“企業ヒミツ”っちゅう言葉は大嫌いなんや」と。
これを聞いた弟は、後頭部を出刃包丁の峰で力イッパイ殴られたような衝撃と、温度調節をまちがえて300℃になってしまった天ぷら油よりも熱い感動に見舞われたということは言うまでもありません。平治さんは四年前に惜しくも亡くなられてしまいました。九十歳で逝かれるまで、調理場を終の棲家として最後まで現役を通された平治さんが、日本の料理界に残された足跡はとても偉大なものでした。弟は平治さんから銘入り包丁を頂いた最後の直弟子のひとりとして平治さんへの思い入れがとても深いのでしょう、この話をするとき、いつも目がウルウルしてます。
ヒミツのお話・その4
やっとでましたラーメンのお話。最近、僕と親しくしていただいてる同業の友人(と言っても年上の先輩)に“支那そばや”の佐野さんという人がいます。久留米市民の皆様には記憶に新しい去年のラーメンフェスタ。そう、県内外のラーメン屋さん十店舗が一堂に会し、大盛況だったこのフェスタ会場の中で、最も長蛇の列ができた店の主人として話題になった人であります。 また、テレビ番組・貧乏脱出ナントカにも超キビシイ師匠としてよく出演され“日本一こわい天才ラーメン職人”として話題に事欠かない人でもあります。
それは一年ほど前のことです。突然フラリと久留米にやって来たその佐野さんを、ウチの店長たちと囲んでイッパイ飲っている時のこと。ラーメン談義に座は盛り上がり、話題はいつしか“味噌ラーメン”になったころです。
ウチの誰かが「醤油ラーメンもムズカシかばってん、味噌ラーメンもムズカシかですねー」と言ったところ、佐野さんはサラリと、「俺の店は醤油専門だけど味噌もつくれるよ」と言いながら、おもむろにメモをとりだし、サラサラと味噌ラーメンのレシピを書き始めました。そして、「はいこれ。これでつくってみな。この味ならテレビの“鉄人”だろが“チャンピオン”だろがかなわねーよ」僕たち一同、目が点。すかさずウチの店長が、「よ、よかっですか?そげな大切かレシピば・・・。」 またもや佐野さんはサラリと、「レシピをヒミツにしてるヤツに限って、その中身は大したことねーんだ。その大したことなさがバレるのが恥ずかしいからヒミツにしてるだけなんだよ」
スゴイ。スゴすぎる。このスゴイことを、江戸っ子のべらんめぇ調でかるく言いながらやってのける勝海舟のようなこの人を、ガンコな料理人、特に久留米の閉鎖的なラーメン屋のオヤジさんたちが見れば、彼の発言と行動は極めてアンビリバボーで危険な思想の持ち主にしか見えないでしょう(この場に居たのがウチの者だけでよかった)。
あ、いつの間にかこんなに書いてしまった!もう紙面がない(どころかとっくにオーバーしてる)!でも、もっと書きたい。 「 ヒミツのお話」は今回で終わる予定だったのに来月に繰り越さざるを得なくなってしまった。ゴメンナサイ。
ところで「上」「下」で終わるシリーズは、次を何でつなげばいいんだろう。
第十五話 ヒミツのお話・上
2013年4月10日 水曜日♪それはヒミツ・ヒミツ・ヒミツ・ヒミツのおは~なし♪
(チョット古すぎるかな?)と、思わずヘンなノリで始めてしまいましたが、
イキナリいくつかの短い物語を思い出したので書いてみました。
ヒミツのお話・その1
昔むかしの大正時代、一般の家庭にコンセントなどなく、天井からぶら下がった1個の電球のソケットがその部屋の唯一の電源だった頃のお話。
そのソケットを、ある1軒の小さな電気屋さんが、家族のわずかな手だけで四苦八苦しながら製造していましたした。
ある日、その電気屋のオヤジさんは家族に提案しました。「従業員を雇って生産力を向上させたい」と。なぜか家族は猛反対しました。その理由は「他人を雇うとお金がかかるし、何よりもこのソケットの製造上の“ヒミツ”を他人に知られたくない」というものでした。オヤジさんは言いました。「そんな了見では、この店はただのソケット屋だけで終わってしまう。それどころか、こんな貧弱な技術をさも大層なもののように人にコソコソ隠し、愚かな“ヒミツ”主義に縛られながら商売を続けていても、このソケット屋ですら潰れてしまうだろう。自分はいろんな技術者たちと共に学び合い成長しながら、やがて自分たちの電気製品で日本中の家庭を豊かにしたい」と。そしてこのオヤジさんの思いは実行され、やがてその小さな電気屋さんは、世界有数の家電メーカーになりました。
そのオヤジさんの名は、松下幸之助。
ご存知「ナショナル」の創業者であります。
ヒミツのお話・その2
今から40数年前。自然豊かな北欧の国・スウェーデンのある自動車メーカーのお話。
当時は、アメリカを中心に世界的なマイカーブームが巻き起こり、同時に交通事故が深刻な社会問題になり始めた時代でした。しかし当時の各自動車メーカーは、競って“売れる車”作りのみにしのぎを削り、安全面に関しては現代とは比べものにならないほどおざなりだったそうです。そんな時代の風潮の中で、このスウェーデンの自動車メーカーは、「もっと安全な車を作って、交通事故で失われる人の命を少しでも救いたい」そんな思いで、来る日も来る日も安全のための研究に真剣に取り組んでいました。
試行錯誤を繰り返し、1958年ついに完成したのが、“3点式シートベルト”。そう、現在世界中の乗用車に装備されている、あのタスキ型のシートベルトです。そう聞くと、そこまで世界中に普及したアイデア商品なら、そのメーカーはさぞガッポリ儲かったことだろうと誰もが思うところですが・・・そうぢゃーない。そのメーカー曰く「このシートベルトの開発目的は、世界中のより多くの人の命を守りたい。この一点のみ」ということで、このアイデアに関するパテント料(特許料)は一切無料にし、その製造上の“ヒミツ”も含めた全てのノウハウを他社へ無償で公開したそうです。
この自動車メーカーの社名は「ボルボ」。
そして2000年を迎えた今年、この3点式シートベルトに対し、「20世紀において最も人命を救ったパテント」としてギネスブックに記録されたそうです。
さて、2つのお話がつづきましたが、そろそろ「いつラーメンのハナシが出てくっとや?」という声が聞こえてきそうですね。しかしながら紙面の都合で今回ココマデ。来月までどうぞご辛抱くだされ。
第十四話 ゼニもうけの理論?
2013年4月10日 水曜日 最近ちょくちょくラーメン屋である僕に、様々な業界の方々から講演の依頼が来るので、正直とても驚いています。でも、お声をかけていただくことはとても有り難いことですが、僕はそんなガラでもないし、最近思うところがあって、基本的に講演のお話は辞退させていただいています。僕もかつては、経営に関する講演やセミナーによく参加していました。そこでは僕も他の受講者と同じように、熱心にメモをとりながら、ありとあらゆる経営情報や経営理論を吸収しようと必死でした。
そんなある日、こんなことがありました。市内の大きな会場で、ある大手企業の会長さんの講演がありました。その数日後、なんとその企業が倒産したのです(地元企業ではないのでカン違いされないよう)。その日を境に、さも当然のように、それまで引く手あまただったその会長さんへの講演依頼はすべて中止となり、取り巻きのファンたちも潮が引くように去って行きました。切り替えの上手な世間は現金なもので、会長さんに予定されていたその後の講演は、すぐに他の講師によってその穴は埋められ、何事もなかったかのようにそれらの講演会はとり行われたそうです。これが世の常かも知れませんが、華やかな舞台が突然消え去り、ポツンとひとり暗がりに残されたその会長さんの姿を想像すると、とても切ない気持ちになったことを憶えています。この頃から僕の講演会やセミナーに対する感心は、突如火を消された釜の湯のように熱を失ってゆき、僕のラーメン屋としての本分を見失いかけていたその時期も、経営者の知恵や生き様を完全に商品化する社会のシステムに対する失望と共に終わりを告げました。
それから何年かの時が移りました。あの頃の講演会場で懸命にメモをとっていた勉強熱心な経営者たちは、今どうしてるでしょうか。バブル景気の最中に、講師に言われるがままに行動し、ビジネスが成功して幸せに暮らしているでしょうか。僕には解りません。しかし、1つだけはっきりしたのは、膨大な経営情報や優れた経営理論を駆使した日本経済が、現在皆さんご承知の状態であるということです。これらのことは、決して経営の勉強はだめだということではありません。実際、僕自身過去に学んだ経営理論は、店舗運営には欠かせないものとして重宝していますが、それはあくまで「道具」であり、「理念」ではありません。経営理論という、いわゆる(悪い言い方ですが)“ゼニもうけの「理論」”を「理念」とカン違いしたところから我が国の経済は崩壊し始めたような気がします。“お医者さんは、一生懸命患者さんを治療して喜んでもらってナンボ”“寿司屋さんは寿司を一生懸命握って、お客さんに「うまか」と言ってもらってナンボ”このような、自らに与えられた仕事の本質を見失わず、雑多な情報や目先の儲け話にとらわれない人たちが、来るべき時代を支えるような気がします。
そのときは、経営理論も情報も、人の幸せを崩壊させる“凶器”から、人を助ける素晴らしい“道具”となっていることでしょう。
第十三話 「小さなラーメンフリークたち」~久留米市立南小学校~
2013年4月10日 水曜日~「遠足よりラーメンがよか。」子どもたちは先生に言ったそうです。そして、予定されていた遠足の日は、子どもたち自ら「ラーメン研究の日」に変更し、全員が市内のラーメン屋さんを廻ってラーメンの研究と、ビデオ取材に励みました。やがて、その活動は「知っとるね?久留米とんこつラーメン」と銘打たれ、学校の体育館を会場にした発表会で地域へ公開され、その模様は新聞・テレビを通じて全国に伝えられました。~
これは去年の暮れ、久留米市立南小学校5年生の子どもたちのお話です。僕の店にも、このかわいい取材クルーは来てくれました。「スープのこだわりは何ですか?」「味の秘訣は?プロのコツは?」などなど、もうイッパシのジャーナリスト。傍らにはVTRのカメラマン、音声さん、記録係、あれこれ取材を仕切るディレクター・・・。プロ顔負けの取材攻勢に、取材慣れしてるはずの店長たちも思わず緊張してしまったとか。偶然、南小学校で5年生を担任されている塚本先生が僕の友人でしたので、いろいろ訊ねてみたところ、実際、今回のこの子どもたちの活動は、今後文部省が全国の小学校に推奨する予定の「教科書のない総合的な学習の時間」のモデルケースとされ、立派な「授業」として認められたそうです。時代の変化といいますか、これまでの教科書中心の学力教育から、子供の自主性や個性を大切にしようとする「心の教育」の大切さが叫ばれはじめた昨今、教育の現場でも、その具体的な動きが始まったようです。理論や計算能力をつかさどる左脳が皆無に等しく、お絵かきやお料理、舶来流行音楽や魚釣りなど、およそ学力成績に何の寄与もしない分野のみが得意だった右脳人間の僕としましては、なんとスバラシイ時代が来たものかと、喝采を贈りたい気分です。
ところで、これら教育現場の変化以上に時代の変化を痛切に感じたことがあります。それは、「ラーメン」または「ラーメン屋」に対する、いまと昔の子供たちの意識の違いです。以前のこのコラムの最初の稿でもふれましたが、1軒のラーメン屋台に生まれ、そこで育った僕の少年時代を回想してみると、その頃は、僕にとっても両親にしても、物心共に、決して幸せな時期ではありませんでした。当時は、日本中の人々が、未来に物質的な豊かさだけを求めていた時代で、子供たちは一流大学から一流企業へという、学力と財力を競う人生コースで勝利を得ることが最も尊いと教えられた、いわば「一億総同一価値観」に席捲されていた時代でした。そんな時代のなかで、僕は「お勉強があまりできない」おまけに「ラーメン屋の息子」というだけで、学校の友だちや周りの大人から侮蔑されたことも幾度となくありました。
時は流れ、やがて「バブル崩壊」。これは「おごれる日本人への天の啓示」と僕は思っています。にもかかわらず、いまでも昔の価値観から抜け出せない大人はたくさんいるようですが・・・。しかし、どうも子供たちは違うようです。
文部省の指導ではなく、自分たちの感性で、新しい、そして正しい人生の価値観を感じはじめたように思います。今回、南小学校の子供たちが、自分たちの社会学習のテーマに「大企業」ではなくて「町のラーメン屋さん」を選んだのは、その象徴のように思えてなりません。体育館での発表会終了後、子供たちから沢山の手紙が僕の店に届きました。「これからも美味しいラーメンを作り続けて下さい。」「私たちもがんばるので○○ラーメンさんもがんばって下さい。」・・。僕はこれらの手紙を店のお守りにしています。かつて僕が少年の頃、僕を育てるために一生懸命働く親に向かって「ラーメン屋やら恥ずかしか!」などとバチあたりなことを言ったことを、いま、とても反省しています。そして、ラーメン屋という素晴らしい仕事を残してくれた両親に心から感謝しています。
最後になりましたが、南小学校の5年生のみんな、君たちはラーメン屋でがんばってる大人たちに、この上もない誇りと勇気を与えてくれました。
本当にありがとう。