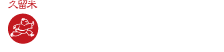前回のコラムで取り沙汰された香辛料「八角」の名誉のために、少々弁解させてください。八角(パーヂャオ:英名Star anise)は、「豚や鶏を用いた中国の煮込み料理には欠かせない香辛料」とされています。日本でも中国料理で一般的に使われる中国のブレンドスパイス「五香粉(ウーシャンフェン)」の中にも、この八角が含まれており、日本人に全く馴染んでないわけではないのですが、なぜ本場の上海料理には、あんなにふんだんに八角が使われているのでしょうか?帰国後、僕は、久留米市内の某・上海料理店の鉄人(自称)に訊ねてみました。
HK:「なし、上海ちゅうとこん料理は、あげん八角がキョーレツかと?」
少々多弁な鉄人:「そやーオマエ、あれたい。八角が好いとっけんたい、ガハハ・・。ちゅーか、(“と言うべきか”の意、“中華”のシャレではない)、それたい、豚たい。特に豚肉料理にハラいっぱい八角使ことったろ?そいはにゃー、(何やらムズカシそうな顔で)国家的豚肉事情の違いたい。オマヤ知らんめーばってん、日本の中華でっちゃ、昔ゃチカライッパイ八角ば使っとったっぞー。昔ん日本にゃ、今のごと配合飼料で育てる品種改良の豚やらおらんやったろーが、そん頃ん豚肉は、残飯で育った昔(品種)の豚の肉たい。そりゃ当然、クセもニオイも今よっか強かったっさい。だけん、八角でクサミば消して、肉の風味ば引き立たせよったと。今ん日本の豚肉にゃ、そん必要はなか。(理解を強要するような顔で)ワカルヤ?」
納得しました。
要するに、“本場上海の料理にクセがあるのではなく、それを輸入した日本の現状が上海料理本来の味をライト化してしまった”というごく自然なことに、いまさら恥ずかしながら、気づかせていただきました。
以前、僕はこのコラムで“「手前味噌」の語源”という切り口から、「人の味覚は、幼年期より体験的に形成され、その味の指向性は、日本中の各地域ごとに異なっており、その地域の食文化として根付いている云々」ということを書きました。日本の小さな“地域”から世界の“国”レベルの食文化の違いを、今回、まざまざと見せつけられました。中国の「手前味噌」は僕にとっては八角というところでしょうか。鉄人の弁は、まだ続いてるようです。
鉄人: 「コラ聞きよっとか!」
HK: 「あ、ごめんゴメン。ところで鉄人、今の日本の豚肉事情はどげん思う?」
鉄人: (少々シンコクな顔で)「そうにゃー、豚肉本来のうま味やコクちゅうとは、昔ん豚肉のクセの中にあったごたる気がする。ばってん。そげな肉は今ん日本の若っかモンは食いきらんめーもん。」
最後に鉄人は、“しかたない”という顔で、・・・「しょんなか。」
ということで、今回のコラムは、九州の一部の地方の人以外は、とても読みづらかったことでしょう。ごめんなさいの謝謝。そして次回も懲りずにおつきあい下さい。
再会(ツェーウェー)。
‘ラーメン今昔物語’ カテゴリーのアーカイブ
第十二話 手前八角
2013年4月10日 水曜日第十一話 上海拉麺事情・下
2013年4月10日 水曜日 バスは、どうにかホテルへ到着し、一行ほっと一安心。ここは、“外灘”という上海の最も賑やかな地区で、ホテルのすぐ前には「黄浦紅」という、対岸まで架けられた吊り橋でも全長が8km以上もある、滔々たる大河が横たい、対岸の上海タワーも遙か遠くに霞んでいます。これでもこの河は揚子江の支流というから、そのスケールには圧倒されます。もはや大陸を実感。また、ホテル側の中山東路へと目を移すと、ここはかつての英国人租界の地。重厚で古色蒼然たる欧州様式の巨大な建造物が立ち並び、阿片戦争以来160年の時を経た今も、当時と同じ姿のまま、圧倒的な存在感で黄浦紅の悠久の流れを見下ろしています。まるで、歴史の中で繰り返される、人間たちの「業」のモニュメントのように・・。なーんてイッパシの史家ぶった感慨にふけってみても、ただのイナカモン。朝からわずかな機内食しか食べてないので、空腹が先に立つ。腹へった。
ようやく現地の有名飯店にたどり着き、出された料理が“ヘビの唐揚げ”。「足のあるものはテーブル以外、空を飛ぶものは飛行機以外、何でも食べる」といわれるこの国の、この飯店で、その後次々に出された料理に、期待の麺類がひとつもなく、肉料理の強烈な“八角(香辛料の一種)”の臭味のみがひどく印象的でした(案内の人、ごめんなさい)。その夜、僕はホテルのベットの中で思いました。「いま上海蟹が旬らしいけど、明日は必ずラーメンを食べてやる」と。
翌朝、昨日と同じのバスに乗り込んだ一行は、一路、江蘇省の昆山市周庄へ。周庄は、いにしえの佇まいを残した水郷の町。柳川の川下りのような小さな船で水路を遊覧すると、両脇には、200年以上の歴史をもつ石造りの民家が延々と立ち並ぶ、明朝そのままの古い町です。この地の名物料理は、その名は忘れてしまいましたが、大きな豚肉の塊を醤油ダレで煮込んだ、いわば巨大な“角煮”のようなもの。ひょっとしたら、和・洋・中の料理が渾然一体となった長崎の郷土料理“卓袱料理”の中にある“角煮”も、ここ周庄が故郷ではないでしょうか。そんな思いをめぐらせながら、その豚肉を頬張ったところ、またもや八角の強烈な臭味。隣席の先輩は「ウマイ、ウマイ」としゃぶりついてますが、僕は炒飯ばかり食べていました。今日も麺類の食体験は期待できないようです。
その夜、上海に戻った一行は、「麺が食いたい、クイタイ」と、憑かれたようにつぶやく僕のココロを汲んでくれたらしく、今夜は「四川料理を食おう」ということになりました。「やった!四川料理といえば大好物の担担麺があるぢゃあないか」。とりあえず、“火鍋(ホウコウ)”という中国寄せ鍋をウリにしている近くの四川料理店へ直行。 まずは、ナベをつつきながらイッパイやって、最後の締めに担担麺を食らおう、ということになりました。出てきた鍋は、四川独特の赤みがかった辛口スープで、別盛りの皿から肉・魚介類・野菜をおもむろに煮立った鍋に放り込んで食べるところなど、まるで“日本の鍋”そのもの。しかし、なんとこの四川のスープにまで八角が幅を利かせていたのです。やはり担担麺も同じ味ということを聞き、ついに僕は観念し、決心しました。「この味も、立派な食文化のひとつ。これも試練、僕の人生の“味覚のインプット期”に漏れていた“八角の味”をいま、入力する時が来たのだ」と(要は“慣れればいいだけ”)。「いざ、食さん」とリキんでスープを口に運んだ途端、イキナリ僕の隣の客がケンカを始めました。店員と大声で怒鳴り合っています。僕はその横で八角と格闘してます。僕の連れたちは、日本人特有の“見て見ぬふり”で黙々と火鍋をつついています。地元の客たちは意に介さず、唾を飛ばさんばかりの会話の最中で、忙しそうに箸で皿をつついています。
やがて僕は、八角臭さと、辛さと、熱さと、騒がしさでTシャツ1枚になりました。異様的大飯店。なんだかこんな光景も、当たり前に感じてきました。・・・やはり、この大陸のフトコロは深い。
帰路、空港へ向かうバスの中、連れが中国の菓子をひとつくれました。ほおばると、八角をタップリまぶしたアメ。思わず吐き出してしまった僕は思いました。「イマダ八角ハ、未入力ナリ」「我最歓喜日本拉麺」。
帰国も、来たときと同じ中国某航空機に搭乗するとき、正面から見ると魚のような、何となくマヌケな顔のジャンボ機までが、僕を見て笑ってるような気がしました。
今回はこのあたりで、
再会(ツェーウェー)。
第十話 上海拉麺事情・上
2013年1月21日 月曜日 先日、上海に行って来ました。「なんだ、今度は上海かい。どーせ“麺の本場中国の味”とかなんとか言って、ウダウダと中国の食文化を批評しながら、祖国日本のラーメンにもアレコレ物申すってやつだろう」なんて声が聞こえてきそうです。めっそうもない。そんなつもりはありません。たかだかこの世に生を受けて40年そこそこの久留米のラーメン屋の倅が、ましてチョット覗いた程度のパック旅行で、4,000年の歴史を持つ国の食文化を論ずるなんぞ、10年、いや、3,960年早いってもんです。実際、旅行の滞在日が短すぎて、地元上海の料理の味をゆっくり堪能する暇もなく、いわば“匂いを一瞬嗅いで来た”に過ぎないのですが、僕なりに感じた“中国の匂い”その話に、少々おつき合いください。
11月20日出発。ある団体(と言っても旅行参加者はわずか7名)のお誘いで参加させていただいたものですが、僕にとっては初めての中国行きです。その日、最後まで一度も笑顔を見せてくれなかった中国某航空のスチュワーデスに別れを告げて、僕はあこがれの国に降り立ちました。「嗚呼中国。儂好上海。長い歴史のなかで、文化・民族あらゆる面で我が国と関係が深い大陸の国。そして、我が生業のラーメンの故郷中国に、僕はついに来たのだ。」空港出口で、そんな感慨にふけっている半ば放心状態の僕に、イキナリけたたましいクラクション。ここは歩行者の横断歩道、しかも信号は青、クラクションの主は信号無視の15年前のワーゲン・サンタナ。僕が慌てて横断歩道を渡ろうとすると、またもクラクション、今度は反対から来た信号無視の20年前のトヨタ・カローラが、僕の尻をかすめて走り去る。青信号を命がけで渡り終えた僕は、ふと思いました「この国には運転免許の制度など無いのかも知れない」と。でもこれも、“この大陸のフトコロの深さ”なのかも知れません。
やがて、我ら一行を迎えに来たのが、日本語が堪能な地元ガイドのお兄さん付きの、見たこともない中国製マイクロバス(やはり年代物)でした。このバス、当然の如く赤信号で出発。歩行者の波と自転車の渦も、これまた信号おかまいなしのスクランブル交差点、そこを縫うように、一人も跳ねず、一人も轢かずに見事に走り抜けます。
さらに、何気なくバスのスピードメーターを眺めてみると、なんとメーターの針は0を指して全く動いてません。驚いてガイドのお兄さんに訊くと、「このバスを手放すとき高く売れるように、メーターの接続を外して走行距離がカウントされないようにしている」とのこと。一行唖然。そのままバスは高速道路へ入り、スピードメーターは0のまま、次々と乗用車やトラックを追い抜いて、矢のように疾走しています。僕は、ふと思いました「このフトコロの深い大陸には、車検制度と交通法規は無いのかも知れない」と。ハタハタと破れたカーテンが風になびく車窓から外を眺めると、季節はずれの黄砂と見まごうほどの、濃いスモッグ越しに、上海の近代的高層ビル群が、排気ガスの雲海に浮かぶようにそびえ立っています。一行は、ガイドのお兄さんの挨拶や道中での注意事項など聞く余裕もなく、ただひたすらこの旅の無事を祈るばかりでした。
第九話 感謝感謝のラーメンフェスタ
2013年1月21日 月曜日 ついにやりました、やってしまいました、ラーメンフェスタ。
「産・学・官」が一体となったまちおこしとしては、久留米は無論、全国でも初めてのラーメンの大イベント 「ラーメン・フェスタin久留米」が、今月の6・7日久留米百年公園にて華々しく開催することができました。 おかげさまで大成功でした。
イベントステージでのアカデミックな「ラーメン学フォーラム」や楽しい「ラーメンクイズ」はもちろん大成功。 そして、ほとんどパニック状態と言うべき押し寄せる人の波また波で、よくぞ「さっさとラーメン食わせろ暴動」が 起きなかったと思わせるほど大盛況だった「ラーメン特設大テント」。200坪のテント内では、地元と全国各地から出店していただいた10店舗の、計1日限定5000杯のラーメンも 連日あっという間に完売しました。同時開催で大変お世話になった「農業祭」、ここの例年の人出が二日間で約7万人。今年は何と二倍、14万人もの来場者があったとか。有り難いことです、感謝してます。また、わざわざ来てくれたのに、フェスタのラーメンが食べれなかった約13万人の人たち、ゴメンナサイ。
さすがに、これだけの人が集まれば町全体への波及効果もすばらしいようで、このフェスタの期間中は、市内のラーメン屋さんも、おしなべて売上が上がったそうです。ちなみに僕のラーメン店の市内4店舗は、フェスタ初日、第一土曜としては過去最高の売上を記録しています。
この「フェスタ大成功」という明るいニュースは、久留米の不況ムードを一気に吹き飛ばしてくれたと思っています。「ラーメン」という、今が旬の食文化の活用は、まちの活性化に極めて効果的であるということが、今回、証明されたと言っても過言ではないでしょう。 いまさらながら、ラーメンの持つ凄まじいまでのパワーに、僕自身、圧倒されています。
久留米のラーメン町おこしは、いまスタートしたばかりです。 フェスタは来年、それ以降も続くでしょうし(たぶん)、今回のフェスタの成功を機に、 やがて久留米のまちに“ラーメンの殿堂的施設”が立ち並び、単なる“ラーメン観光のまち”を越えて、日本のみならず “アジアの麺類情報発信都市”となる日も夢ではないような気がします。最初のコラムにも書いたことですが、戦後の復興期、久留米のまちで力イッパイ働くオトーサンのお腹を満たしてくれたのが、 屋台で食べる一杯40円のとんこつラーメンでした。 そして現在の不況、必ずやとんこつラーメンは、二度久留米を救ってくれてるでしょう。
ところで「ラーメン特設大テント」での出来事。 先月このコラムで、フェスタの準備会議のとき、Mラーメンの社長さんが一言、 「(テント内で)先に売り切れたラーメン屋さんは、まだ残っているラーメン屋さんを手伝いましょうや。」 僕はこの言葉に感動した云々と書きました。 実際はどうだったかと言いますと、・・・やってくれました! 地元のラーメン屋さんどうし、次々と他店の呼び込みを始めたり、調理場へ入り込んで手伝ったり、 またホールでは、Dラーメンの部長さんとTラーメンの店長さんが ゛肩を並べて″お客さんの案内をしたり、 ・・・歴史的な日でした。 きのうまでの商売敵が、いま同じ屋根の下で、同じ汗をかき、数千人のお客さんに揉まれながら、奪い合うことなく、罵り合うことなく、ただ譲り合って、助け合う。久留米商人の典型と揶揄されていたラーメン業界が、この瞬間に生まれ変わった気がしました。
最後に、フェスタに来てくれたお客さんとフェスタの関係者、それを支援してくれた人たち、そして、僕たちラーメン屋を育んでいただいた地元のすべての人たちと、こんなバカ息子に「ラーメン」という素晴らしい財産を 残してくれた、今は亡き父に、感謝しています。
第八話 ラーメンフェスタ in 久留米
2013年1月21日 月曜日 今回は、ワタクシ「久留米・ラーメンルネッサンス委員会」の一メンバーとして、ちょっとばかりPRをさせて下さい。
さて皆さまお待ちかね、世紀の大ラーメンイベント「ラーメンフェスタin久留米」が、今月11月6日(土)~7日(日)の2日間、久留米百年公園において大々的に開催されます。初日のイベントステージでは、「ラーメン学フォーラム」と銘打ってとんこつラーメンの栄養学や歴史的検証、麺文化についての専門家の講話など、ちょっとおカタいハナシのあとに華々しく「とんこつラーメン発祥の地宣言」を全国にアピールするという企画が予定されてます。二日目のステージは、初日とはうって変わって「クイズ・とんこつラーメン王選手権」やら「とんこつラーメン早食い競争」など楽しい企画が盛り沢山。いやが上にもお祭りムードは盛り上がるでしょう。 そしてフェスタの最大の目玉、200坪の「ラーメン大テント」では、北海道の旭川、東北の郡山そして関東から、それぞれ地元を代表する有名ラーメン店が出店。また地元の久留米とんこつラーメン会から7店、計10店の蒼々たるラーメン屋さんが一同に会して皆さまをお待ちしています。ラーメンは、1日限定5000杯ではありますが、地元各店のとんこつラーメンのみならず、全国各地のラーメンを一カ所で食べ比べることができるのも、このイベントのウレシイ特徴であります。全国に例のない、この大ラーメンイベント。これがきっかけとなって久留米のまちが少しでも元気になってくれたらいいなと思っています。
余談ですが、久留米・ラーメンルネッサンス委員会とほぼ時を同じくして発足しました「久留米とんこつラーメン会(地元ラーメン店31店舗で構成)」の会合が先日ありました。その日の主な議題は、目前に迫ったラーメンフェスタの大テント内ラーメン店出店に関するものでしたが、会議も終盤に近づいてきた頃、もと久留米市内で開業されていて、現在基山の三号線沿いにあるMラーメン(ここまで言えば誰だってワカる)の社長さんが一言。「(テント内で)売り切れたラーメン屋さんは、そのまま帰るんじゃなくて、まだ残っているラーメン屋さんを手伝いましょうや。」・・・・・ 感動しました。一般の人にはこの感動は理解できないかも知れません。他の業界の会合ならこれぐらいの提案は当たり前のことでしょう。大変失礼ながら、以前このコラムで、久留米のラーメン業界の体質を「一匹狼的で同業者間の協調性に欠ける云々」と書いたことがあります。実際、このラーメン会も発足後2度ほど総会はありましたが、活発な意見も出ず、なんとなく互いが警戒しあっている雰囲気でした。
しかし、今回の会合ではフェスタへの協力という「一つの目的」を共有できたことが良かったのでしょう、しだいに意見が出始め、やがて、今までシカメッツラだった皆さんのその顔に自然な笑みと時折笑いまで出るようになりました。そして前述のMラーメンの社長の一言です。この言葉を聞いた瞬間、僕はフェスタの成功を確信しました。歴史的な日です。
「久留米商人が歩いたあとは草も生えん」と誰も言わなくなる日は、もうすぐそこまで来ています。
第七話 手前味噌ラーメン
2013年1月21日 月曜日 今回も引き続き「味」ついて恐縮ながらもうひと講釈。
かつて久留米育ちのラーメン好きのお客さんたちからよく耳にしていのが「東京でラーメンば食べてみたばってん、アラなんや、スープは真っ黒でマズくて食えん」。また逆に、初めて九州の豚骨ラーメンを食べた東京出身者のほとんどは「クサくて食べれない」と言われてました。まさにこの人たちは、自分が育った地域で親しんだラーメン以外は受け入れられない“ふるさとのラーメンによる呪縛状態”とでもいいますか・・・。
さて、「手前味噌」という言葉があります。その昔、ほとんどの家庭で味噌は自家製でした。無論、生まれ育った我が家の味噌の味は一生忘れられない故郷の味です。当然、「我が家の味噌が一番ウマい」と人に自慢したくもなります(実際人間の味覚は、幼年期から思春期前までに体験的に形成されてしまうそうで、これを僕は“味覚のインプット期”とよんでいます)。このように今では、「手前味噌」という言葉は“自分の自慢話”の前に添える慣用句になったそうです。現代、ほとんどの家庭の味噌は“近くのスーパーで買ってくる地元メーカーの味噌”にとって代わりましたが、「手前味噌」は“家庭”から“地域”へとその単位をかえて、今なお各地方に根付いているようです。
余談ですが、僕が学生時代、バイト先の定食屋のマスターが、本人曰く「日本一ウマい」という味噌を、わざわざ東北の仙台から取り寄せて僕に分けてくれました。僕は喜び勇んで早速下宿に持ち帰って「日本一の味噌汁」を作ってみたところ、これがまたショッパイ、しょっぱい。まるで塩水。塩分濃度が高いのでしょう。しからば、いつも使ってる地元九州の味噌の半分の量にして再度挑戦したところ、今度はしょっぱさはいいが味噌の風味とコクがない。世話になったマスターからせっかく頂いたものなので処分する訳にもいかず、結局、九州の味噌に少しづつ混ぜながら使っていたという思い出があります。ちなみに、面倒見のいい江戸っ子のマスターから頂いた「日本一の味噌」をやっとの思いでを食べ尽くしかけた頃、またもウッカリ頂いてしまった「日本一の醤油」 ・・・・これも同じ結果でした。いや、決してこれらがマズかったということではありません。ただ僕の「好み」に合わなかっただけで、ゴカイのないように。「手前味噌」と「お国自慢」、食の世界でも同意語のようです。
日本人の“味覚のインプット期”に最も影響を与える調味料が「味噌・醤油」なら、「料理」というカテゴリーでみると、それはやはり「ラーメン」でしょう。いろいろな地方の人たちが集まる席で、それぞれの「お国自慢」に花が咲くとき、よく出る話題は「ラーメン」。酒が進むごとにその話題は熱を帯びて・・・
~とある居酒屋。全国各地から集まった6人の男女がラーメン談義をしている~
京子: 「東京のしょうゆラーメンが一番です。」
熊男: 「そぎゃんこつなか。 ホー、ニンニクたっぷりで ホー、スタミナんつく熊本ラーメンがウマかっどー、ホー。」
博太: 「フクロウか?きさん、博多んラーメンのほうがメジャーじぇ。」
久雄: 「なんば言いよっとかお前たちゃ、久留米が九州ラーメンのルーツちゃ知らんめー?」
京子: 「東京のしょうゆラーメンが一番です」
久雄: 「まーだ言いよっとかお前は、いまは九州ラーメンのハナシやろうが。」
雪子: 「やっぱ北海道の旭川ラーメンがおいしいっしょー」
博太: 「いつ来たとや、きさん。あっち行きやい」
隆盛: 「おはんたち喧嘩はこんぐらいにしモッそ。ここはひとつ、かごんま(鹿児島)んラーメンが一番ということで日本国はまとまりモッそ。」
博太: 「幕末や?きさん、帰りやい。」
隆盛: 「幕臣のおはんらとはサラバでごわす。薩摩は再び鎖国しモッそ。」
京子: 「東京のしょうゆラーメンが一番です。」
久雄: 「たいがいにせんかお前たちゃー。」
雪子: 「旭川ラーメンがおいしいっしょー」
~やがて、ワケのわからないこの会は、一段と収拾がつかなくなってゆく~
と、まあこんなシチュエーション(当然フィクションです)でしょうか。最近、全国的な“ご当地ラーメンブーム”とやらの影響で、僕の店でも、情報誌などを片手に“クサイ”豚骨ラーメンをおいしそうに食べられている関西や関東からのお客さんたちが増えました。これは一見、ラーメンを食べる人たちの“ふるさとのラーメンによる呪縛状態”が、緩やかになってきたようにみえますが、さにあらず。この現象は、マスコミを中心とした“ラーメン仕掛け人たち”による「暗示」現象でしょう。マスコミが“行列のできる店”とか“ラーメンのチャンピオン”とかはやしたれれば、暗示された人たちにとっては「クサくて食べれない」ラーメンも「おいしいラーメン」にバケてしまうのです。そんな暗示はすぐに解けてしまいますし、その人に長年蓄積された“味覚のインプット”にはかないません。そしてラーメン観光の旅から帰った人たちは、まっ先に「ふるさとのラーメン」に舌鼓を打ちながらつぶやくことでしょう。
「やっぱりこのラーメンが日本一」と。
第六話 プロのコツ“味の決め手”
2013年1月21日 月曜日 今回は、ラーメン屋のワタクシが皆様にプロのコツをお教えしましょう。さあ、これさえ読めばアナタもラーメン屋になれる(かも)。
さて、まずは調理のコツから。(各ラーメン屋さんで若干の違いがあると思いますが)。
最初に、充分に沸騰したタップリのお湯に、麺をよくほぐしながら入れます。次に、ラーメン丼にタレを少々入れます。このタレは「元ダレ」や「塩タレ」または「バカタレ」(これはウソ)など各ラーメン屋さんで呼び名が違うようです。ちなみにウチの店では「ラーメンしょうゆ」といってます。このタレには、塩と醤油そしてその店独自の各種調味料が絶妙なバランスでブレンドされています。このタレこそが、その店の味の個性そのものが濃縮された、いわゆる「秘伝のタレ」と呼ばれるものであります。釜のスープは味付けされてませんので、丼にそそぐタレのサジ加減ひとつで一杯のラーメンが濃い味にも薄味にもなります。次にラードを少々加えた後、豚骨ラーメン独特の強火で激しく沸騰・白濁させた大釜のスープを網で漉しながら丼にそそぎます。あとは、茹であがった麺を良く水切りして静かに丼に入れ、最後に新鮮な刻みネギ・スライスしたチャーシューなどをトッピングすれば、さあ出来上がり。ザッとこんなもんです。
さて、これからお話するのがプロのコツ。僕の店はオープンキッチンなので注文されたお客さんの姿を見ることができます。僕の場合、注文伝票が入ったら必ずお客さんの姿を見てから味付けを決めています。女性の場合、一般的に脂と塩分の取り過ぎを嫌われるので、タレとラードは少なめにした「あっさり・薄味」がよろこばれるようです。逆に男性の場合、特に汗をかく肉体労働関係の方や体育会系の学生さんに対してはタレとラードはやや多めにいれて「こってり・濃い味」にしています。この味付けはお酒を飲んだ帰りのお客さんにも合うようです。の嗜好に応えているからでしょう。また、お年寄りには、やはり「あっさり・薄味」にして、なおかつ麺を柔らかく茹でて歯になるべく負担がかからないように心がけています。これら様々な味付けも、夏と冬では微妙に違ってきます。もうお解りでしょう、たくさん汗をかく真夏に無意識に体が求めるは当然塩分ですね。ですから同じ「薄味」でも季節や天候によって若干の変化をもたせています。これら全ての状況把握と味付けの判断は、お客さんから一枚の注文伝票が来た途端、一瞬の内にこなさなければ、忙しいピークタイムには対応できません。しかし、人間には必ず味の個人差というものがあるということで、最近僕の店では、お客さんのご希望があればご注文の際にお好みの味や麺のかたさをお訊きするようになってしまいました。But・バッテン・ところがどっこい、長年ラーメン屋をやってると、初めての来られたお客さんでも、そのお客さんの顔を見れば「味の個人的な好み」も霊感的に見えてくるのであります。コレホント。
色々ゴタクをならべましたが、「うまい味」というものは、まず「質の良い食材」と「すぐれたレシピ」そして「相手が好む味付け」これらが三位一体となって醸し出されるものと思っています。
あ、ひとつ一番大切なものを忘れてました。それは、“おいしく食べてもらいたい”と願う作り手の「想い」という名の調味料。これを最後に“ひとふり”、これが味の決め手です。
第五話 北海道ラーメン行脚・下
2013年1月21日 月曜日 目前に現れたのは、古びた赤提灯のたもとから吹き出す煙と、お世辞にもキレイとは言い難い店。おびただしい炭焼きの煙は、店全体を包みながら漆黒の北の夜空に立ち昇っています。誰もいない寂しい街角に、そこだけ生物反応を感じる異様な風景。屋号は「鳥源」、なぜか同じような入り口が二つ並んでいて、右の扉の横には屋号看板と同じ位の大きな字で「勝手口」と書かれています。「なんと親切な店だろう」僕は迷うことなく左の扉から突入しました。そして店に入ってビックリ。100席近い客席を埋め尽くす老若男女のお客さんたち。焼き場には、数千本はあろうかと思われる串打ちされた焼き鳥の山と、それを無造作につかみとっては炭火の上に並べるイキのいい二人のお兄さん。コの字型二連の炭焼台から勢いよく立ち上がる煙。焼き場の熱気と客席の活気に僕は圧倒されました。「何だ、繁盛してる焼き鳥屋なんか探せばどこにでもあるじゃないか」と読者諸氏はお思いでしょう。さにあらず、最後まで読んでいただきたい。
運良く焼き場正面のカウンターに座ることができ、メニューを見ると、焼き鳥は鳥皮と鳥身(ヤッパリ)のみ。あとは飲み物と、なぜか「そば」だけ。僕はとりあえず「ビール」ではなく「焼酎」と焼き鳥を数本注文して、焼き場のお兄さんたちのテキパキとした仕事振りを眺めていました。すると僕の横の扉から、入って来るわ入って来るわ、ひっきりなしのお客さん。ここは福岡・天神のど真ん中でもないし、まして平日の木曜日。いったいその人たちはこのゴーストタウンのような町のどこから涌いてくるのか?ベトコン兵のごとく何処からともなく突然現れるお客さんたちを見ながら僕は思いました。「この焼き鳥屋はタダモノではない」。
それを裏付けてくれたのが、まずは当然ながら焼き鳥の「味」。冷凍モノでないことは言うに及ばず、よほど素材を吟味しているのでしょう、口の中でジワリとにじみ出るアツアツの肉汁のうま味は逸品。北海道には珍しく「塩焼き」を薦めるのもうなずけます。
そして極めつけは、やっぱり焼き場の元気なお兄さんたち。特にぼくの目の前の“若い頃の三島由紀夫”ソックリのお兄さんたるや、焼き鳥を焼く手を休めることなく、来る人・帰る人全てのお客さんに対し、爽やかな挨拶に加えて、必ず一言そのお客さんガラミのイキな世間話をしています。その上すべてのお客さんの名を記憶してるようです。少ない常連客だけのうらぶれた飲み屋ならいざ知らず、都会の大型繁盛店なみの客数がありながらこの細やかな接客はスゴイ。僕が何気なく三島由紀夫兄さんに「九州から来たとばってん、近くにイワナの釣れる川はなかね?」と訊ねると、お兄さんは焼き串を返しながらイキナリ大声で奥のお客さんに向かって、「○○さーん、チョットこっち来てー九州の人に釣り場を教えてー、穴場知ってるっしょー」。
すると店の奥から、ヨッパライたちをかき分けながらヨッパライおじさんがフラリと現れました。おじさんは僕が広げた地図を見るなり、「ここ!釣れるヨ。ア・ナ・バ。」そして両手を一杯に広げて、「こーんなアメ(アメマス:イワナの一種)がウヨウヨ。川に入ると足にぶつかるっしょー。」と、信じがたい情報をあっさり教えてくれました。僕が早速 明日その穴場に行かせていただく旨と深い感謝を伝えると、そのおじさんはまたフラリと去って行きました。
何もかもがタダモノではない町。僕の中では、そのチャンピオンは、やはり三島由紀夫兄さんでした。焼き鳥屋に限らず、ラーメン屋も含めてあらゆる食べ物屋が経済繁栄だけを求めて企業化・システム化しているこの時代に、失われかけていた「人をもてなす心」という最も大切な「商売の基本」をこのお兄さんは僕に思い出させてくれました。
今回の北海道ラーメン行脚の旅で、僕にとって最大の収穫の場は全国に名だたるラーメン屋ではなく、小さな町の焼鳥屋でした。
翌日、巨大アメマスへの期待に胸躍らせておじさんが教えてくれた穴場へ直行。しかし、足にぶつかる魚体はおろか、一日中竿の穂先に何の反応もなく久々のボーズで北海道の旅は幕を閉じました。
やはり、北の大地はタダモノではない。
第四話 北海道ラーメン行脚・上
2013年1月21日 月曜日 先日、北海道の旭川へ出張してきました。「ナニ?久留米のラーメン屋のオヤジが北海道に何の仕事があっとか?」と言われそうですが、そりゃ、とりあえずルアーとフライ(釣り道具)をバックに忍ばせては行きましたが・・・、何をかくそう「久留米・ラーメンルネッサンス委員会としての表敬訪問」と「旭川ラーメンの調査・研究」という目的を持ったリッパな“出張”であります。もちろん滞在中の朝食以外の食事はすべて“旭川ラーメン”。当然、朝早くから開いてる店があれば“一日三食ラーメン状態”。まるで先月このコラムで僕が書いた“個人的取材に励むラーメンオタク”そのもの(撮影は許可を得てます)になり果てながら、キチンと“仕事”をこなしてきたのでありました。またその間、地域の食文化を知る上で最も大切な“地元の酒と肴の調査・研究”も決して怠ってません。
その町は、旭川から50km程北に位置する小さな田舎町でした。その日もいつものように夕食(当然ラーメン)を終えた僕は、おもむろに店のオヤジさんに尋ねてみました。「こん近くに地元のウマかもんば食わしてくるっ居酒屋んごたっとこはなかね?」すると、今までただ黙々と仕事をしていた不愛想なオヤジさんが「お客さん九州の人っしょー」。なぜ僕が九州の人間だとわかったのか?、このタダモノではないオヤジさんは続けて、「焼き鳥、ヤ・キ・ト・リ。あの国道を渡ってスグ。そう、ヤキトリ屋、この町一番の繁盛店っしょー」。なんで北海道まで来て焼き鳥なんだ、焼き鳥文化は九州のレベルが一番高いのを知らないのか? メニューはどうせ鶏身と皮のタレ焼きぐらいしかないんだろう。などと内心とても失礼なことを思ってしまいましたが、オヤジさんがあまりに熱心に薦めるので、とりあえず行ってみることにしました。
するとこのオヤジさん、一段と機嫌が良くなり、僕がラーメン屋ということを知ってか知らないでか、聞かれもしないのに旭川ラーメンの作り方を懇切丁寧に教えてくれました。やはりタダモノではなかったオヤジさんにしみじみとお礼を言って店を出ると、外はいつしか陽が落ち、閑散とした町は夕闇に包まれて、道行く人の途絶えた通りは、北国独特の寂しさの底に沈んでいました。うら悲しい旅情を感じながら、詩人の僕は思わずつぶやく。 「こげんだーいもさるきよらん町で、そん焼き鳥屋は商売できとっとやろか?」どこにも車がいない国道の交差点をとぼとぼ渡って裏道に入ってみると、益々道は暗くなり人っ子独りいません。まるで西部劇のゴーストタウン、とても店などあるような雰囲気ではありません。不安な気持ちのまま歩き続けていると、何やらポツンと赤い灯が見えてきました。「もしかしてアレ?」まるで“怪談のっぺらぼう”に出てくるそば屋の赤提灯にそっくり。 僕の「不安」は「恐怖」へと移行してしまいそうでしたが、とにかく勇気を振り絞って赤提灯めがけて突撃しました。 それは、以外な結末に・・・。
第三話 目覚めよラーメンフリーク
2013年1月21日 月曜日 ここ数年、新聞のテレビ番組欄を見ても、書店の雑誌コーナーに行っても「ラーメン」の文字を見ない日はありません。この全国的なラーメンブームとその情報の氾濫はいつまで続くのでしょうか。最近特に「ご当地ラーメン」ブームが加わり、一段と拍車がかかった観もあります。
先日、インターネットで「ラーメン」を検索してみました。すると、あるわあるわ、ラーメンフリークと呼ばれる(いわゆるオタク)たちのホームページが。勝手なラーメンランキングやら、もう言いたい放題、書きたい放題の投稿コーナーやら。僕も何気なく、ランキングに自分の店の名を見つけては喜んだり、投稿記事の内容に一喜一憂したりして、結構楽しんでいました。思わず想像してしまったのは、ラーメン情報のホームページの開設者の取材風景です。おそらく、一般のお客さんにまぎれて苦労しながら秘密の取材をしているのでしょう(一言いってくれたら気持ちよく協力するのに)。たぶん、出されたラーメンをデジタルカメラでこっそり撮ったら、やおら自作のチェック表を取り出すと、一口スープを啜っては採点をし、一口麺を噛んでは採点をし、それと同時に卓上の薬味や調味料の種類、メニューの数と売価なども記録していることでしょう。とてもラーメンをゆっくり味あうヒマなどありません。ウマいラーメンもマズくなります。
そんな他愛ない想像なんかしながら、ラーメン情報のホームページを眺めていたある日、ある投稿コーナーに、僕も知っているラーメン屋さんの名を見つけました。それは、集中的にそのラーメン屋さんに向けられた、無責任な誹謗中傷の投稿文でした。それを読んだ途端、その投稿者たちに対し、何とも言えない感情、「嫌悪感」というより「寂しさ」を感じました。「店を活かすも殺すも、この人たちのキーボード次第」というところでしょうか。パソコンなんぞにはとんと縁のないラーメン屋のオヤジさんたちが、自分の息子と同じ世代の、それもインスタントラーメン以外作ったことのない若者たちから、知らないうちに吊し上げられてしまう時代。そして、この上もなく便利だけれど、この上もなく野放しで無秩序なデジタル情報の世界に、いま強い危機感を感じています。
しかし、久留米のラーメン屋のオヤジさんたちよご安心あれ!我々「久留米・ラーメンルネッサンス委員会」が募集した「ラーメン探偵団」は自らの足でラーメン屋さんを廻り、キチンと挨拶をして、正々堂々と取材をさせていただくアナログ集団です。この取材の基本姿勢は当然、“ランク付けなし”“勝手な主観なし”そして“一切の批判なし”であります。オヤジさんの“思い”、存分にぶつけて下され。取材目的はただ一つ、観光客向けの「久留米・ラーメンマップ」づくりであります。