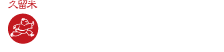平成11に始めて開催された「ラーメンフェスタ in 久留米」も、平成18年第8回を最後に、休止となりました。そしてそれを引き継ぐように、翌年から(全国)B-1グランプリが久留米で開催され、以降、「九州B-1グランプリ」という企画で、毎年九州中のご当地B級グルメがこのまちに一同に会し、食の祭典が賑やかに催されています。その運営ノウハウは、ラーメンフェスタで培われたものと言っても過言ではありません。さて、それではラーメンフェスタの運営母体であった「久留米・ラーメンルネッサンス委員会」は消滅したのか?・・・否、ちゃんと存在しているのです。地下に潜ったレジスタンスのように、この4年間、地味ながらも次なるステップへの準備を進めて参りました。それは、来年3月の九州新幹線久留米駅開業に向けての「駅前のラーメンモニュメント」の設置と、九州ラーメンの元祖「南京千両」さんの最初の開業の地(何と文化街入口の甘栗屋さんの前)に、九州ラーメン発祥の記念碑を建てるという活動でした。本来委員会は、「ラーメンフェスタ」という、打ち上げ花火的な催しと平行して「後世に残るモニュメントの設置」という、二本柱の目的を持った組織でありました。しかし委員会メンバーは、毎年実施されるラーメンフェスタの企画・運営にほとんどエネルギーを使い切ってしまい、なかなか忍耐と根気の要るモニュメントの設置活動には手つかずの状態でした。そこで、思い切ってラーメンフェスタを休止して仕切り直しをしたのです。そしてついに今年、新久留米駅東口のラーメンモニュメントと、明治通りの九州ラーメン発祥の記念碑設置の認可が降りたのです。そこで市民の皆様にお願いがあります。これらのモニュメントは、企業などの協賛ではなく、賛同される皆様からの「募金」で建てられたものとしたいのです(募金箱は市内各所のラーメン店に依頼中)。これが成就すれば、今までのように「九州ラーメン発祥の久留米」を楽しみに来た来訪者が久留米駅に降り立ち、「どこがラーメンのまちなの?」と、がっかりさせることも無くなるでしょう。ご理解とご協力をお願いいたします。
‘ラーメン今昔物語’ カテゴリーのアーカイブ
第百三十二話 駅前にラーメンモニュメントを
2013年4月18日 木曜日第百三十一話 奇跡のコラボラーメン
2013年4月18日 木曜日 ラーメンバカチンクラブ、略してRBCという会があります。それは「もっとラーメン文化を盛り上げよう」という、志を持った全国の有名ラーメン店主たち18名で構成された組織であります。去る8月7日、そのRBCのメンバーが一堂に介してイベントを開催しました。場所は東京・銀座、イベント内容は、ラーメンをメインとしたフルコースの中の一品を、それぞれの店主たちが創作して腕を競うというものでした。そこで僕が担当したのがメインディッシュのラーメン二品の内の一品でした。さらにその作品は、僕ともう1人、久留米でラーメン店を営む「龍の家」の梶原社長とのコラボによるもの!これは地元のラーメンフリークならずとも「え?龍の家と大砲が手を組んだ?」と、驚愕のニュースではないでしょうか(自意識過剰?)。というのも、RBCの会議の場で、梶原社長が僕と組みたいと言ってくれたのが、今回のコラボの発端でした。いや?、それは嬉しかったですね。そこで気を良くした僕は、長年温めていた創作ラーメンを、梶原社長に提案しました。梶原社長はその提案を即座に受け入れてくれ、そこで2ヶ月に及ぶ龍の家・大砲による創作ラーメンの開発がスタートしたのです。やがて試行錯誤を繰り返し、本番直前にようやく完成した作品が、題して「常夏のグリーンサンセットラーメン」。南の海に沈む夕日をイメージしたラーメンです。そして本番、会場を埋め尽くす審査のお客様。その手にはそれぞれの作品に点数を着ける採点票。全ての料理の提供が終わると、審査結果の発表です。僕も梶原社長の「ビリじゃなければいいか」なんて考えていました。そしてMCによる場内アナウンスが始まりました。「最優秀賞を発表します・・・。作品名「常夏のグリーンサンセットラーメン」。僕たちはしばし沈黙・・。やがて我に返ると2人で抱き合っていたのです。感動しました。九州の片田舎のラーメン店が、花の東京・銀座の檜舞台で勝利したのです。57年前に1軒の小さなラーメン屋台を始め、13年前に他界した僕のオヤジは、草葉の陰でこんな息子をどう思っているでしょうか。
実はこのラーメン、更に改良を加え、10月1日から11日までの期間限定で龍の家上津店(土日祝のみ)、大砲ラーメン合川店(平日のみ)で、販売いたします。売り切れの場合はご容赦下さい。最後に、この作品の完成に尽力してくれた、梶原社長と、その若いスタッフ心より感謝いたします。
第百三十話 炎天下の行列
2013年4月18日 木曜日 この夏も、記録的な猛暑の夏でした。お盆の間も、夕立も降らない酷暑の日々が続きましたが、にもかかわらず、久留米に帰省したお客様は、今年も僕の店の前に長い行列をつくって下さいました。有り難い限りです。せめて外にお並びのお客様には、冷茶やかき氷のサービスくらいしか僕たちにはできませんが、炎天下で何十分も並び、さらに熱いラーメンを食べていただけるということは、僕たちはラーメン屋冥利に尽きます。感謝の極みです。
そして、そんなお客様をお迎えして、これまた熱い釜の前で、一杯一杯心を込めてラーメンを作る社員、ホールを駆け回るパート・アルバイトさん、本当にありがとうございます。
また、僕たちがこだわる良質の食材を厳選して届けてくれる業者さんや、その他全ての協力会社の誠意に、いつも感謝しています。
これらのことを、経営者である僕が「当たり前」などと思えば、お天道様の罰が当たり、商売する資格すら無くなるでしょう。
そんな思いを改めて心に刻み込んだ、今年の夏でした。
第百二十九話 結婚披露宴
2013年4月18日 木曜日 僕ももうこの年になると、よく結婚披露宴で挨拶を依頼されます。それは僕の会社の若い社員や、取引先、知人などの披露宴で、多いときは年に7~8回ということもあります。そんな披露宴での僕の挨拶は、すべてアドリブで、メモに頼ったことはありません。新郎新婦の顔を見て、そのときその場で思いついたことを面白おかしくしゃべって、挨拶に代えさせていただいています。しかし、アドリブがゆえに思わぬことを言ってしまい、後になって反省することも多々あります。
それは、最近よくある「できちゃった結婚」というケースの披露宴でのこと。そもそも僕は、その「できちゃった結婚」というものが嫌いです。そんな気持ちのまま挨拶したものだから、知らずに「え~新郎の○○君、そして妊婦の○○さん」と、「新婦」と「妊婦」を間違えてしまいました。でも2人の内情を知る一部の友人たちからウケたので、僕はあえて訂正することなく、親族の心情を察することも忘れて挨拶を続けました。その披露宴もめでたく終わりました。しかしあとで聞いたことですが、そのときの妊婦、いや新婦のお父さんは、そのスジの親分さんだったとのことでした(お陰様で後難はありませんでした)。
また、もうひとつの結婚披露宴は、「できちゃった結婚」どころか「できちゃって生まれちゃった結婚」でした。その子供は1~2才くらいの女の子でした。そのときも挨拶で僕は言ってしまいました。「私はできちゃった結婚が大嫌いです。ところがこれは、できちゃって、すでに生まれちゃった結婚。更に嫌いです。シカシナガラ、その女の子はカワイイ。しかも愛子内親王殿下にそっくり。従ってこの結婚は特別に認めます」これはウケました。満場の拍手でした。
最後に、僕が実験的な挨拶を試みたときの披露宴。そのとき僕は、最後の万歳三唱の役でした。宴もクライマックスとなり、新婦の涙の手紙、新婦の父の感無量の言葉。涙で声にならない新郎の挨拶・・・。会場は感動でしんと静まり、すすり泣きさえ聞こえます。そんな中で、「最後の万歳三唱のご挨拶を」と、僕の名が呼ばれました。そのとき僕は、涙なみだの披露宴を、最後くらいは笑いで終わらせようと、万歳三唱前の挨拶でこんなことを言ってしまいました。「新郎新婦のお2人に大切な言葉を贈ります」静寂の会場、人々は僕の次の言葉に聞き耳を立てています。一呼吸おいて僕は続けました「その大切は言葉とは・・・・・『おっぱい』・・・」思わずお笑い芸人の「小ボケ先生」のネタをやってしまったのです。会場は一瞬静寂。親族は目が点。やがて一部の若い男性たちから爆笑が起こりましたが、それだけでした。「小ボケ先生」はあまりメジャーではありませんでした。ましてそのネタを、最もふさわしくないところで使ってしまいました。それでも僕は気を取り直して、作法通りに万歳を三唱して降壇しました。
第百二十八話 ジャズとラーメン
2013年4月18日 木曜日 僕のラーメン店では、二十年ほど前からBGMにジャズを流しています。今でこそ居酒屋から、はては寿司屋までジャズを流すお店が出てきていますが、二十年前ジャズのBGMを流す店といえば、それこそジャズ喫茶かショットバーくらいでした。ですから当時はよくお客さんから「何でラーメン屋にジャズなの?」という質問を受け、僕はこう答えていました。「たとえば、クラシックは白人の王侯貴族に雇われた音楽家が、王侯貴族のために創った音楽。一方ジャズは、かつてのアメリカ南部で人種差別と貧しさに生きるアフリカ系アメリカ人(黒人)たちの中から自然発生した、自分たちの魂の音楽です。僕のラーメン屋も、元々は戦後の貧しい一軒の屋台から始まりました。ラーメンそのものも、いわば社会の底辺から生まれたものです。音楽にたとえるならば、やはりその生い立ちがジャズに近いものを感じて、BGMをジャズにしました」と、まあこのような説明をしていました。そして最近ある本で、一般的な飲食店のBGMはどのような音楽がふさわしいのか?というタイトルの記事を読んだのですが、飲食をするお客さんが、食事や会話に耳障りを感じないのがやはりジャズでした(静かなインストゥルメンタル・ジャズ)。要するに、高級レストランは別として、クラシックはかしこまりすぎるし、歌謡曲やポップスは、それぞれの曲調がバラバラなので、お客さんのテンションとの差が生じ、曲によっては不快感を与えるということでした。これを読んだ僕は「うん、自分は間違っとらんやった」と、ほくそえんでしまいました。しかしながら僕がさらに思うのは、何でもかんでもどんな店にもジャズを流せばよいというものでもありません。やはりそのお店の意匠・環境・空間というトータルなコンセプトがきちんとしていなければ、ジャズのBGMを流しても、それは浮いたものになるでしょう。
今回はジャズの話を偉そうに書いてしまいましたが、実は・・・、僕はジャズ愛好家でも何でもなく、僕が好きなのは七十年代のアメリカンロックなのでした(苦笑い)。
第百二十七話 星になったラーメン店主
2013年4月18日 木曜日 僕の友人でもあるラーメン店主がきのう亡くなりました。それは5月のさわやかな雨上がりの夕暮れ時でした。今回、49歳という若さで逝ったそのラーメン店主の話を少々させて下さい。
生前の彼は冗談好きな飄々とした男でしたが、ラーメンに対する思いはなかなか熱いものがありました。10年ほど前に宅配ピザの店を人に譲り、一念発起でラーメン屋を始めてから以降、ことあるごとに、ラーメンに関するアドバイスを僕に求めました。たとえば「豚骨の部位はどこが一番スープが出るとね?」と訊かれると、僕は「そりゃ、呼び戻しスープなら、全部の部位がよか。まず、一番もろい脊髄からダシが出て、次にバラ、そしてアタマ。最後にゲンコツ(大腿骨)が自然に壊れてダシが出る。間違ってもゲンコツは割って入れたらでけんばい。一気にいいダシが出てしまうけんね。割って入れるのは取りきりスープのやり方ばい」と、まあこんな具合ですか。また、彼はラーメン店の経営のやり方も一風変わったところがありました。突然、三潴や大川を中心に同じ屋号の店を、何店舗か一気に出店し、それらの店が軌道に乗ったかと思うと、次々と屋号ごと弟子に安く売ってしまったのです。そして自分は柳川に別の屋号の店を出し、その1つの店に収まってしまいました。本当に奇抜な男でした。趣味と言えば「酒」。とにかく無類の酒好きで、僕が朝起きて携帯を見ると、深夜2時や3時の彼からの着信記録が幾度となくありました。恐らくどこかの飲み屋あたりでラーメン談義に盛り上がり、その勢いで僕を誘いだそうとしたのでしょう。結局、その酒が祟ってこのようになってしまったのですが、彼にとっては、それも本望なのかも知れません。
しかし彼は、幾ばくもない自分の余命を知りながらも、やはりラーメンへの思いは最後まで衰えず、取引のある僕の麺工房の部長を入院中の病院まで呼んで、新作の麺の打ち合わせをしていました。それも常に冗談交じりで…。僕にはこのようなまねはできないでしょう。恐るべきラーメン魂です。
そんな彼の死は僕の心に悲しみの風穴を空けてしまいました。しかし、彼がラーメン屋として生きた足跡は何かのかたちで記録しておきたいと思い、冥福を祈ると共に今回のコラムで彼の話を書かせていただきました。
先ほど聞いたことですが、去年嫁いだ彼のひとり娘が、先月男の子を産んだということでした。星になった彼は、これからはその孫の成長を空の彼方から見守り続けるでしょう。
第百二十六話 九死に一生
2013年4月18日 木曜日 テレビの特番で、よく「衝撃の映像」なるものをやってますが、そのほとんどが事故や災害に巻き込まれた人間が奇跡的に助かるという、いわゆる「九死に一生モノ」の映像で、「それでよく助かったな」と見ていて驚かせられます。かく言う僕も、その奇跡的に助かったという「九死に一生体験」の持ち主であります。それはン十年前の、僕が二十歳ちょっと過ぎの頃のことです。その頃僕は渓流釣りを始めたばかりで、その面白さにハマり込み、寝ても覚めても、渓流の女王「ヤマメ」のことで頭が一杯でした。そんなある日、僕は弟と2人で、熊本の緑川上流のある支流に釣行しました。山中の未舗装の狭い林道を四駆を揺らせながら走っていると、突然大きな崖崩れの跡が林道を遮っていました。前日の大雨で山の斜面が崩れたのでしょう。それは眼下遙かに谷の底まで達しています。当然車はそこでストップを余儀なくされ、徒歩でこのガレ場(崖崩れ跡)を越えるしかありません。目指す絶好の釣り場はこのすぐ先の谷です。僕たちは「早くヤマメを釣りたい」という一念で、登山界ではタブーとされている「ガレ場のトラバース(斜面の横断)」を決行しました。まず僕が先頭に立ち、グラグラと動く不安定な岩々に注意しながら進みました。時々足下の岩が音をたてて深い谷底に転がり落ちていきます。そんなガレ場を冷や汗かきながら慎重に進んでいるとき、ふと、頭上を見るとワイヤーロープが土の中から垂れ下がっていました。恐らく、なぎ倒された崖崩れ防止フェンスのワイヤーロープでしょう、僕は何気なくそのロープを掴んでしまいました。すると、何とそのロープがスポッと土から抜け出たのです。その瞬間、僕はバランスを崩して転落しました。よく、人が目前に不可避の死を感じたとき、一瞬のうちにその人の今までの人生が、頭の中に走馬燈のように駆けめぐると言いますが、僕もその時、確実な死を感じましたが、なぜか恐怖心は全くなく、斜面を転がり落ちながら頭に浮かんだのは、「弟も僕を見下ろしながら兄の死を覚悟しとるやろうな。うちのラーメン屋は弟が継いでくれるやろうか?僕の死体をこんな山奥から担ぎ出すには、里の人たちの手を煩わすだろうな。・・・それにしてもまだ死なんな。そろそろやろうばってん・・・。」こんなことでした。やがて僕の体は50メートルほど滑落して、斜面の土くれにぶつかって止まりました。僕はすぐに立ち上がり、弟に手を振って生存を知らせました。そして自分の体を確かめると、骨折どころか、かすり傷もないのです。岩だらけのガレ場を50メートルも滑落して、全く無傷というのは奇跡でした。まさに九死に一生です。上から見ていた弟が言うには、僕の体は回転し、岩と岩の間の土の部分だけを選ぶように落ちていたそうです。
それ以来僕は思っています。人は自分で生きているのではなく、天に生かされているんだなと。僕が死ぬのは、その滑落事故のときではなかったわけです。久留米でラーメン屋をしなければならないという役目があったのですね。きっと人には色々な役目があって、それを果たし終えたときに、天は、その人を召し上げるのでしょう。 僕はまだまだ死にましぇん。
第百二十五話 感謝とは?
2013年4月18日 木曜日 先日、ある食べ物屋の前を通りかかったら、そのお店の外壁に大きく「ありがとう」と書かれていました。僕はすごいなと思いました。そこまで「ありがとう」という感謝の言葉を大書きして店外に宣言しているというのは、その店の社員からパート・アルバイトに至るまで、よほどお客様への感謝の心を持たせる教育が徹底しているのでしょう。 僕はまだその店に入ったことはありませんので、その真偽はわかりませんが・・・。
世間では、感謝感謝とよく耳にします。ところが真の意味での「感謝」というのは、なかなか難しいものです。僕の店でも「ありがとうございます」という基本用語は徹底させていますが、はたして従業員全員が本当に感謝の心を以てお客様にそれを伝えているのか?心のないロボットが言っているのではないか?まだまだ僕には自信がありませんし、まして店の壁に「ありがとう」の大書きなど、とんでもありません。
しかし僕は従業員にことあるごとに言うことにしています。「給料は会社からもらっているのではない。まして社長からもらっているのでもない。お客様から頂いているのです。それを忘れてはいけません」と。
また「従業員の皆さんは『働いてやってる』ではなく『働かせて頂いている』という心で働き、管理職は、従業員の皆さんに対し『働かせてやってる』ではなく『働いて頂いている』という心を常に持って下さい」ということも言い続けています。
互いに感謝の心があれば信頼関係が生まれ、労使の争いなど起こり得ません。
さて、あらためて「ありがとう」という言葉について、一風堂の社長・河原さんはこう言っています。「親に『ありがとう』を言えない者が、お客様に心からの『ありがとう』を言えるはずがない」と。同感です。
感謝の心のない「ありがとう」が相手に伝わる訳がありません。そう、「ありがとう」とは、「言う」のではなく「伝える」ことなのですね。
ところで読者の皆様、毎回僕のこんな駄文にお付き合い頂き、本当にありがとうございます。
伝わったかなぁ・・・。
第百二十四話 クレームは宝
2013年4月18日 木曜日 20年ほども前の話ですが、僕が近所のある小さな商店で饅頭を買い、家で食べようとしたところ、何とその饅頭にカビが生えていました。お客さんも少ないうらびれた店だから、商品の回転も悪くて古くなっていたのでしょう。僕はとりあえずカビの生えた饅頭をその店に持って行きました。「おばちゃん、さっき買った饅頭、カビの生えとったよ」すると、そのおばちゃん、僕が差し出した饅頭を見もしないで、「ウチはそんな商品は置いとらんし、売った覚えもなか!」と、いきなり逆ギレ。僕はけんもほろろに追い返されてしまいました。とっても印象的なお店の対応で、僕はあきれて腹も立ちませんでした。
クレームはその対応の仕方で、その店なり会社なりのレベルがわかります。
まず三流の対応、それはそのカビの生えた饅頭を売った店のように、クレームそのものを認めもしないで、しまいには逆ギレしてお客様を逆恨みするパターン。もうこれは論外ですね。
次に二流の対応。それはクレームのお客様に対して、上っ面だけで謝り、心の中では舌を出して、お客様を小馬鹿にしているというもの。こんなお店や会社は伸びないどころか、確実に衰退します。
そして、一流のクレーム対応は、まずお客様の話を真剣に聞き、話の内容を全て把握した上で、こちらに落ち度があれば、お客様の気持ちになって心から謝罪する。そしてお客様に損害があれば、誠意を以て対応するというもの。さらにその後が最も大切です。クレームというものは重要な情報であり、氷山の一角です。その情報を真剣に解析し、その不具合の要因が見つかれば、即座に改善をし、それを全社に周知徹底させるということです。
こんな会社(店)は必ず伸びます。そしてその会社は、クレームに感謝します。クレームは宝なのです。
とは言うものの、果たしてウチの会社は何流なのだろう・・・、ちょっと不安です。
第百二十三話 嗚呼、見タクナキコト
2013年4月18日 木曜日 50年も生きると、見たくないものばかり見せられます。先日、あるファミリーレストランでのこと。僕が隣のテーブルを何気なく見ると、若い女性が片膝を立て、その膝に右手の肘を乗せて食事をしていました。ずり下がったジーンズからはパンツのゴムまで見えて(見せて?)います。その正面の母親らしき年配の女性は、くわえタバコでぼんやり外を眺めていました。この光景を見て、僕は思いました。「この国の行く末を憂う」というより「この国の病気はすでに末期だ」と。この親子の姿は、戦後日本の象徴です。
アメリカ製の自由と個人主義がこの国に押しつけられて、わずか60年でかつての世界に誇れる日本人の品格は、完全に地に落ちてしまいました。身に美しいと書いて躾「しつけ」という、この美しい言葉も、その観念も、この母親には無いのでしょう。ああ、見たくなかった。「厚化粧をしてレオタードで踊る○沢○郎」と同じくらい見たくない光景でした。
もうひとつ、「毛の生えた肉だんご」と同じくらい見たくも聞きたくもないことが僕の身近で起きました。それは書きたくもないことなので書きません。