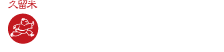第八十六話 心に残る一杯・下(改)
〜前回からの続き〜
「はい、お待ちどうさま」怪しいカウンターの下から現れたのは、紛れもない味噌ラーメンであった。厚手の白い丼に茶褐色のスープ。麺は黄色い極太の縮れ麺。トッピングは厚めのチャーシュー(枚数は忘れた)と炒めた玉ネギと太モヤシ。この環境と調理のシチュエーションで疑い深くなっていた私は「いやいや、見てくれにダマされちゃイカン、喰わにゃーわからんワカラン」と、スープをすすってみた。「・・・」さらに麺を一口。当時こんなコトバはなかったが・・・「マイウ〜!」とにかく旨い。友人も同感。やや焦がされた赤味噌が溶け込んだ鶏ガラベースのスープには、心地良い香りと深いコクがある。噛みごたえのある極太麺のモチッとした食感と、とろけるように柔らかい豚バラチャーシューとの絶妙なバランス。
私はかつて、味噌ラーメン、特にそのスープにはある種の違和感を持っていた。味噌汁のようで味噌汁でない、ラーメンのようでラーメンにあらず。そんなどっちつかずのスープにストレスを感じ、その度に注文したことを後悔した。インスタントの味噌ラーメンなどはその極みで、そこ10年程食べてなかった。しかし!この目の前の味噌ラーメンは、インスタントなんかとんでもない、本物の見事な味噌ラーメンだ。私のそれまでの味噌ラーメン観は、このラーメンによって完全に覆されたのだ。
読者諸氏には予想通りの展開だったかも知れないが、やはり北海道という大地はタダモノではない。こんな場末のスナックのような店(申し訳ない)で、こんなに旨い、プロ風に言えば「最強なる商品力を持ったラーメン」が当たり前のように出てくるという驚き。さらにママがポツリポツリと語るには、このあたりでは一般家庭でも、母親が手作りのラーメンをこれまた当たり前のように作るそうで、寒い日は子供たちにとって最高のご馳走だとか。ママ自身も子供の頃からお母さんの作る味噌ラーメンで育ったそうだ。この町では「お袋の味」とは、味噌汁ではなく味噌ラーメンということだ。当世流行の「ラーメンご当地」とか、どこかのラーメンフリークやメディアが仕掛けたような薄っぺらなものではなく、この地は正に気候風土と人の生活そのものが、ラーメンに適した土地なのである。
そんなママの話を聞きながら、私たちはスープも残さず完食したことは言うまでもない。
やがてその「斜里の名店」をあとにしながら私は、昔小説か何かで読んだ「子供から年寄りまで町の住人全員が泥棒」という話を思い出し、思わず想像してしまった。「ひょっとしたらこの町は住人全員がラーメン屋なのかもしれない…恐ろしか」と。
それから長い時が流れてしまい、いまその店の名をどうしても思い出せない。その後そのママと店がどうなったのかも当然わからない。いつかこのコロナ禍が立ち去れば、再び斜里の地を訪れて場末のスナックを見つけたら、迷うことなく味噌ラーメンを注文したいと思っている。