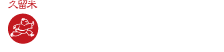第九十七話 原爆投下の目撃者
諫早の有喜(うき)という、のどかな農村に母の実家がある。私が小学生のころ、夏休みには毎年そこを訪れていた。実家のすぐ近くの小さな丘の上には有喜小学校があり、その丘を眺めながら母はある体験談をよく語っていた。それは、その小学校で世界的大事件を目撃したと言う話。
昭和6年生まれの母が通っていた有喜小学校は当時「有喜国民学校」と呼ばれていて母は高等科2年生。その年の夏、昭和20年8月9日の昼前のこと。この日、学校は夏休みの出校日だった。朝礼も終わり掃除の時間、突然空襲警報が鳴り響いた。
この空襲のない農村でも、警報が鳴れば生徒たちは素早く防空ずきんを被り机の下に身を潜める。やがて警報は解除されて掃除再開。母は小高い丘をくだった石段下の井戸でバケツに水を汲んでいた。すると爆撃機の音が聞こえる。空を見上げると、自分の頭上に銀色のB-291機があった(当時は小学生でも、その米軍最大の爆撃機のカタチも音も知っていたそうだ)。「空襲警報は解除されたのに何で?」と思いながら見ていると、B-29は西に向かって飛び、やがて飯盛山の方角、長崎上空あたりで、2つの落下傘(パラシュート)を投下した。バケツを持って石段を上り切った母はその時、昼というのに目が眩むほどの閃光に包まれた。驚きながらも校庭を横切って校舎に入ったその瞬間、今度はドーンという凄まじい轟音。それは後に言う原子爆弾であった。
昭和20年8月6日、米軍は人類史上最悪の兵器・原爆を、初めて広島に投下。さらにその3日後には長崎へ投下した。広島12万人・長崎7万4千人という20万人近い命が一瞬にして奪われた。そのほとんどが一般市民。これで日本の敗戦は決定的なものとなった。私の母は、その悪魔のごとき歴史的瞬間を目撃した証人のひとりなのだ。有喜は長崎市から幾つかの低い山を隔てた地であったために原爆の直接被害は避けられたが、そこが被爆地の風下に位置していたのか原爆投下直後から白い灰が村中を覆い、周囲の田畑も一面真っ白になったという。それが後にいわれる「死の灰」である。太陽も、その灰のために真っ赤な火の玉のようになったそうだ。それは翌日まで降り続いたという。14歳のときにその灰を浴びたという母は、被曝の心配をしながらも長らく元気でいたが9年前に81歳で亡くなった。
母がバケツを持って登り下りした、小学校の急勾配の石段も木造校舎も、私が小学生の頃はまだ残っていたが、数年前、久方ぶりに訪ねてみると、石段のあった所は雑木に埋もれてその痕跡もなくなり、なだらかな舗装道路となっていた。やはり木造校舎はモダンな校舎に生まれ変わっていた。
今年もその日から76回目の8月を迎える。近代化という名の波は、歴史の記憶を侵蝕し、風化させるものであっては欲しくない、と思った。