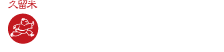第百二十九話 映画「ラーメン侍」幻の脚本⑱
〜前号からの続き〜
屋台は、いまや全国に誇れる※久留米と博多の名物であり、まちの貴重な観光資源でもある。暖簾をくぐると、客と主人、また客同士の距離感がない。知らぬ者同士がすぐにうち解け合うことのできる温もりの空間である。
ところが平成6年、福岡県警は昭和遺産というべき〈屋台〉を自然消滅させるべく「道路使用許可は現営業者1代限りとする」という方針を打ち出し、その権利の売買はおろか、子への譲渡すらも禁止した。かくして、このまちの夜の風物詩でもある屋台の灯は確実に消えつつある。屋台という、戦前から続く愛すべき庶民文化を、誰が何のために消し去ろうとするのだろうか。
飲み干したコップ酒をカウンターに置いた稲富、いつもの恵比寿顔がやや神妙な顔になっている。「のぼっちゃん・・・やっぱしここの立ち退きはしょんなかばい。国鉄駅前に並びここ西鉄駅前は久留米の玄関口やろ、役所としてはその駅前の目抜き通りが未だ穴だらけのコンクリート製やけん、コレば流行りのアスファルトにせにゃいかんげな。ついでにこの銀行前の歩道も拡張して久留米の玄関前らしくするっち。この計画は前の議会で可決しとるし、屋台の道路使用許可を管轄しとる警察署もコレに同意しとった。新人議員の俺ひとりのチカラじゃ、もうどうにもならんとこまできとった・・・」
昇は黙って聞いているが、さすがに動揺しているようで、珍しく不安な顔をしている。嘉子の方がかえって肚の据った表情だ。
そこへ若い男の客が入ってきた。20代後半のその男は、眼光鋭く頬に短い傷がある、上着は肩に掛けただけの絵に描いた遊び人風である。男は周囲を上目使いに見回しながら座ろうとした、そのとき焼き鳥を焼いている端午と目があった。ふたりの動きは一瞬止まった。すかさず昇が男に言った。
「マサオか」男は上目使いのまま昇に向き直り、小さく頭を下げた。「のぼっしゃん、ごぶさたです」「ラーメン食いに来たとか?それとも何かハナシか?」「いや・・・ただ、のぼっしゃんの顔ば久方ぶりに見とうなって」
歪んだ笑みで男が言った。昇の目が鋭く光った。
「そのツラ・・・、とうとうお前もホンナモンになってしもたな」
「いやァ・・・はい」
~次号へ続く~
※令和6年現在久留米の屋台は絶滅状態