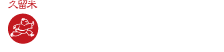第百三十話 最終回
座りながら頭をかくマサオの二の腕には、刺青が見えた。いや、見せようとする仕草だった。昇はそんなものには目もくれず、マサオの前にコップを置き、1升瓶の酒を注ぎながら言った。「お前はこの1杯で帰れ。そして、もう来るな」
マサオは三白眼で昇を睨んだ。屋台の空気が重く淀んだ。「のぼっしゃん、そんじゃこれで」
稲富は小銭をカウンターに置いて、2人をちらりと見ながら、のれんをくぐり出た。焼き鳥席では、きなこ相手ににこやかに飲んでいた2人の男性客も、この空気から逃れるように帰ろうとしている。端午は焼き鳥を返しながら、マサオの方を見つめている。
マサオは置かれたコップ酒を一気に飲み干すと、袖をめくり、大きく露出した牡丹の刺青の腕で唇を拭きながら、低い声で言った。「のぼっしゃんも、昔の舎弟には冷とうなったね」マサオは100円札をコップの下に置いた。「釣りはいらん」
マサオは暖簾をくぐり出た。それを追うように端午も外へ出た。
昇は、コップの下の2つ折りにされた100円札の折り目から、かすかにはみ出た白いメモを見た。昇は右手に空コップを取り上げ、それも嘉子に渡しながら、左手で100円札とメモを素早くわしづかみにして、前掛けのポケットに押し込んだ。嘉子はそのメモに気づいていた。
屋台から少し離れた歩道では、端午とマサオが向かい合っている。あごを上げ、見下ろすようにマサオが言った。「ダンゴ、今度はお前がのぼっしゃんの舎弟や?」
端午は肯きもせず、マサオを睨みながら言った。
「マサオしゃん、何の用か知らんばってん、昇のアニキには近づかんでくれんですか」
「ほう、俺に指図や?お前もえろうなったね・・・またにゃ」
マサオはネオンの中に消えていった。
・・・と、ここまで書いた時点で映画の撮影スケジュールの都合により、続きは脚本家の我妻正義氏にバトンタッチすることとなった。映画(Amazon prim videoで配信中)をご覧になった方はお気づきと思うが、私の脚本はいくつかのシーンで採用されたものの「あらすじ」は大きく様変わりし、まさに「幻の脚本」となった。このコラムで1年半に亘ってその脚本を掲載させていただいたのも、幻のまま埋もれて消える前に一度陽の目を見せたかったからである。読者には「幻の脚本」を通して、戦後久留米のラーメン黎明期というべき時代のエネルギーを感じてもらえたなら幸甚である。
さて唐突ながら、この「ラーメン外伝」は今回を以て最終回とさせていただきたい。
私のコラム執筆は1999年の第1回ラーメンフェスタに併せて始まった。以来25年間、地元2誌(くるめすたいる・Second)で通算276話を書かせていただいた。
この稿を借りて2誌に深く感謝を申し上げたい。
豚骨ラーメン発祥地・久留米を全国に発信することで、地域活性化の一助としたいという思いで、この4半世紀、微力ながらさまざまな活動を行なってきた。
今や後進も育ち、「ラーメンのまち久留米」という認識もそれなりに全国に定着したと感じる。従って私自身もそろそろ一区切りしたいという考えに至った。
またいつか、スポット的にコラムを書かせていただくこともあるかもしれない。
その日まで読者の皆様もお達者で。ありがとうございました。