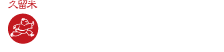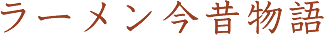第八十話 追憶の底
最近、忘れていた遠い昔の一コマが、なぜかふと甦りました。
それはもう四〇年以上も前のこと。僕は保育園から帰るといつも、そのまま両親が営むラーメン屋台に向かいました。テレビもないキノコの家(初代熱風録・その5に登場)で淋しく留守番するよりも、両親のいる屋台の周辺の歩道にチョークで絵を描いて遊ぶほうが何より楽しく、また両親もその方が安心だったようです。今のように幼児の誘拐や殺人など皆無の良き時代です。僕の遊び場は夜の町の歩道でした。
お絵描きに遊び疲れると、僕は決まって近くのあるところへ遊びにいきました。それは久留米なのに「道頓堀」という名の歓楽街の一角にポツンと座っている女性の易者さんのところです。 彼女はいつでも優しく幼児の僕の相手をしてくれました。細くて色白の静かな人で、年の頃は三〇ちょっと過ぎといったところでしょうか、小さな台には手の平の絵が描かれたロウソクの行燈が置かれています。その揺れる灯り越しに見るその人の笑みはいつも、何となく淋しそうでした。
ある日、遠くの町へ家族で出かけたときの帰りのこと。夜汽車の窓の遠い町明かりを、僕はぼんやり眺めていました。時おり足早に過ぎ去る遮断機の音の向こう、闇に浮かぶ家明かりが、ゆっくりと流れていきます(そういえば“千と千尋の神隠し”の水面を静かに走る電車の幻想的なシーンを見たときも同じ感覚でした)。僕はふと、あの薄暗い家明かりのなかに、道頓堀の易者の女性がいるような気がしてなりませんでした。
数日後の夜、そのことを確かめようと、道頓堀の角に行ってみましたが、その人はいませんでした。そしてその後も、その優しい易者の女性は僕の前に現れることはありませんでした。
そして時は流れ、僕が小学五年生の頃のこと。家の近くに銭湯があり、ある日その銭湯の向かいに小さなタコ焼き屋が開店しました。
僕は銭湯で一風呂浴びた後、さっそくそこにタコ焼きを食べに行くと、その店は三十後半くらいの細身の女性が一人でやっていました。この人もどこか翳りを感じる静かな人でしたが、胸の病でも患っているのでしょうか、カチャカチャと千枚通しでタコ焼きを返す手を、ときおり休めては後ろを向いて「コホン、コホン」と咳をしています。僕は不潔さも感じず、千枚通しの音と咳のリズムがなぜか心地よかったのを憶えています。その時「もしかしたらこの人は、あの道頓堀の易者さんでは?」という思いがよぎりましたが、その頃は僕も五年生でしたから、幼児期のように大人の女性に屈託なく問いかけることもできないまま・・・、やがてほどなくその店もその人もどこかへ去ってしまいました。
今回、ただそれだけの話でしたが、遠いとおい過去の記憶が突然わき上がる、そんな経験は皆さまにもおありでしょう。
何か、意味があることかもしれませんね。